Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
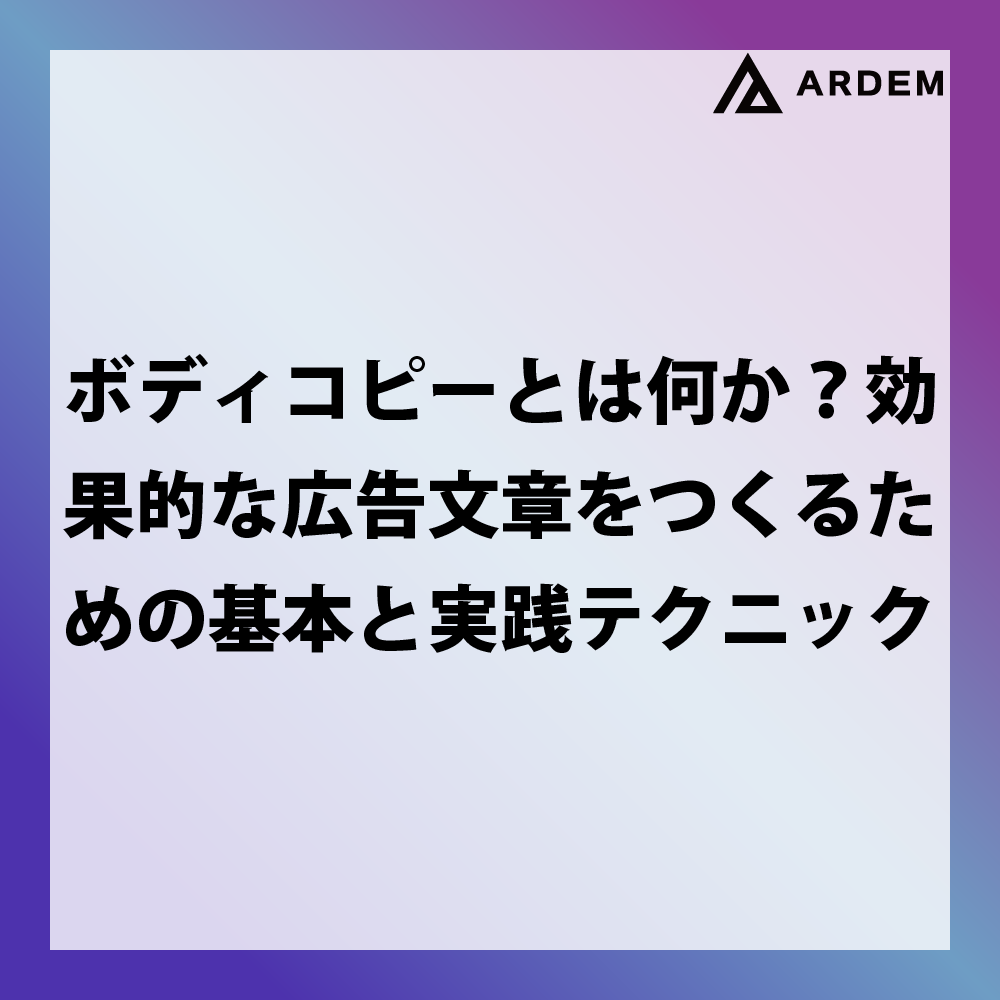
目次
「キャッチコピーは思いつくけれど、ボディコピーでつまずいてしまう」
広告や販促に携わる方なら、一度はそんな経験があるかもしれません。ボディコピーとは、広告の本文部分。商品の魅力や価値、他との違いなどを、より深く、丁寧に伝える役割を担っています。たとえ心をつかむキャッチコピーが書けたとしても、ボディコピーで読み手の関心をつなげられなければ、購入や問い合わせといった行動にはつながりません。
本記事では、「そもそもボディコピーとは何か?」という基本から、その役割・他のコピーとの違い、実際にどのような場面で使われているのかまでを丁寧に解説します。これからコピーライティングを学びたい方、広告効果を高めたい中小企業のWeb担当者の方にとって、明日から活かせる実践知をお届けします。
伝わるホームページを作りたい方へ
どれだけ魅力的な商品やサービスでも、それを伝える文章や構成が整っていなければ成果にはつながりません。ARDEMでは、ボディコピーを含め、読み手の心に届くホームページ制作を行っています。
伝えたい価値がきちんと伝わる。そんなホームページをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
▶ ホームページ制作の無料相談はこちら
ボディコピーとは、広告や販促物における「本文」にあたる部分を指します。商品やサービスの魅力、使い方、他社との違い、導入することで得られる未来などを、論理的かつ感情的に訴求する文章です。
役割としては、読者に対して「興味」や「関心」を維持させながら、次第に「納得」や「欲求」に導くこと。つまり、キャッチコピーで振り向かせた後の“引き留め役として、読者との対話を深める橋渡し的存在とも言えます。
特にWebサイトやチラシなど、比較的長いコンテンツではこのボディコピーの質が成果を大きく左右します。読み手の理解度や行動率(CV)を高めるために、わかりやすさと説得力を両立させることが求められるのです。短くても、しっかりと「伝わる」「響く」文章を組み立てる技術が、ボディコピーの肝になります。
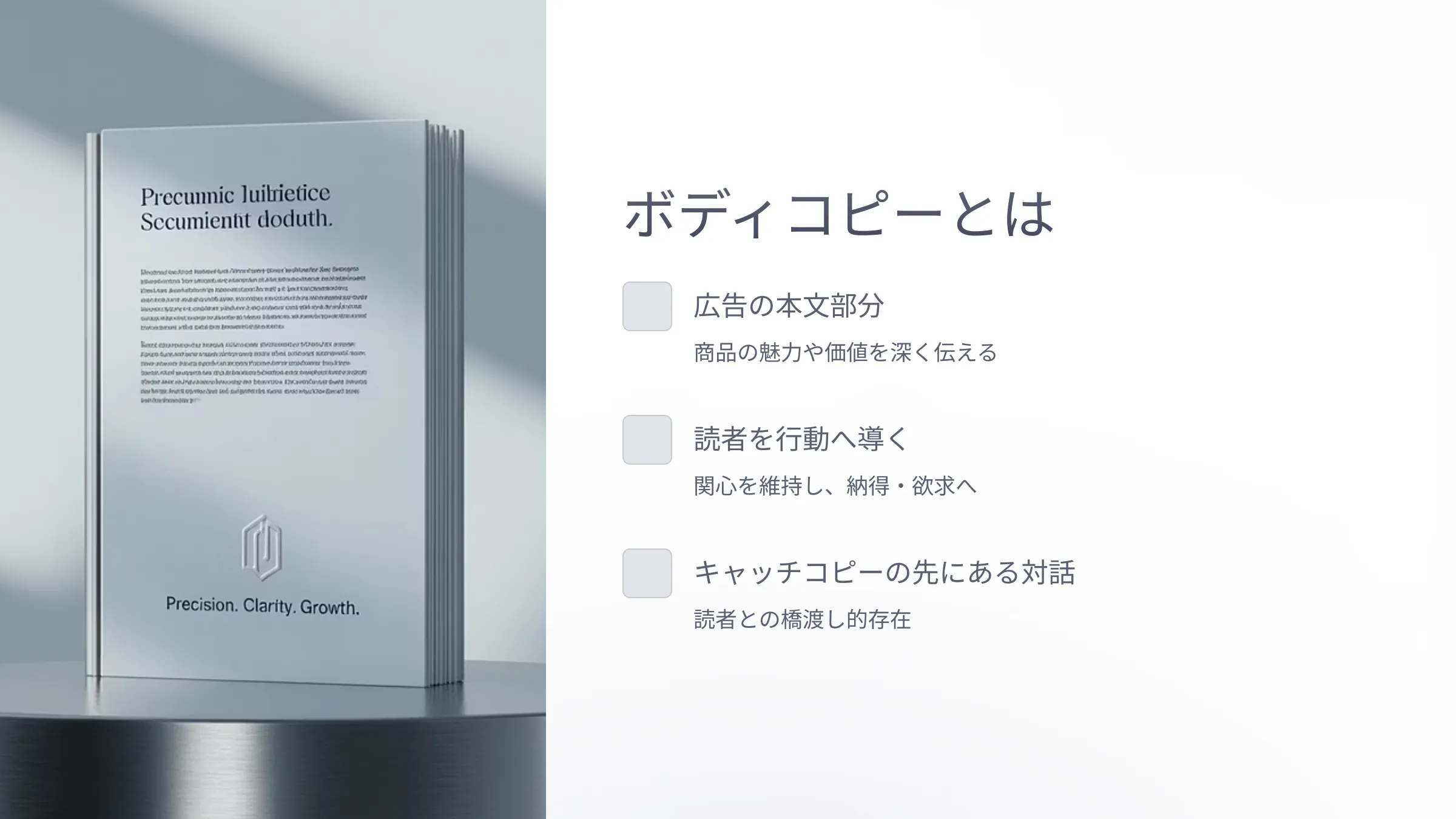
広告文には、ボディコピー以外にも「キャッチコピー」「リードコピー」と呼ばれる要素があります。これらはそれぞれ役割が異なり、読み手の心理を段階的に動かす仕組みを作っています。
つまり、これらは三位一体で機能し、それぞれが“導線としての役割を果たしているのです。ボディコピー単体で考えるのではなく、全体構成のなかでどう配置されているかが、成果に直結します。
ボディコピーは、あらゆる広告媒体で使用されています。中でもよく見られるのが、次のような場面です。
つまり「ただ文章を書く」のではなく、媒体の特性や読者との関係性をふまえて組み立てるのが、優れたボディコピーなのです。

どれほど素晴らしい商品であっても、その魅力が読み手に伝わらなければ意味がありません。ボディコピーにおいて重要なのは、「読まれる文章」であること。読まれないコピーには、いくつかの共通点があります。
まず、前提知識を無視して難解な専門用語を並べたり、一方的に企業目線で話を進めてしまったりするケースです。これは、読者の関心よりも自社の伝えたいことを優先してしまっている状態。逆に読まれるコピーは、読者が抱えている課題や不安に寄り添い、対話をするようなトーンで進行します。
また、文章に「流れ」があるかどうかも大切です。支離滅裂だったり、結論が見えなかったりするコピーは途中で離脱されがちです。読者が自然に読み進めたくなる構成と、感情にフィットした言葉選びが、読まれるボディコピーの条件といえます。
ボディコピーは、単に情報を羅列するものではありません。読者の心の動きに寄り添いながら、「関心を持つ→共感する→行動する」という段階を踏ませる設計が求められます。
まずは「自分ごと化」してもらうこと。冒頭で読者の悩みや状況に言及し、「あ、これは自分のことかも」と感じさせることが最初の一歩です。そのうえで、「あなたと同じような悩みを持っていた人が、こんなふうに解決しました」というストーリーを示すと、共感が生まれます。
最後に、納得と安心を与えるデータや実績を添えることで、行動へのハードルを下げることができます。人は、理由なく行動することに不安を感じる生き物です。だからこそ、ボディコピーには「動機」や「根拠」をセットで与えることが重要なのです。
読者に「行動」してもらうには、心理的な仕掛けを意識したボディコピーが効果的です。人の心の動きには一定のパターンがあり、それをうまく活用することで成約率は大きく変わります。
代表的なアプローチのひとつが「ベネフィット訴求」です。機能や特徴ではなく、「それを使うことでどんな良いことがあるのか」を中心に伝えることで、読者の未来を想像させ、購買意欲を刺激します。
また、「限定性」や「社会的証明」も有効です。「○○名限定」「すでに○○人が利用」などの情報は、人の“今動かないと損するという心理に働きかけます。さらに、読者と似た立場の人の声や事例を見せることで「自分にもできそう」という安心感を与えることができます。
つまり、成約率を高めるには、ロジックだけでなく感情にもアプローチすること。理性と感情の両方を満たす文章が、成果につながるボディコピーになります。
ボディコピーを書く際には、「どの順序で伝えるか」が非常に重要です。どんなに良い要素が含まれていても、構成がバラバラでは読者に届きません。基本的な流れとしては、次のようなステップを意識しましょう。
1. 読者の状況を想定した書き出し
冒頭では、読み手の課題や興味を代弁するような言葉から始めます。「〇〇で悩んでいませんか?」といった問いかけが効果的です。
2. 商品の概要と特徴の提示
次に、商品やサービスの内容を簡潔に伝えます。ここでは、特徴よりも「どんなことができるか」「何が解決できるか」を先に示しましょう。
3. 他との違いや強みの説明
他社との違いや、自社ならではのポイントを丁寧に解説します。競合との差別化が読者の興味をつなぎます。
4. 利用者の声・実績の紹介
「実際に使っている人がいる」という事実は、大きな安心感につながります。数字や事例を交えると効果的です。
5. 行動を促すクロージング
最後に、読者の背中を押す言葉とCTA(行動喚起)で締めくくります。「今すぐお試しください」「無料でご相談いただけます」といった一言が、行動のきっかけになります。
このように、起承転結のような構成を意識することで、読みやすく、説得力のあるコピーが書けるようになります。
ボディコピーに説得力と共感性を持たせるには、情報の羅列ではなく「物語」として語る視点が役立ちます。これがストーリーテリングの手法です。たとえば「過去にこんな悩みを抱えていたAさんが、この商品と出会い、どう変わったか」という流れで伝えると、読み手は自分をそのストーリーに重ねて考えることができます。
加えて、コピー全体を「ベネフィット重視」で組み立てることも大切です。特徴やスペックを伝えるだけでは、読者の心は動きません。重要なのは「それを使うと、自分にどんな良いことがあるのか?」という視点です。
たとえば「24時間サポート対応」という事実があったとして、それを「夜間の急なトラブルにもすぐに相談できます」と表現することで、読者のメリットがはっきり伝わります。単なる事実を、具体的なベネフィットに翻訳する力が、ボディコピーの質を大きく左右するのです。
読者に納得してもらうには、感情的なアプローチだけでなく、客観的な「裏付け」が必要です。ボディコピーの中で、信頼性を高めるための証拠やデータを適切に挿入することで、文章全体の説得力が格段に向上します。
たとえば、「この製品は使いやすいです」と書くよりも、「利用者の92%が“操作が直感的で分かりやすいと回答」といったデータを提示する方が、読者の信頼を得やすくなります。また、第三者機関の評価や受賞歴、顧客の声(口コミ・事例紹介)も有効です。
重要なのは、ただ数値や実績を並べるのではなく、「なぜこの情報を伝えるのか」という文脈の中に組み込むこと。証拠は文章を補強する“スパイスであり、流れを邪魔しない形で自然に組み込むのが理想です。
ボディコピーを書くうえで、論理的な流れを意識することは非常に重要です。その際に役立つのが、広告・マーケティングの現場で広く使われているフレームワークです。特に代表的なのが「AIDMA」や「PASONA」です。
AIDMA(アイドマ)は以下の5つの段階で構成されます。
この流れを意識して構成すれば、自然と読者の感情を段階的に動かす文章になります。
一方、PASONA(パソナ)は悩みを解決するストーリー展開に強みがあります。
とくにWeb広告やセールスページにおいて、PASONAは非常に効果的です。「困っている人を助ける」という流れは、読者の共感を得やすく、反応も取りやすい構成です。
これらの型をうまく取り入れることで、ボディコピーに「迷いのない筋道」を与えることができ、成果にも直結します。
同じ内容でも、使う言葉や語尾によって、読み手に与える印象は大きく変わります。ボディコピーでは、魅力的な言葉選びと、スムーズに読ませる語尾の使い方がカギになります。
まず、読者の語感に近い表現を選びましょう。たとえば「最先端の技術を搭載」よりも「最新の技術で、誰でも簡単に使える」と表現したほうが親しみやすく、伝わりやすくなります。専門用語や硬い言い回しよりも、平易でイメージしやすい言葉が好まれます。
また、語尾には注意が必要です。すべてが「〜です」「〜ます」では、単調で読み疲れてしまいます。ときには「〜できます」「〜してみませんか?」「〜という声も届いています」と変化をつけることで、読者のテンポに寄り添うことができます。
さらに、「自分ごと化」しやすい表現──たとえば「あなたにもできる」「今日から始められる」などは、行動への後押しになります。言葉選びと語尾の工夫は、ボディコピーの“肌触りを決める重要な要素なのです。
ボディコピーを書き慣れていない方が陥りやすい失敗には、いくつかのパターンがあります。ここでは代表的な例と、その回避策を紹介します。
1. 読者視点を欠いている
「自社の伝えたいこと」ばかりを書いてしまい、読者にとってのメリットや興味に触れていないケースです。これは「スペックの羅列」になりがち。対策としては、「この情報は読者のどんな疑問に答えているか?」を常に自問しながら書くことです。
2. 感情に訴えかける要素がない
機能説明ばかりで、読み手の心に響く“物語や“共感の言葉が不足していると、説得力が弱くなります。実体験のエピソードや、顧客の声を交えることで、感情に触れるコピーになります。
3. 読みにくい構成・文字量
長文になりすぎて情報が散らかっていたり、改行がなく詰め込みすぎたりすると、読む気を失わせてしまいます。構成を整理し、見出し・改行・箇条書きを適度に活用することで、読みやすさを確保できます。
これらを意識するだけでも、ボディコピーの質は確実に向上します。上手く書こうとするより、「読み手に伝わるかどうか」を基準に見直すことが、何より大切です。
コピーライティング初心者に多いのが、考える前にとにかく書き出してしまうという行為です。思いつくままに文章を並べても、読者にとって意味のあるコピーにはなりません。書き始める前に「誰に、何を、どう伝えるのか」という設計図を描くことが重要です。
まず、伝えたい商品の特徴や魅力を書き出し、それがどんな読者にどのような価値を提供するのかを整理しましょう。また、目的(認知/販売/問い合わせなど)を明確にすることで、コピー全体の軸が定まります。文章を書くのは、情報と意図を整理した“後”でいいのです。
「すべての人に伝えたい」と思って書いたコピーは、結果的に“誰にも刺さらない”文章になりがちです。伝えるべき相手を絞り込むことが、伝わるコピーへの第一歩です。
性別・年齢・職業・ライフスタイル・抱える悩み・関心事など、できるだけ具体的にターゲット像を描きましょう。たとえば「30代の共働き主婦で、時短家電に興味がある人」といった具合です。読者像が明確になれば、自然と使う言葉や伝え方も絞れてきます。
読み手の気持ちや行動を想像できていれば、「どんな言葉が響くか」「何に不安を感じているか」が見えてくるようになります。コピーは技術だけでなく“相手理解”がすべての出発点なのです。
一度書いたコピーを「書きっぱなし」にしてしまうのも、初心者にありがちなミスです。自分ではよく書けたと思っていても、他人の目線で見れば伝わりづらかったり、説得力に欠けたりすることは珍しくありません。
書き終えたら、必ず時間を置いて読み返すこと。できれば声に出して読んでみると、不自然な流れや表現のくどさにも気づきやすくなります。また、「この文章は本当に読者のメリットになっているか?」「伝える順番は論理的か?」といった視点でチェックすることも大切です。
可能であれば、第三者に読んでもらってフィードバックをもらうのも良い方法です。自分の中だけで完結せず、読み手の目線を意識した客観的な見直しを習慣にすることで、コピーの精度は着実に上がっていきます。
「せっかくホームページを作ったのに反応がない」と感じている方へ。Webマーケティングの基本から集客導線の整え方まで、実践的に解説した一記事です。改善ポイントを明確にしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
よく混同されがちな「マーケティング」と「ブランディング」の本質的な違いを、初心者にもわかりやすく解説。自社の戦略設計を見直したいと考えている方におすすめの一記事です。
見た目のデザインだけでなく、企業の想いや強みを「言葉」で届けるブランディングサイト。その役割や効果、成功事例を交えて解説しています。差別化したホームページを作りたい方にぜひ読んでいただきたい内容です。
ボディコピーは、広告やWebサイトなどの文章の中で、もっとも多くの情報を読者に届けるパートです。単なる説明文ではなく、読者の「共感」や「納得」、そして「行動」へと導く役割を担っています。
本記事では、ボディコピーの定義や他のコピーとの違いに始まり、読まれる文章の条件、構成の基本、具体的な書き方のテクニック、そしてよくある失敗とその回避策までを解説してきました。
コピーライティングにおいて大切なのは、テクニックを覚えること以上に、「誰に」「何を」「なぜ」伝えるのかを深く考える姿勢です。読む人の立場になって設計し、伝わる言葉を選び抜く。そんな積み重ねが、成果につながるボディコピーを生み出します。
広告文やWebコンテンツを通じて読者の心を動かしたい方は、まずはボディコピーの基本を押さえ、着実に実践していくことから始めてみてください。
コピーまで含めたWebサイト制作をご検討中の方へ
「何をどう伝えるか」でホームページの成果は大きく変わります。ARDEMでは、企画・設計・ライティングまで一貫してサポートし、御社の魅力を言葉とデザインで形にします。
ボディコピーの改善やコンバージョンに強い構成設計まで対応可能です。まずはご要望をお聞かせください。
▶ お問い合わせフォームはこちら
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。