Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
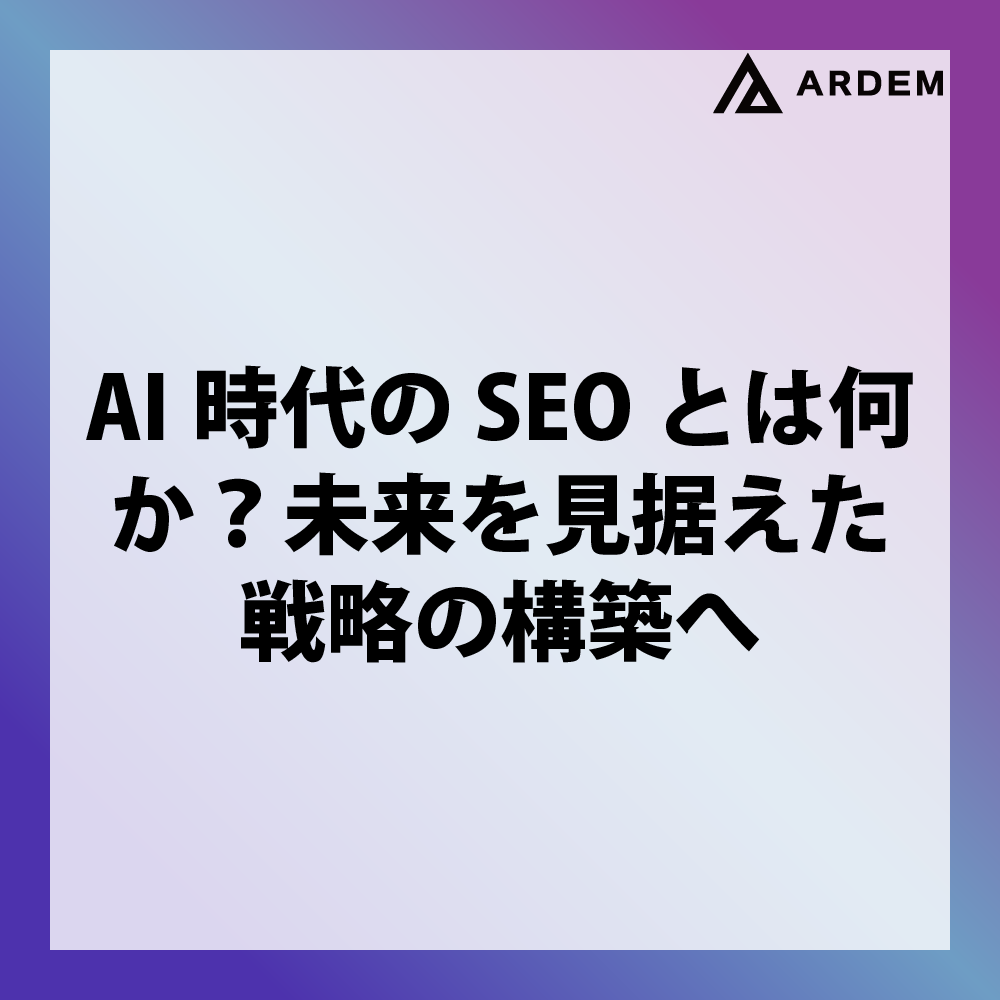
目次
近年、AI技術の飛躍的な進化が、私たちの生活やビジネスのあり方に大きな変化をもたらしています。特にSEO(検索エンジン最適化)の領域では、AIの影響が無視できないものとなっています。従来は「検索キーワードの最適化」や「被リンクの獲得」などが中心だったSEOも、AIの登場により“検索エンジンの理解力そのもの”が高度化し、求められる戦略も大きく様変わりしてきました。
Googleが推進する検索アルゴリズムの進化、ChatGPTやBardといった生成AIの台頭、そしてゼロクリック検索の増加など、情報の取得プロセスは新たなフェーズへと移行しています。こうした環境下で、企業がデジタルマーケティングを成功に導くためには、「AI時代のSEO」という新たな視点から戦略を見直す必要があります。
この記事では、AIの進化がSEOにどのような影響を与えているのか、そしてこれからの時代に通用するSEO戦略をどう構築すべきかについて、体系的に解説します。
AI時代のSEOに不安を感じている、もしくは何から始めるべきか迷っている方へ。ARDEMでは、AIを活用したSEO支援から、貴社に最適な戦略の設計までトータルでサポートしています。
ぜひお気軽にご相談ください。
▶ SEO無料相談はこちら
AI技術の進歩により、検索エンジンは単なるキーワードベースのマッチングから、「文脈」や「意図」を読み取る次世代の理解モデルへと進化しています。Googleが導入した「BERT」や「MUM」といった自然言語処理アルゴリズムは、検索クエリの意味をより深く理解し、ユーザーが本当に求めている情報を提示する能力を高めています。
これにより、従来のようにキーワードの出現回数を増やすだけの施策では、検索順位の向上は見込めなくなりました。代わりに、「誰に向けた、どんな意図に基づいたコンテンツか」を的確に設計することが、検索エンジンとの“対話”の鍵となっています。
つまり、SEOは“機械に向けた最適化”から“ユーザーの意図に対する最適な答えを提供する”という、本質的な情報設計力を問われるフェーズへとシフトしているのです。
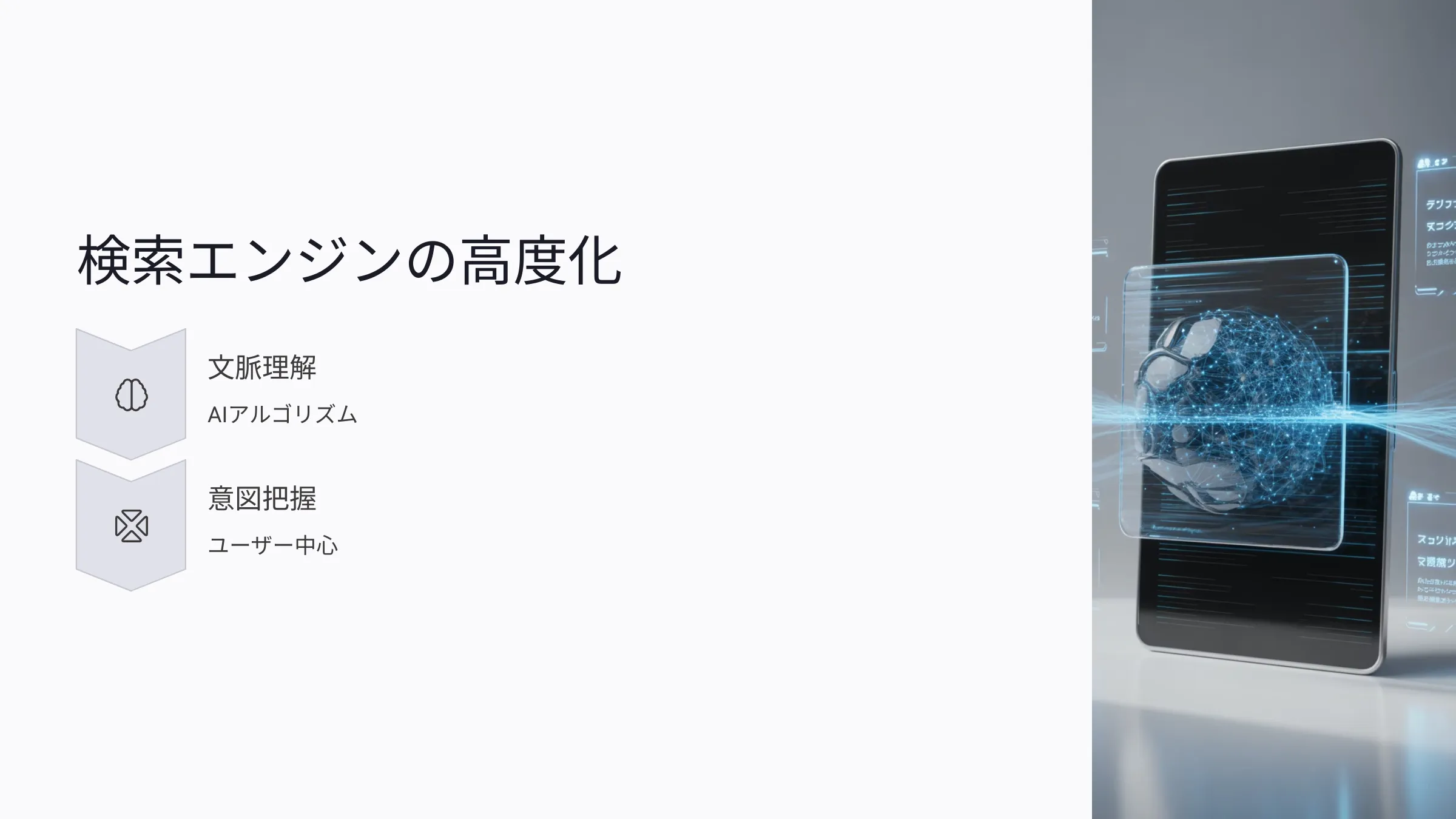
ChatGPTやBardといった生成AIの登場は、情報の取得方法そのものを変えつつあります。従来の検索行動では「検索→リンクをクリック→情報を探す」という手順が主流でしたが、これらの生成AIはユーザーの質問に対して直接“答え”を提示するという構造を持っています。
その結果、ユーザーは検索結果のリンクを踏まずに、AIの回答のみで満足する「ゼロクリック検索」の頻度が増加しています。これにより、SEOは検索順位を上げるだけでは不十分となり、「AIによって参照されるコンテンツであるか」という新たな評価軸が必要となります。
AIに取り上げられるためには、オリジナリティの高い一次情報や、明確なエビデンスを持ったコンテンツが不可欠です。単なる情報の寄せ集めではなく、独自の視点・専門性が求められるようになっているのです。
AIが進化したことで、検索エンジンはユーザーの「検索意図」をより深く理解できるようになりました。たとえば「パンケーキ 作り方」と「パンケーキ カロリー」は、同じキーワード「パンケーキ」を含んでいても、目的はまったく異なります。
これまでのSEOでは、こうした違いに明確に対応できていないコンテンツも上位表示されるケースがありましたが、AIの導入により、ユーザーの目的に合致したコンテンツのみが上位表示されやすくなっています。
そのため、SEOにおいては「検索キーワードの羅列」ではなく、「検索意図の構造化」が重要になっています。コンテンツ制作者は「ユーザーがどんな課題を抱えているか」「何を知りたいのか」「どのような行動をとりたいのか」といった点を読み取り、自然言語でその意図に応える文章設計が求められます。
AIの進化に伴い、SEOの実務も大きく様変わりしています。特に、従来は人の手で地道に行っていたキーワード選定やコンテンツ設計、SEOライティング、構造化データ対応などの業務が、AIによって支援・自動化されるようになってきました。ここでは、実務における具体的な活用方法と、その効果、そして注意点について解説します。
かつてはGoogleキーワードプランナーや関連キーワードツールを使いながら、地道に検索ボリュームや競合性を調べていたキーワード選定。しかし、現在はAIツールを活用することで、より短時間かつ網羅的にユーザーの検索ニーズを抽出できるようになっています。
たとえば、自然言語処理に対応したAIツールでは、単なるキーワードの羅列ではなく「トピッククラスター」や「検索意図(インテント)」に基づいたキーワードの分類が可能です。これにより、単一キーワードごとにページを分けるのではなく、意図に応じた情報構造に再設計することができ、検索エンジンからの評価も高まりやすくなります。
さらに、AIは競合サイトの構成分析や共起語の抽出も高速に行えるため、コンテンツ設計においても、ユーザーが求める情報を過不足なく網羅できる骨組みを短時間で設計できます。結果として、企画・構成段階での工数を大幅に削減できるだけでなく、戦略性の高いコンテンツ制作が可能になります。
AIライティングツールの活用は、SEO実務における大きな革命です。見出しごとの要点を指示するだけで、一定の品質の本文を自動生成できるため、作業効率が格段に向上します。特に、SEO向けのテンプレートに沿って文章を生成することで、読みやすさ・キーワードの適切な分布・見出し構造の最適化など、SEOの基本を抑えた原稿を短時間で制作することが可能になります。
一方で、AIのライティングには明確な限界もあります。例えば、
といった要素は、現時点のAIだけでは不十分なケースが多く、人間の手による調整や追記が必須です。
特にYMYL(Your Money or Your Life)領域では、信頼性や正確性が強く求められるため、AIだけに任せた記事では検索上位が難しくなります。そのため、AIはあくまで「下書き支援ツール」として活用し、最後は人の視点で調整・監修するワークフローが最適です。
SEOにおいては、ページの表示速度、内部リンクの最適化、構造化データのマークアップなどの「技術的SEO(テクニカルSEO)」も非常に重要です。従来はこれらの施策を、開発者やマークアップの専門知識を持つ担当者が手作業で行っていましたが、現在はAIの支援により、より正確かつ効率的に対応できるようになっています。
たとえば、構造化データに関しては、製品情報・FAQ・レビュー・記事タイプなど、目的に応じたスキーマをAIが自動生成・提案してくれるツールも登場しています。これにより、リッチリザルト(強調スニペット)表示を狙った最適化がスムーズに行えるようになり、CTR(クリック率)向上につながります。
また、Webサイト全体の内部リンク構造を分析し、ユーザー行動や検索意図に応じたリンク設計をAIが提案するケースもあります。これにより、クロールの効率やページ評価の分散を防ぎ、SEOスコアの底上げが図れます。
さらに、HTMLの構造やメタデータの最適化など、細かな部分でもAIが問題点を洗い出し、修正案を提示してくれるため、技術的なミスや見落としを防ぐことができます。
AIが検索アルゴリズムにもコンテンツ制作にも関与する現代において、SEOで成果を出すための基準は変化しています。もはや、キーワードの数や被リンクの数だけでは上位表示は難しくなりました。ここでは、AI時代のSEOで特に意識すべき3つの成功要因について解説します。
Googleがコンテンツの品質評価指標として提示しているE-E-A-Tは、AI時代のSEOでも中心的な評価軸です。特に、E(Experience:経験)が加わったことで、実際に体験したことに基づくリアルな視点がより重視されるようになりました。
たとえば、医療、金融、法律、不動産などのYMYLジャンルでは、専門家や資格保持者による執筆・監修があるかどうかが、検索結果の順位に大きく影響します。さらに「その道のプロが実際に使った」「現場でこうだった」といった体験談が加わることで、よりE-E-A-Tに富んだ評価を得ることができます。
AIによる自動生成コンテンツでは、この「経験」や「実在性」の要素が欠落しやすいため、以下のような取り組みが重要になります。
E-E-A-Tはページ単位で評価されるだけでなく、サイト全体の信頼性にも関係するため、SEO施策と並行して、ブランド価値や運営体制の強化にも取り組むことが求められます。
AIの活用が進む中で、誰でも同じような情報を自動生成できる時代になりました。だからこそ、コピーペーストではない「独自性」が評価される傾向が一層強まっています。
Googleは2023年以降、「Helpful Content Update」などを通じて、機械的に生成された情報や他サイトと大差ないコンテンツを順位下落の対象としています。これに対して有効なのが、一次情報や現場のリアルな声です。
具体的には以下のような要素がSEOにおける独自性として機能します。
これらはAIでは模倣が難しく、Googleからも「オリジナリティ」として高く評価されます。企業サイトであれば、営業現場やカスタマーサポートで得られた知見、ユーザーの悩みに直接向き合った対応事例などを掘り起こすことで、十分に独自性の高いコンテンツを制作することが可能です。
特にローカルSEOやニッチ業界においては、こうした一次情報の差がそのまま検索順位の差につながります。
検索エンジンが進化するにつれ、コンテンツそのものの中身だけでなく、「使いやすさ」や「ストレスのなさ」といったユーザー体験(UX)の要素も評価対象に含まれるようになりました。
Googleはコアウェブバイタル(Core Web Vitals)という指標を通じて、以下のようなUX要素をスコア化しています。
この他にも、スマホ対応の有無、画像の読み込み速度、ナビゲーションのわかりやすさ、内部リンクの設計、スクロール量に対する情報密度など、あらゆるUX要素が間接的にSEO評価に影響を与えています。
UXを改善するための具体的な施策としては、
などが挙げられます。いずれも「ユーザーの行動」を意識して設計されており、滞在時間や直帰率、コンバージョン率の改善にもつながります。
AI時代のSEOでは、単に検索上位を狙うのではなく、その先にいるユーザーの利便性や満足度まで設計に組み込むことが重要です。SEOとUXは表裏一体の関係であり、AIがいくら高度に分析しても、ユーザーの不満には勝てません。

AIの進化により、SEOの土台そのものが大きく変わりつつあります。従来の「検索→クリック→サイト訪問→情報取得」という一連の流れが変化し、検索体験そのものがAIアシスタントや生成AIの回答によって完結する場面も増えています。こうした潮流の中で、企業やWeb担当者が今後のSEO戦略を立てるうえで、見逃せない3つの方向性があります。
これまでのSEOはGoogleなどの検索エンジンアルゴリズムに最適化するものでしたが、今後は「ChatGPT」や「Claude」「Gemini」など、生成AIの回答領域に自社情報を取り込ませるための最適化=LLMO(Local Language Model Optimization)が重要なテーマになります。
たとえば、ユーザーがAIに「札幌でおすすめのWeb制作会社は?」と尋ねたとき、その回答文の中に自社が含まれるかどうか。これは検索結果以上にコンバージョンに直結する場面です。
LLMOを強化するためには、
といった取り組みが必要です。
また、ChatGPTなど一部の生成AIでは「Custom GPT」などの個別学習機能も提供されており、今後は企業側が自社のLLMを持ち、そこにSEO的な文脈を組み込んでいくことも現実的になってきました。検索エンジンに最適化するだけでなく、「AIに選ばれるための情報設計」こそが次世代のSEO戦略と言えるでしょう。
Google検索での「ゼロクリック検索(Zero Click Search)」とは、ユーザーが検索結果をクリックせず、画面上の抜粋情報(リッチスニペット・ナレッジパネル・People Also Askなど)だけで目的を達成してしまう現象です。
これにより、Webサイトへの流入が減少するケースも増えており、特にFAQや定義、地図情報、レビュー情報などはゼロクリックの影響を大きく受けています。
この状況において重要なのは、「クリックされなくても、ブランドを印象付ける」情報設計です。具体的には以下のような施策が効果的です。
つまり、SEOの成果を「流入数」に限定するのではなく、あくまで認知・信頼・行動誘導という一連のカスタマージャーニー全体で捉えるべきです。
また、Webサイト以外のチャネルで顧客接点を持つマルチチャネル戦略を前提とした情報発信が、これからのSEO成功において不可欠となっていきます。
AIはもはやSEOだけでなく、あらゆるマーケティング領域に活用されています。特に、パーソナライズ、リード分析、コンテンツ生成、広告運用などとの連動が進んでおり、「SEOだけの施策」で成果を上げるのは難しくなってきました。
これからのSEOでは、次のような統合的なAIマーケティング戦略が求められます。
AIによって制作コストが下がる一方で、「どう組み合わせて効果を最大化するか」という設計力・戦略力がSEO担当者には求められています。
AIは単なる自動化ツールではなく、「施策を選ぶ力を持ったパートナー」として捉え、SEO・コンテンツマーケティング・SNS・広告・CRMなどすべてをシームレスに設計していくことで、より大きな成果を得ることができるでしょう。
生成AIの登場により、SEOの現場では記事作成や分析、リライトなど多くの業務が自動化・効率化されています。一方で、その恩恵に安易に頼りすぎると、検索エンジンからの評価を下げたり、ユーザーの信頼を損ねたりするリスクも高まります。SEOにAIを活用する際には、技術的なメリットだけでなく、倫理面やガイドライン遵守の視点も不可欠です。ここでは、AI活用SEOの代表的なリスクと配慮すべき点を整理します。
2023年にGoogleが発表した「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」の強化方針により、SEOでのAIコンテンツ活用には慎重な姿勢が求められるようになりました。Google自体は「自動生成コンテンツを一律に否定するわけではない」としつつも、「価値のない量産記事」や「低品質なキーワード詰め込みコンテンツ」は明確にスパムと見なすと明言しています。
実際に、AIが生成したコンテンツの中には、
といった特徴が見られることがあります。これらは一見するとSEOに最適化された記事に見えても、ユーザーにとっての有益性が薄く、E-E-A-Tの観点では評価が下がる要因となります。
そのため、AIによる下書きやアイデア出しを活用すること自体は問題ありませんが、最終的な公開コンテンツは必ず人間が編集・監修し、
を意識することが重要です。
特に医療・金融・法律・教育などのYMYL(Your Money or Your Life)領域では、AI生成コンテンツだけで構成されたページは評価が極端に下がる傾向があるため、専門家の監修・署名・著者情報の明示が不可欠です。
AIの出力には必ず「幻覚(hallucination)」と呼ばれる事実誤認のリスクがつきまといます。特にChatGPTのような大規模言語モデルは、あたかも本当の情報のように見える文章を自信満々に生成することがあり、実際には存在しないデータや出典を記載することもあります。
そのため、AIを使ってSEO記事やFAQ、製品ページを作成する場合は、以下のような二重チェック体制を整えることが推奨されます。
また、近年では「AIっぽい文章」に対する読者の警戒感も高まっており、読みやすさや人間らしさを感じさせる工夫(具体例・会話調・エモーショナルな語り口など)も重要です。
SEOにおけるAI活用はあくまで補助的な役割とし、「手軽に量産」ではなく、「信頼性と独自性の向上」に繋がる使い方を模索すべきでしょう。
AIがもたらす変化の中で、多くの企業が直面するのが「人間はどこまで関与すべきか?」という問いです。今後、コンテンツ制作・マーケティング業務における人とAIの適切な役割分担を再定義する必要があります。
具体的には、
といった住み分けが基本となります。AIはあくまで「実務効率化のための道具」であり、「ユーザーに価値を届ける設計者」としての責任は人間が担うべきです。
このような視点を持つことで、SEO施策そのものの質も向上し、長期的にGoogleや読者から信頼されるメディア運営が可能となるでしょう。
AIの進化により、SEO施策はこれまで以上に効率化・高度化が可能になりました。キーワード選定や競合分析、コンテンツ作成、UX最適化など、あらゆるプロセスでAIの恩恵を受けられる一方で、倫理的な配慮や品質管理の重要性も増しています。
これからのSEOで求められるのは、AIを「量産の道具」として使うのではなく、「ユーザーに本質的価値を届けるためのパートナー」として活用する視点です。人間の創造力とAIの技術力を融合させ、検索エンジンとユーザーの双方に評価されるコンテンツ戦略を構築していきましょう。
AIを活用したコンテンツ制作やSEO運用に取り組みたいが、自社だけでは難しいとお感じではありませんか?
ARDEMでは、SEO×AIの最前線を踏まえた実践的なサポートをご提供しています。まずは一度、ご相談ください。
▶ AI時代のSEO支援サービスについてお問い合わせ
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。