Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
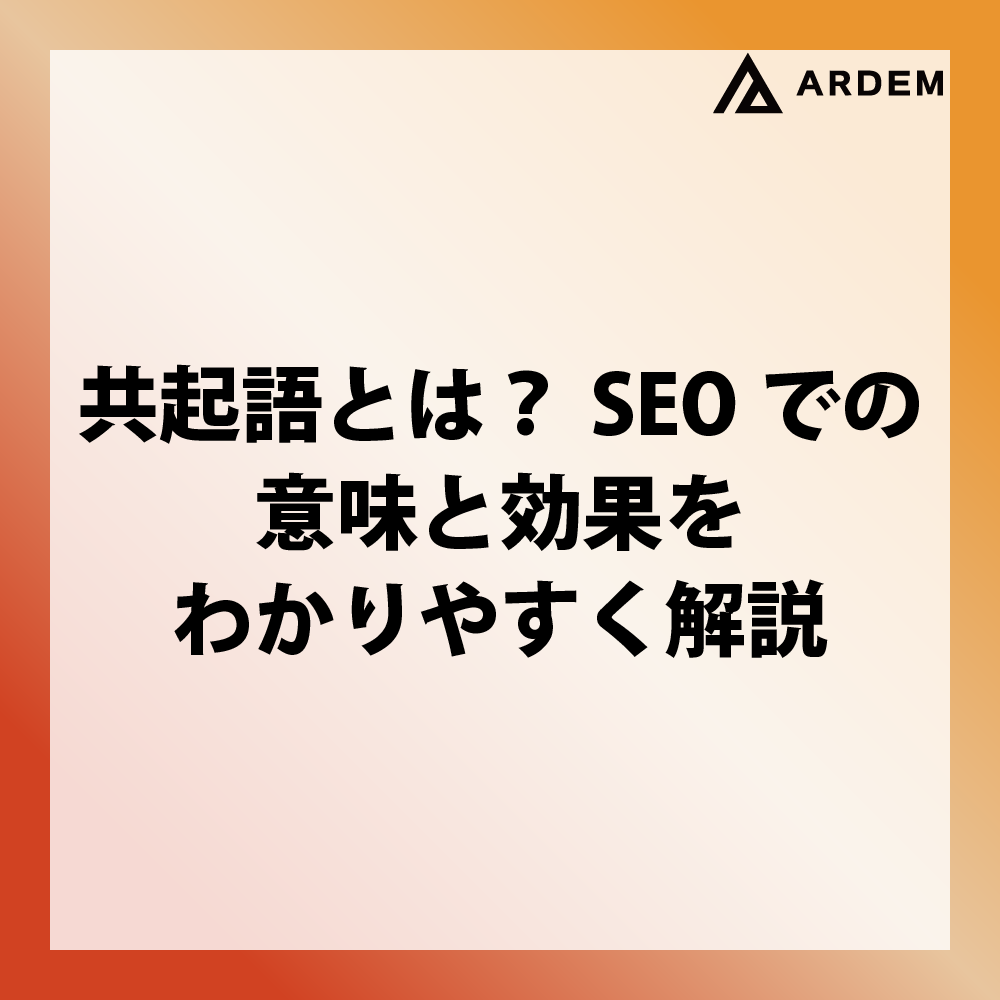
目次
SEO対策の現場では、「共起語」という言葉が頻繁に使われるようになっています。しかし、具体的にどのような意味があり、なぜ重要なのかを正しく理解している方は意外と少ないかもしれません。共起語は単なるキーワードの羅列ではなく、検索エンジンがコンテンツの「質」や「関連性」を評価する上で大きな役割を果たしています。
この記事では、共起語の基本的な概念から、SEOへの効果、効果的な使い方までを初心者にも分かりやすく解説します。これからWebサイトや記事を最適化したいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
SEOの成果を最大化するためには、キーワード選定だけでなく「共起語」の理解と活用が欠かせません。
「自社サイトの検索順位が伸びない」「記事を書いても流入が増えない」と感じている方は、共起語を活かしたコンテンツ設計を見直してみませんか?
ARDEMでは、共起語分析を含むSEOライティング支援も行っています。まずはお気軽にご相談ください。
▶ 無料相談はこちらから
共起語とは、あるキーワードと一緒に頻繁に使われる単語や表現のことを指します。たとえば「SEO」というキーワードに対して、「検索エンジン」「アルゴリズム」「Google」「順位」などが共起語として挙げられます。これは、検索結果に表示される多くのコンテンツ内で、それらの単語が同時に登場しているためです。
共起語は、検索エンジンが「そのページが本当にそのテーマについて詳しく書かれているか」を判断する際の参考指標のひとつです。コンテンツ内に自然な形で共起語が含まれていれば、検索エンジンはそのページを「専門性の高いページ」と認識しやすくなります。
共起語は、類義語や関連キーワードと混同されがちですが、それぞれ意味が異なります。類義語とは、意味が似ている別の言葉のことで、たとえば「Webサイト」と「ホームページ」などが該当します。一方、関連キーワードは、検索ユーザーが一緒に検索することが多い語句やフレーズです。
共起語はこれらと違い、「あるキーワードを含むページ内で、他にどんな語が一緒に使われているか」という“文脈上の共通性”に基づいています。つまり、検索エンジンが自然言語処理を通じてコンテンツの意味を理解しようとする際の「補助的な手がかり」だと考えるとよいでしょう。
共起語は、コンテンツの「専門性」や「網羅性」を高めるために重要な役割を果たします。検索ユーザーは、あるキーワードに対して単一の答えを求めているわけではなく、そのキーワードを取り巻く情報を包括的に理解したいと考えています。
たとえば「SEO対策」というキーワードをテーマに記事を書く場合、「内部対策」「外部対策」「Googleアルゴリズム」「検索順位」「キーワード選定」などの共起語を適切に含めることで、読者にとっても検索エンジンにとっても「内容の濃い、信頼性の高いページ」として認識されやすくなります。
これにより、ユーザーの滞在時間やページの閲覧数が増加し、結果的にSEO評価の向上につながります。
Googleの検索アルゴリズムは、単純なキーワード一致だけでなく、ページ全体の「文脈」や「意味の深さ」を解析しようとしています。その中で、共起語は「このページが本当にそのキーワードにふさわしい内容を持っているか」を判断する重要なシグナルのひとつとされています。
とくに、Googleが導入しているBERTやRankBrainといった自然言語処理技術は、文脈や関連語のつながりを理解しようとする仕組みを持っています。これらのAIがページを評価する際、共起語の自然な登場は「テーマの深堀り」や「話題の一貫性」を示す要素となり、結果として検索順位の向上に寄与する可能性が高まります。
共起語を戦略的に活用することで、SEOの効果をより高めることができるのです。
共起語を意識してコンテンツを設計することで、記事全体の質と検索エンジンからの評価が飛躍的に向上します。単にキーワードを詰め込むSEOはすでに時代遅れとなり、現在は「読者の知りたいことを深く、幅広くカバーするコンテンツ」が求められています。
たとえば「ダイエット 食事」というキーワードに対し、「低糖質」「栄養バランス」「食事制限」「リバウンド」などの共起語を含めることで、検索ユーザーの多様な関心をカバーできます。これにより、直帰率の低下や滞在時間の増加、さらにはシェアや被リンクの獲得といった間接的なSEO効果も期待できます。
また、共起語の活用は、専門性の高い記事やテーマにおいて、内容の正確性や説得力を高める点でも有効です。
実際に共起語を活用して見出しや本文を改善する方法を見てみましょう。
改善前:
改善後(共起語を意識):
このように、共起語を見出しや本文に自然に組み込むことで、記事の信頼性と網羅性が向上し、検索エンジンにも高く評価されやすくなります。
共起語は有効なSEO施策ですが、「入れすぎ」は逆効果になることがあります。不自然に同じ語を繰り返すと、読みづらい文章になり、ユーザー体験を損なってしまいます。また、Googleから「不自然なキーワードの詰め込み」と判断されれば、逆に評価を下げるリスクもあります。
自然な使い方のポイントは以下の通りです。
共起語はあくまで「読者の疑問に幅広く答えるためのツール」です。無理に使うのではなく、文章の質を高めるために活用するという意識が重要です。
共起語を効果的に活用するためには、まず「どの言葉が共起語として関連性が高いのか」を把握する必要があります。ここでは、無料で使えるツールを中心に、実際の調査手順と確認すべきポイントを解説します。
SEO初心者でも扱いやすく、無料で利用できる代表的な共起語調査ツールを紹介します。
Googleのサジェストワードや共起語、周辺語を一括で取得できる日本語対応のツール。入力したキーワードに対して、ユーザーが実際に検索している関連ワードを一覧で表示してくれます。共起語というよりも「検索ニーズの把握」に強く、コンテンツの方向性決めに役立ちます。
文章単位での共起語を抽出できるシンプルな無料ツール。調査したいキーワードを入力すると、それとよく一緒に使われる語句が表示されます。日本語処理がしっかりしているため、SEOライティング向けの共起語調査に最適です。
Googleでキーワード検索を行い、上位表示されているページの「タイトル」「メタ情報」「hタグ」「本文」などを確認することで、競合が使用している共起語を読み取る手法。SEO META in 1 CLICKのようなブラウザ拡張を使えば、ページの構造を素早く把握できます。
検索窓にキーワードを入力した際に表示される候補(Googleサジェスト)や、検索結果ページ下部の「他のキーワード」も共起語としてのヒントになります。ユーザーの実際の検索意図が反映されており、自然な文脈の共起語を拾うのに有効です。
共起語調査は、単にツールを使うだけではなく、調査結果をどのように活用するかが重要です。以下に、実践的な調査ステップとその際の確認ポイントを紹介します。
まずは、記事の主軸となるキーワード(例:ダイエット、SEO対策、求人サイトなど)を明確に設定します。
決めたキーワードを、共起語検索ツールやラッコキーワードなどに入力し、頻出する語句をピックアップします。ツールによっては、品詞での絞り込みや、出現頻度の高い語順に並べ替える機能もあるため、活用しましょう。
取得した共起語を「特徴を示す言葉(例:高性能、低価格)」「用途・シーン(例:ビジネス、初心者向け)」「技術・仕組み(例:アルゴリズム、内部対策)」などの観点で分類します。これにより、コンテンツの構成や見出しの設計が明確になります。
Google検索で自分の狙うキーワードを調べ、上位表示されている記事にどのような共起語が含まれているかを確認します。その上で、足りない情報や差別化できるポイントを見つけ、共起語の選定や内容に反映します。
調査で得た共起語を、見出しや本文に無理なく織り込むよう意識しながらライティングします。「網羅性」と「自然な文脈」の両立がポイントです。
Googleをはじめとする検索エンジンは、単純にキーワードの一致だけでなく、「そのキーワードが使われる文脈」や「検索者の意図」を理解する方向へと進化しています。つまり、検索順位を上げるには、検索キーワードそのものだけでなく、ユーザーが本当に求めている情報——すなわち検索意図を正確に捉える必要があります。
このとき、共起語は検索意図を推測するための強力な手がかりになります。なぜなら、共起語とは「あるキーワードと一緒によく使われる語」であり、ユーザーがそのテーマをどのような観点で考えているかを反映しているからです。
たとえば、「ダイエット」というキーワードの共起語に「食事制限」「筋トレ」「リバウンド」「糖質オフ」などがあったとします。これは、ユーザーが「どうやって痩せるか」「どんな方法があるのか」「失敗しないための注意点」などの具体的な疑問を持っていることを示しています。これをヒントにすれば、単に「ダイエットとは」と説明する記事よりも、検索意図にマッチした深い情報提供が可能になります。
共起語をコンテンツ内に自然に盛り込むことは、読者の満足度向上にもつながります。共起語には以下のような役割があるためです。
共起語を含めることで、ユーザーが想定している関連情報を漏れなくカバーできます。これにより「知りたいことが全部書いてあった」と感じさせることができ、滞在時間や再訪率の向上にも貢献します。
適切な共起語を活用することで、「このサイトはちゃんと理解して書かれている」という印象を与えられます。専門用語や業界特有のキーワードが適切に登場することで、権威性や信頼感が増します。
共起語には「ユーザーの本音」や「潜在ニーズ」が隠れていることが多く、それを拾い上げることで、ただの説明ではなく、共感や納得を呼ぶコンテンツに近づきます。
たとえば、転職に関する記事で「履歴書」「志望動機」「面接」「未経験OK」といった共起語が含まれていれば、読者が「実際に応募する場面」を想定して読めるようになります。ただの情報提供から一歩進み、ユーザーの行動を後押しするコンテンツに昇華できるのです。
SEOの基礎から実践までをしっかり学びたい方にはこちらの記事がおすすめ。Googleの評価基準や内部・外部対策など、2025年時点で押さえておくべき最新情報を初心者にも分かりやすく解説しています。
SEOの成果を出すためには「コンテンツの質」がカギとなります。この記事では、効果的なキーワード選定や構成案の作り方、コンテンツの改善・運用の手法まで、成果につなげる手順を丁寧に紹介しています。
共起語は、検索キーワードとともによく使われる関連語であり、コンテンツSEOにおいて非常に重要な要素です。検索エンジンは、ユーザーの検索意図をより正確に理解するため、単一のキーワードだけでなく、その周辺にある共起語の出現にも注目しています。
共起語を意識してコンテンツを制作することで、検索順位の向上だけでなく、読者にとっての情報の網羅性や満足度も高められます。また、検索意図に沿った適切な構成・内容に仕上げることができ、結果的にCV(コンバージョン)や滞在時間などの指標にも良い影響を与えるでしょう。
SEOで成果を出すには、「共起語を自然に取り入れながら、読者の課題を的確に解決するコンテンツ」をつくることが、今後ますます求められていきます。技術としての知識だけでなく、ユーザー視点の理解も欠かせない時代です。コンテンツの質をさらに高めたい方は、共起語を積極的に活用してみてください。
「どの共起語を選べばいいのか分からない」「効果的な記事構成が思い浮かばない」――そんなお悩みはありませんか?
ARDEMでは、SEOに強いライティングとキーワード設計をトータルでサポートしています。
専門スタッフによるアドバイスをご希望の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
▶ SEOのご相談はこちらから
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。