Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
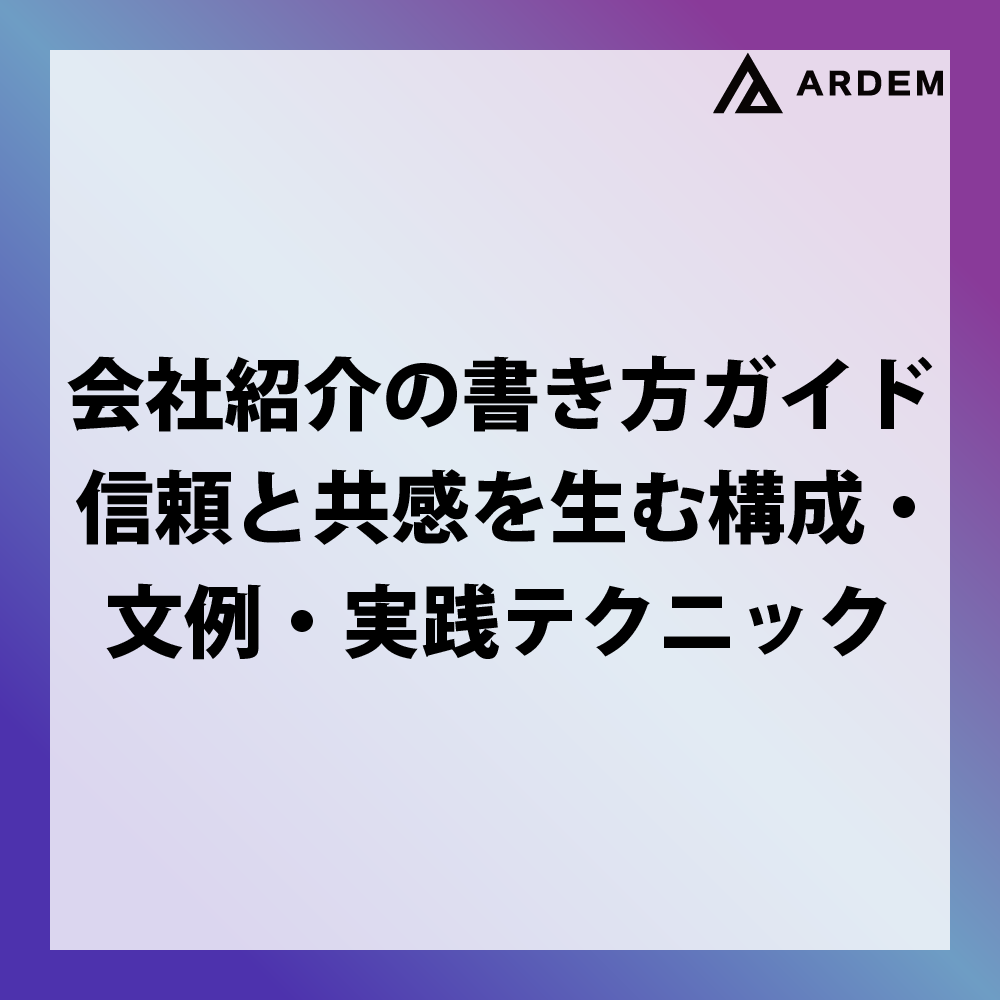
目次
「御社のことを簡単に教えてください。」
営業先や採用活動、あるいはWebサイトの制作時に、こう聞かれて戸惑った経験はないでしょうか。自社のことを一番よく知っているはずなのに、いざ言葉にしようとすると何から伝えるべきか迷ってしまう――それが「会社紹介」の難しさです。
会社紹介は、単なる会社の説明文ではありません。読んだ相手に「どんな会社か」が伝わり、信頼や共感を持ってもらうための大切な第一印象です。特にWebサイトやパンフレットでは、言葉だけが会社の顔になることも少なくありません。
この記事では、会社紹介の役割や書き方、伝わる構成、媒体別の表現方法までを、実例やテンプレートも交えて解説します。「ありきたりな紹介文から抜け出したい」「他社と差がつく表現が知りたい」とお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
「何をしている会社か」だけでなく、「なぜ選ばれる会社なのか」を伝える紹介文を作りませんか?ARDEMでは、企業の強みや想いを丁寧にヒアリングし、言葉で価値を伝えるWebサイト制作を行っています。
会社紹介文の見直しや掲載コンテンツのご相談もお気軽にどうぞ。
▶ ホームページ制作の無料相談はこちら
「会社紹介」と「会社概要」は、混同されやすい表現です。どちらも企業情報を伝える役割を担いますが、内容や目的には明確な違いがあります。
会社概要は、会社名・所在地・設立年・資本金・代表者名・事業内容など、いわば“事実情報の羅列”です。読み手に会社の基本情報を端的に伝えるもので、履歴書における氏名や住所のような役割に近いと言えます。
一方の会社紹介は、会社の価値観や想い、事業の強みなど、より“ストーリー性”や“伝える意図”を持った文章です。社内外のステークホルダーに向けて、「私たちはどんな会社なのか」「どんな価値を届けているのか」を言葉で表現するものです。
たとえば、以下のように役割の違いが見えてきます。
| 区分 | 内容 | 目的 |
| 会社概要 | 基本情報・データ中心 | 正確に伝える |
| 会社紹介 | 思いや背景・強み | 共感・信頼を得る |
つまり、会社概要が「会社の名刺」であるとすれば、会社紹介は「会社のプレゼンテーション」。無機質な情報だけでなく、読み手との距離を縮める“語り”の要素を持つのが特徴です。
会社紹介は、さまざまなビジネスシーンで活用される文章です。目的によって伝える内容は変わりますが、共通して言えるのは「信頼を獲得する」ための入り口となる点です。
たとえば営業活動では、提案書や資料に会社紹介を添えることで、初対面の相手に安心感を与えることができます。採用の現場では、応募者に「この会社で働いてみたい」と感じてもらうための重要な情報源となります。
また、Webサイトにおいては会社紹介ページが「企業の顔」となることも多く、訪問者が最初にアクセスするコンテンツの一つです。ここで魅力的に伝えられるかどうかが、問い合わせや採用応募といった行動につながるかどうかを左右します。
会社紹介には、以下のような役割があるといえます。
つまり会社紹介とは、「企業そのものの印象をつくる文章」。表面的な説明ではなく、企業としての“姿勢”や“誠実さ”を伝えることが、読み手の心に響く紹介文につながります。
会社紹介は、特定のタイミングだけで必要とされるものではありません。むしろ、あらゆる対外的なコミュニケーションの場面で「会社を語る言葉」として機能し、信頼の起点となります。ここでは、特に活用頻度が高い3つの代表的なシーンをご紹介します。
企業のWebサイトにおける「会社紹介」は、訪問者が最初に目にするコンテンツの一つです。特に初めてアクセスする人にとっては、企業理解の出発点となるため、どれだけ明快に、かつ魅力的に語れているかが重要です。
また、採用ページでは「どんな会社か」「どんな思いで人を募集しているのか」を知ってもらうために、会社紹介文が大きな役割を果たします。ただ情報を羅列するのではなく、「働く意味」や「文化」を言葉で表現することで、求職者の心に届く内容に仕上がります。
例えば、次のようなコンテンツでの活用が考えられます。
Webは誰もが自由に見られる開かれた場だからこそ、そこに載せる会社紹介は“会社の顔”そのもの。ターゲットに応じた表現の工夫が求められます。
営業先への提案書や会社案内パンフレットにおいても、会社紹介文は欠かせません。特に初めての商談では、「この会社に任せて大丈夫か」「どんな実績があるのか」といった情報を短時間で伝える必要があります。
このとき、会社紹介が単なる年表や沿革になっていると、相手にとっては「印象に残らない情報」に終わってしまいます。むしろ、「なぜこの事業をやっているのか」「どんな課題を解決できるのか」といった“意志”の部分まで伝えることで、共感や安心感につながります。
営業資料では特に、以下のような使い方が効果的です。
限られた紙面や時間の中で、自社の魅力を伝える手段として、質の高い会社紹介文は強い武器になります。
会社紹介は、情報提供のためだけにあるのではありません。もっとも本質的な役割は、「信頼の起点をつくること」です。たとえば、メディア掲載や業界団体への加入時、あるいは取引先企業の審査過程など、会社の背景を問われる場面は意外と多く存在します。
その際に、一貫性のある紹介文が用意されていれば、情報の正確性と共に企業としての姿勢も伝わりやすくなります。特に最近は、企業の社会的責任や持続可能性への取り組みといった“中長期的な信頼”が重視されるようになっており、そうした視点も含んだ紹介文が求められる傾向にあります。
また、M&Aや資金調達のように、企業の“中身”を問われる局面においても、会社紹介は第一印象を左右する情報になります。端的に言えば、会社紹介とは「ビジネス上の信頼構築のスタートライン」とも言えるのです。

会社紹介文は、ただ事実を並べるだけでは読まれません。読み手の興味を引き、企業への理解と信頼を深めてもらうためには、どのような情報をどう組み立てるかが重要です。
ここでは、伝わる会社紹介文に欠かせない4つの要素を紹介します。
まず基本となるのが、会社名や事業の概要、そしてその会社ならではの強みです。読み手が「どんな会社なのか」「何をやっているのか」をすぐに理解できるよう、簡潔かつ具体的に表現する必要があります。
たとえば、次のような情報が該当します。
ここでは「差別化」が重要です。ありふれた説明ではなく、「なぜこの会社に頼みたいと思えるか」という視点で伝えましょう。
読み手に会社の“人格”を感じてもらうためには、理念や創業の背景をしっかり盛り込むことが大切です。企業として何を大事にしているのか、どんな未来を目指しているのかを言葉にすることで、信頼や共感につながります。
このパートで含めたい内容は以下の通りです。
感情を込めすぎず、誠実に語ることで、企業の姿勢や人となりが自然に伝わります。
理念や想いといった“抽象的な話”だけでは説得力に欠ける場合もあります。そこで重要になるのが、実績や取引先、数値データなど“具体的な裏付け”です。これらの情報をバランスよく交えることで、紹介文の信頼性がぐっと高まります。
たとえば、次のような形で記載できます。
数字を使う際は、ただ羅列するのではなく「だからどうすごいのか」を一言添えると読みやすくなります。
最後に、未来に向けた意気込みや読者へのメッセージを添えることで、紹介文を“開かれたもの”に仕上げることができます。会社紹介は、過去や現在を伝えるだけでなく、「これからどこへ向かうのか」を描くことも大切です。
このパートでは、次のような内容を意識しましょう。
たとえば、「これからも地域とともに成長し続けます」「新しい価値を生み出す挑戦を続けていきます」など、前向きな表現で締めくくると印象に残りやすくなります。
せっかく時間をかけて作った会社紹介文も、最後まで読まれなければ意味がありません。読み手の関心を引き、記憶に残る紹介文にするには、「誰に向けて、どんな形で伝えるか」の工夫が欠かせません。ここでは、読まれる会社紹介にするための3つのポイントを解説します。
まず意識すべきは、「誰に向けた紹介文なのか」を明確にすることです。たとえば、BtoB商談用の会社紹介と、一般消費者に向けた企業案内では、使う言葉も文章のトーンも異なるべきです。
ビジネスパートナーや採用希望者向けなら、以下のようなポイントを意識すると効果的です。
一方、生活者や一般ユーザー向けであれば、
といった工夫が求められます。読者の属性・関心・読み方を考えながら、文章全体の雰囲気や言葉選びを調整していきましょう。
企業の理念や創業背景、挑戦のエピソードなどを、ストーリーとして語ると読者の印象に残りやすくなります。たとえば単に「地元密着で営業しています」と書くより、「創業当時は地元の商店街の一角で小さな八百屋として始まりました」のように、情景を描くことで親近感が生まれます。
ストーリー化する際のコツは以下の通りです。
ただし、長すぎるストーリーは逆効果になることもあるため、「1~2エピソード」に絞り、要点を押さえた構成を意識しましょう。
会社紹介は伝えたい情報が多くなりがちですが、すべてを一気に盛り込んでしまうと冗長で読みにくくなります。そこで重要になるのが「構成のメリハリ」です。
具体的には以下のような工夫を取り入れましょう。
また、文章が単調にならないように「事実→背景→意図」のような流れを意識すると、情報が整理されて読みやすくなります。
会社紹介は、掲載される媒体によって伝えるべき内容やトーンが異なります。読み手の状況や目的が異なるため、それに合わせて文章の構成や言葉遣いも調整する必要があります。ここでは代表的な3つの媒体(Webサイト、パンフレット、提案資料)における会社紹介の特徴と書き分けのポイントを紹介します。
Webサイトは企業の顔とも言える存在で、会社紹介ページは訪問者が最初に企業を知る入口になります。多くの場合、検索やリンク経由で訪れたユーザーが短時間で企業の情報を把握しようとするため、「視認性の高さ」と「端的な表現」が求められます。
コーポレートサイト向けのポイント
採用ページ向けのポイント
Webサイトでは「パッと読める・でも深掘りもできる」構成が理想です。ビジュアルやUIの工夫も併せて検討しましょう。
パンフレットは展示会や商談時など、対面で手渡されるケースが多く、紙媒体ならではのレイアウト・写真・図解が大きな役割を果たします。Webサイトよりもストーリー性や感情に訴える構成が向いています。
パンフレット向けのポイント
特に営業用パンフレットでは「読み終えたときに、どんな印象を持ってもらいたいか」を逆算して構成することが大切です。
提案書や営業資料における会社紹介は、「信頼感を獲得すること」が最優先の目的です。読み手はサービスや商品の導入を検討している立場なので、客観性や数字の裏付けが特に重要視されます。
営業資料向けのポイント
また、相手企業や業界に応じて、会社紹介のトーンや重点項目を柔軟に差し替えるカスタマイズ性も求められます。資料作成の段階でテンプレート化しておくと、営業現場での活用度が高まります。

会社紹介文は、ただ事実を並べれば良いというものではありません。伝える相手がいて初めて意味を持ちます。しかし、多くの企業が無意識のうちにやってしまっている“残念な紹介文”には共通点があります。ここではよくある失敗と、それをどう改善すればよいかを具体的に見ていきましょう。
「お客様第一のサービスを提供します」「社会に貢献する企業を目指しています」──こうした表現は一見立派に聞こえますが、何をしている会社なのか、何が強みなのかは伝わりません。抽象的な言葉は受け手の想像力に委ねてしまうため、印象にも残りづらくなります。
改善ポイント
抽象表現を使う場合は、必ず裏付けとなる事実やエピソードを添えて説得力を持たせましょう。
「創業◯年」「従業員◯人」「○○市に本社を構え~」といった定型情報だけを並べて終わる会社紹介は、読まれることなくスルーされる典型例です。読み手はその情報の「背景」や「意味づけ」に関心を持っています。
改善ポイント
事実は素材でしかありません。それを「どのように語るか」が、会社の魅力を伝える鍵になります。
「我が社は~」「当社の理念は~」「私たちの強みは~」といった“自分語り”ばかりの文章は、読者の関心や共感を引きづらくなります。情報提供の主導権を一方的に握る構成は、相手目線の欠如につながります。
改善ポイント
会社紹介文は、あくまで「読み手に向けたコミュニケーションツール」です。共感や信頼を得たいのであれば、自社の都合ではなく、相手の視点に立って設計することが不可欠です。
会社紹介文は企業の業種や目的、掲載媒体によって最適な表現が異なります。
ここでは、実際に使いやすい3つのパターン(BtoB企業/地方・家業系企業/採用向け)に分けて、基本的なテンプレートと例文を紹介します。
自社紹介文をゼロから考えるのが難しい方は、まずはこれらをベースにカスタマイズしてみてください。
BtoB領域では「実績の裏付け」や「問題解決力」が重要視されるため、客観的な表現や数値・成果ベースの紹介が求められます。
テンプレート構成:
1. 創業の背景と事業の概要
2. 解決できる課題・得意分野
3. 実績・取引先・強みの数値的裏付け
4. 今後のビジョンや提供価値
例文:
弊社は2005年の創業以来、製造業向けの業務システム開発を専門に手がけてまいりました。特に在庫管理や生産管理の自動化においては多数の導入実績があり、現在までに全国200社以上の導入を支援しています。
業界固有の業務フローを理解したエンジニアチームが、現場課題に即したシステムをオーダーメイドで構築。導入後3ヶ月で業務工数を30%削減した実績もあります。
今後も「現場から信頼されるITパートナー」として、中堅・中小企業の生産性向上に貢献してまいります。
「土地に根ざした信頼感」や「人柄」「物語性」が共感につながりやすいため、理念や創業ストーリーを軸に語るスタイルが向いています。
テンプレート構成:
1. 創業の歴史と地域とのつながり
2. 代々受け継いできた想いやこだわり
3. お客様との関係性や大切にしていること
4. 今後の展望と地域貢献への姿勢
例文:
私たちは、昭和48年に○○町で創業した木工所から始まりました。祖父が立ち上げた小さな工房は、地域の家具修理やオーダー品づくりを通じて、町の暮らしに寄り添ってきました。
現在は3代目として、地域産材を使ったオリジナル家具の製造と販売を行っており、デザイン性と職人の技術を融合させた製品づくりにこだわっています。
「長く使ってもらえるものを届けたい」という想いは今も変わらず、これからも地域に根ざした“ものづくりの拠点”として歩み続けます。
求職者に「ここで働くイメージ」が持てるよう、企業理念や働く人の価値観、環境への配慮を織り交ぜながら語るのがポイントです。
テンプレート構成:
1. 会社の理念やビジョン
2. どんな人が働いているか、職場の雰囲気
3. 仕事のやりがい・社会への影響
4. 一緒に目指す未来と求める人物像
例文:
「人と技術の力で、暮らしに安心を届ける」──それが私たちの企業理念です。防災設備の設計・施工・保守を通じて、社会インフラを守る仕事に誇りを持っています。
社員の年齢層は20〜40代が中心。新卒・未経験で入社したメンバーも多く、学び合いながら成長できる環境です。お客様の「ありがとう」が仕事の原動力であり、街の安全に貢献しているという実感が得られます。
これからの当社は、より多様な働き方や若手の活躍の場を広げ、柔軟で挑戦的な組織へと進化していきます。私たちと一緒に、次の安心をつくりませんか?
会社紹介文は、一度作ったらそれで終わりではありません。企業活動や社会の変化に合わせて定期的に見直し、常に「いまの自社」を正しく伝えられているかを確認することが大切です。
ビジネス環境は常に変化しています。新しいサービスの開始、社内体制の変化、SDGsやDXへの対応など、企業の姿は年々変わっていくものです。にもかかわらず、何年も前に作った紹介文を使い続けていませんか?
たとえば、かつては「地域密着」が売りだった企業が、今では全国展開していたり、「職人の技」が主力だった事業が、今ではテクノロジーと融合したサービスになっていたりすることもあるでしょう。古い情報や価値観のまま放置された紹介文は、企業の進化を正しく伝えられず、むしろ信頼性を損なう原因にもなります。
読者が求める視点も変化します。BtoBなら業界トレンドや社会課題への対応、採用向けなら働き方や価値観の共有など、読み手がどこに注目しているかを敏感に捉えて、文面に反映させる必要があります。
会社紹介文の見直しは、自社のブランディング戦略にも直結します。定期的なリライトによって、言語化の精度が高まり、社内外に向けたメッセージの一貫性も保ちやすくなります。
とくに、以下のようなタイミングでは紹介文のアップデートを検討しましょう。
紹介文を見直す過程で、自社の強みや価値をあらためて言語化できるという副次的効果もあります。これは、社内での方向性の共有や、営業・採用活動における発信の軸を整えるうえでも有効です。
「なんとなく古いまま」「手をつけづらい」――そんな状態で放置されている紹介文こそ、実は見直しのチャンスです。文章は企業の“顔”のひとつ。最新の自社像を、言葉でもしっかりと伝えていきましょう。
会社紹介文は、単なる「企業情報の羅列」ではなく、読み手に信頼や共感を与え、自社の価値を伝えるための重要なコンテンツです。まずは自社の立ち位置や伝えたい相手を明確にし、その目的に合わせて構成や表現を調整することが大切です。
とくに中小企業にとっては、ボリュームや美しさよりも、「等身大の言葉で何をどう伝えるか」が肝心。会社の歴史、想い、強みを丁寧に言語化することで、顧客や求職者との距離をぐっと縮めることができます。
一度作った紹介文も、定期的に見直すことでブランド力や発信力を高めることが可能です。時代や読者に合った“伝わる会社紹介”を、戦略的に育てていきましょう。
紹介文は、企業ブランディングの第一歩。ARDEMでは、文章の設計からWeb全体の構成までトータルにサポートし、読み手の心に届くホームページづくりをお手伝いしています。
まずは、今の会社紹介文を一緒に見直してみませんか?
▶ お問い合わせはこちらから
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。