Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
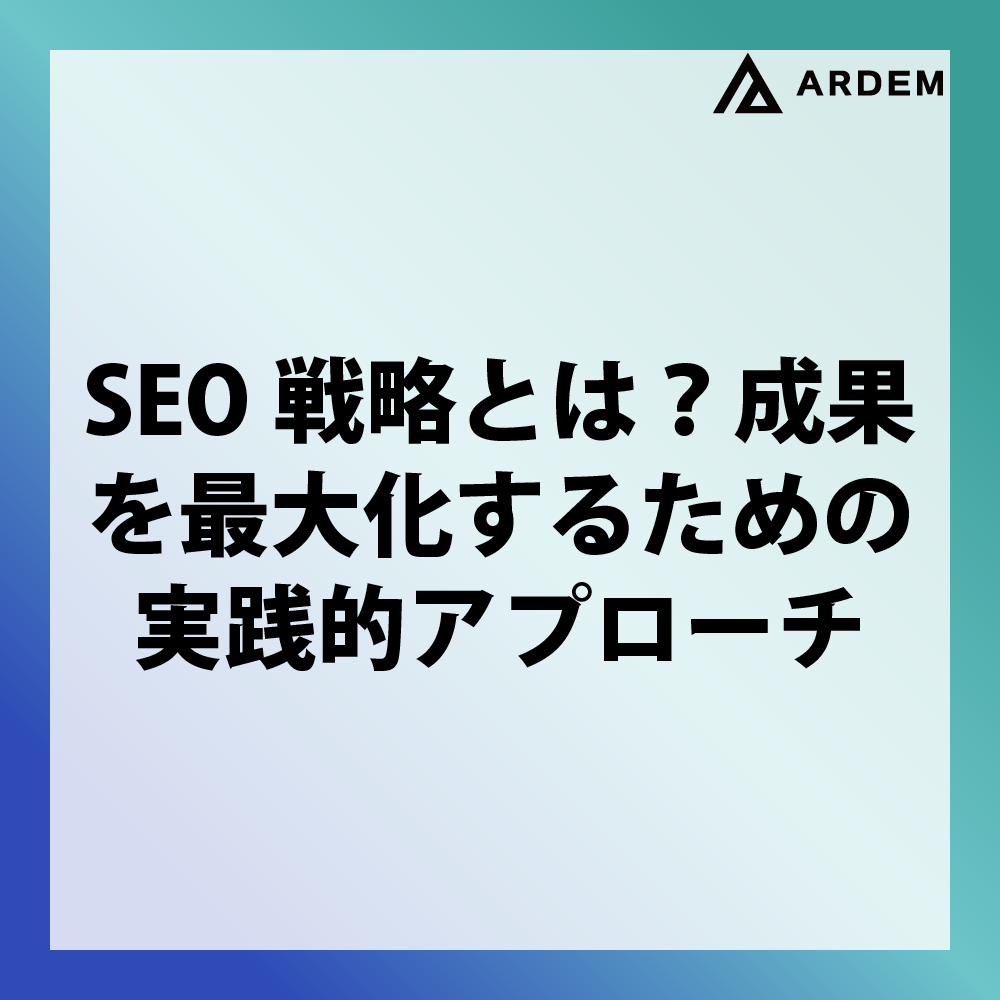
目次
SEO対策に取り組んでいるにもかかわらず、検索順位やアクセス数が伸び悩んでいる。そんな悩みを抱えていませんか?
原因は、戦略なき施策の繰り返しにあるかもしれません。
SEO(検索エンジン最適化)は、単にキーワードを盛り込んだコンテンツを作成するだけでは成果につながらない時代になっています。検索エンジンの進化とユーザー行動の多様化により、「どんな情報を、誰に、どのように届けるか」を明確に定めた上で、戦略的に取り組むことが欠かせません。
本記事では、SEO戦略の基本的な考え方から、実行のステップ、成果を出すための実践ポイントまでを体系的に解説します。これからSEOを強化したい企業担当者やWebマーケティングの見直しを検討している方にとって、具体的な指針となる内容です。
「戦術」ではなく「戦略」によって、検索結果の上位表示を超えた本当の成果を目指していきましょう。
ホームページを作ったけれど思うように集客できない、検索結果に出てこない…。そんなお悩みはありませんか?
ARDEMでは、SEOやWebマーケティングの視点から現状を分析し、改善の方向性をご提案します。まずは無料相談からお気軽にご相談ください。
▶ 無料相談はこちら
SEO戦略とは、検索エンジンでの上位表示を通じて、最終的なビジネス成果(売上、問い合わせ、資料請求など)を得るための長期的かつ体系的な設計図のことです。ただ単にキーワードを入れて記事を書く、リンクを増やすといった「単発的な施策」ではなく、「誰に・どんな情報を・どのような導線で届けるか」といった全体構造を考えることが求められます。
SEOの現場では、「戦略」と「施策」が混同されやすいのが実情です。たとえば、「キーワードをh1タグに入れる」「メタディスクリプションを設定する」といったテクニカルな対応は、いわば施策であり、戦略とは別物です。
戦略は、それらの施策をどの順番で・どの目的で・どのターゲットに向けて実行するかという上位の概念です。たとえば、以下のような視点が戦略には含まれます。
つまり、SEO戦略とは「施策を正しく選定し、優先順位をつけ、ゴールまでの道筋を構築する工程」であり、戦略なきSEOは、地図を持たずに登山に挑むようなものだと言えます。
多くの担当者が見落としがちなのが、SEOの本来の目的です。確かに「検索順位の上昇」は重要ですが、それ自体は手段であり、目的ではありません。検索1位を取っても、そこからの流入が自社のサービスや商品の成約に結びつかなければ、意味は半減します。
真の目的は「ビジネス成果」です。問い合わせ件数の増加、ECでの売上拡大、セミナー集客、ブランド認知向上など、企業の目的に直結する指標に対して、SEOがどう貢献するのかを明確にする必要があります。
このように、SEO戦略では「誰のために」「どんな価値を」「どのキーワードで」届けるのかを設計し、それを実現するために施策を展開するという全体的な視座が欠かせません。次章では、その戦略をどのように立案していくのかを具体的に解説していきます。
SEOは単なるテクニックの積み重ねではなく、ユーザーと検索エンジンの双方に価値を届けるための「戦略的思考」が求められます。とくに近年のGoogleアルゴリズムの高度化や、ユーザーの情報探索行動の複雑化に伴い、戦略の有無が成果を大きく左右する時代に入っています。
戦略がないSEOは、言わば「ターゲットも目的も定まらないまま広告を出す」ようなものです。たとえば、キーワードをリストアップしてとりあえず記事を量産しても、それがユーザーのニーズを捉えていなければ、検索流入もコンバージョンも見込めません。さらに、競合が増えるなかでただの情報提供では埋もれてしまう可能性も高くなっています。
また、短期的な施策の効果に一喜一憂してしまい、長期的な視点での改善が進まなくなるリスクもあります。目先の順位変動にとらわれていては、安定した成果や成長は得られません。戦略を明確に持つことで、優先順位を定めた施策の実行や、改善のための判断基準を持てるようになります。
Googleは常にアルゴリズムをアップデートし、「よりユーザーにとって有益な情報」を検索結果上位に表示しようとしています。かつてのように単純な被リンク数やキーワード出現頻度だけでは評価されず、コンテンツの質、専門性、信頼性、ユーザー満足度といった多面的な評価軸が重視されるようになりました。
一方で、ユーザーの行動も変化しています。単語で検索するだけでなく、疑問文・会話調・複合語など、多様な検索クエリを使いこなすようになり、また検索結果ページで比較・検討する時間も長くなっています。このような背景のなかでは、「どんなユーザーが」「どんな悩みを」「どんなキーワードで」検索するのかを読み解いたうえで、最適な情報設計を行う必要があります。
SEO戦略は、こうしたアルゴリズムとユーザー行動の変化を前提に、常にアップデートされるべき指針でもあります。目標達成のために変化に柔軟に対応し、計画的に改善を重ねていくためには、戦略的なフレームワークが欠かせないのです。次章では、具体的にどのような流れで戦略を立てていけば良いのかを解説していきます。
成果を出すSEO戦略を設計するには、単発の施策に頼るのではなく、全体を見通した体系的な構築が必要です。ここでは、戦略を支える6つの基本構成要素について解説します。
まず初めに行うべきは、どのようなユーザーに情報を届けたいのかを明確にすることです。年齢や性別、職業、悩みや価値観までを具体的に落とし込んだ「ペルソナ設計」は、SEOにおいても重要な起点です。
なぜなら、検索キーワードやコンテンツの切り口は、ユーザーのニーズや行動に直結しているからです。
たとえば、同じ「ダイエット サプリ」というキーワードでも、20代女性が求める情報と40代男性が探す情報はまったく異なります。ペルソナを設定することで、コンテンツの内容やトーン、導線設計まで一貫性を持たせることができ、検索意図にも的確に応えやすくなります。
Googleが最も重視しているのは、ユーザーの検索意図(インテント)です。検索窓に入力されるキーワードの裏には、「知りたい」「比較したい」「買いたい」などの明確なニーズが存在します。
たとえば「ホームページ 作り方」というキーワードは「情報収集(Know)」に該当し、初心者向けのノウハウ記事が適しています。一方、「ホームページ 制作 札幌」は「購入検討(Do)」に近く、会社案内や実績紹介ページの方がニーズに合致します。
検索意図を見誤ると、検索結果に表示されてもクリックされなかったり、すぐに離脱されてしまうリスクがあります。検索クエリの分類(Know / Do / Go / Buy)やサジェスト、関連キーワードなどを通して、ユーザーが「本当に欲している情報」を読み解くことがSEO戦略の肝です。
検索意図の理解に基づき、適切なキーワードを選定します。ここで重要なのは、「検索ボリューム」や「競合性」だけにとらわれず、ビジネスの目的やユーザーとの接点を意識することです。
そして選定したキーワードは、「カテゴリ別」「検索意図別」「ファネル段階別」に分類(グルーピング)することで、情報構造が明確になります。たとえば、
例)「SEOとは」「ホームページ 初心者」
例)「SEO 対策 方法」「ホームページ 制作 札幌 比較」
例)「SEO コンサル 依頼」「ホームページ 制作 見積もり」
のように整理することで、各段階に最適なコンテンツ設計が可能になります。
SEOでは、検索結果に表示される「競合コンテンツ」の内容を把握することが不可欠です。自社が狙いたいキーワードで上位表示されているページを分析し、以下のような観点を確認します。
この分析から、「上位表示されるために必要な水準」が見えてきます。また、競合の不足点を逆手に取り、自社ならではの強みを盛り込んだ差別化戦略も立てやすくなります。
さらに、自社の現在地を把握するために、Google Search Console や SEO分析ツールを使って現状のトラフィック、掲載順位、CVRなどの数値も可視化し、ベンチマークを設定します。
キーワードグルーピングと競合分析の結果をもとに、どのようなページを、どの順序で、どのドメイン内に配置するかを図解化した「コンテンツマップ」を設計します。
これは、SEO施策における「設計図」にあたる重要な工程です。
コンテンツマップでは、以下のような要素を整理します。
情報が体系的に整理されているサイトは、Googleからの評価も高くなりやすく、ユーザーにとってもストレスのない閲覧体験を提供できます。
SEOには、サイト内部の最適化(内部対策)と外部からの評価(外部対策)の2種類があります。限られたリソースの中で効率的に成果を出すためには、それぞれの施策に優先順位をつける必要があります。
【内部対策の一例】
【外部対策の一例】
SEOは中長期的に効果を発揮する施策です。まずは内部対策で土台を固め、並行して外部対策の準備を進めるような段階的戦略が効果的です。

戦略の基本構成が整ったら、次は具体的な実行フェーズに進みます。ここでは、SEO設計の要件定義から、実装・改善までの実務的なステップを詳しく解説します。
まず行うべきは「要件定義」です。これは、どのようなコンテンツを、どのような目的で、どのページにどのように設置するのかを事前に整理する工程で、以下のような項目を明文化します。
この段階で情報を整理することで、制作チーム・ライター・開発者間の認識が一致し、スムーズな制作と公開につながります。
特に、KPI設定は後述するモニタリングの基準にもなるため、目標値や期間を明確にしておくことが重要です。
次に重要なのが「コンテンツ企画」です。キーワードごとの検索意図に基づき、どのような切り口・構成・語調で書くかを企画し、ライティングのガイドラインを整備します。
【主な企画要素】
検索エンジンに評価されるコンテンツは、単なる文字数の多さではなく、「検索意図への応答力」「情報の網羅性」「読みやすさ」「専門性」に優れたものです。
ユーザーにとっての価値を最優先に、信頼性と親しみやすさのバランスを保った設計を心がけましょう。
また、企業ブログやオウンドメディアでは、ブランドのトンマナ(トーン&マナー)を維持した表現ルールを定めることも、運用上の安定につながります。
コンテンツ設計と並行して、「技術的SEO」や「UX(ユーザー体験)」の最適化も進めます。検索順位を上げるには、コンテンツの良さだけでなく、サイトそのものの技術的な完成度が求められます。
【技術的SEOの主な対応項目】
【UX向上に関する要素】
技術的な質は、Googleのクロール効率やページ評価に直結します。また、ユーザーがストレスなく情報にアクセスできることは、直帰率や滞在時間といったSEO評価指標にも好影響を与えます。
SEOは一度の施策で終わるものではありません。公開後もデータを継続的にモニタリングし、改善を繰り返すことで成果を高めていきます。
【使用する代表的なツール】
掲載順位、クリック率、インデックス状況、ページエラー
流入経路、直帰率、滞在時間、CV数
スクロール・クリックの動線可視化
被リンク分析、競合順位比較、キーワードランキング
モニタリングの結果をもとに、次のような改善を検討します。
こうしたPDCAサイクルの中で、常にユーザーとGoogleの両方を意識した最適化を積み重ねることが、競合に打ち勝つSEO戦略の鍵となります。

SEOで成果を出すためには、単に検索ボリュームの多いキーワードを狙うだけでは不十分です。検索ユーザーの意図、ページの役割、信頼性の構築など、いくつもの視点を組み合わせた「戦略的アプローチ」が不可欠です。ここでは、より本質的なSEO戦略の設計において押さえておくべき4つの視点を解説します。
SEO施策を検討する際、多くの人がまず注目するのがキーワードの検索ボリューム(検索数)です。しかし、検索ボリュームが多い=成果につながるとは限りません。重要なのは「その検索キーワードの背景にあるユーザーの意図(=検索意図)」です。
たとえば、「ホームページ 制作」と検索する人と、「ホームページ 制作 料金 相場」と検索する人では、検討の深さが明らかに異なります。前者は情報収集段階の可能性が高く、後者は具体的な業者探しをしているケースが多いでしょう。
検索意図に応じた適切なコンテンツを提供することが、CV(問い合わせ・資料請求・購入)につながるカギになります。
検索意図の分類例:
キーワード選定時には、数値だけでなく、ユーザーが「なぜその言葉を使って検索しているのか?」を読み解く視点が欠かせません。
Googleがユーザーの検索クエリを分類する際、よく使われるのが「クエリタイプ」です。代表的な分類として、以下の3つが挙げられます。
購入・問い合わせ・予約など、何らかのアクションを起こそうとしている検索(例:「Tシャツ 通販」「資料請求 フォーム」)
何かを知りたい、調べたいときの検索(例:「SEOとは」「Web制作の流れ」)
特定のサイトやブランドを探す検索(例:「ChatGPT ログイン」「Amazon ギフト券」)
SEO戦略を立てる際には、狙うキーワードがどのタイプに属するかを判断し、それに適したページ構成・導線設計を行う必要があります。
たとえば、DOクエリを狙う場合はCTAの位置や文言が重要になりますし、KNOWクエリであれば網羅性の高い記事や信頼性のある情報設計が求められます。
Googleは検索意図に合致したコンテンツを評価する傾向にあるため、検索意図 × クエリタイプ × コンテンツタイプの整合性が、成果を出すうえでの重要な鍵となります。
近年のGoogleアルゴリズムでは、「E-E-A-T」(経験・専門性・権威性・信頼性)という評価基準が非常に重視されています。特に医療・金融・法律などのYMYL(Your Money or Your Life)領域だけでなく、企業サイト・BtoB領域でもE-E-A-Tの重要性は増しています。
E-E-A-Tの構成要素:
実体験に基づく記述・写真・事例など
専門家による監修、肩書き、資格、発信内容の深さ
外部からの評価(被リンク、レビュー、SNSなど)
運営者情報、プライバシーポリシー、SSL、口コミ対応など
SEOコンテンツの企画・制作にあたっては、単に検索ワードを入れるだけでなく、「誰が」「なぜ」「どの立場で」発信しているのかを明示する工夫が必要です。
たとえば、
Googleは「人の役に立つかどうか」を重視するアルゴリズムを強化しているため、E-E-A-Tは今後もSEOにおける本質的な評価軸として欠かせません。
SEOは、短期間で結果が出る広告とは異なり、中長期で育てていくマーケティング施策です。そのため、継続的なモニタリングと改善が前提となります。
【PDCAを回す際の実務ポイント】
特に、公開直後は順位が安定せず、検索上位に表示されるまでに1〜3か月以上かかることが一般的です。焦らず定期的に成果指標(アクセス数・CV・滞在時間・離脱率など)を確認し、改善サイクルを継続することが重要です。
また、SEOはアルゴリズムのアップデートや競合状況により順位変動が起きやすい領域でもあります。中長期での戦略設計とリスク分散を前提に、「SEO=積み上げ型の資産づくり」であるという視点で取り組む姿勢が求められます。

成果を上げるSEO戦略において、直感や経験だけに頼るのではなく、データに基づく判断が欠かせません。検索順位やトラフィックは常に変動しており、ユーザー行動も多様化しています。ここでは、SEOの現状把握と改善に役立つ主要ツールと、その活用ポイントを紹介します。
SEOにおける基本中の基本が、Google Search Console(サーチコンソール)とGoogle Analytics 4(GA4)の導入と活用です。この2つのツールを連携して使うことで、検索パフォーマンスとユーザー行動の両面から分析が可能になります。
SEO施策の成果検証においては、「どのページが、どの検索語で、どのような行動をもたらしているか?」という一連のデータを追うことが非常に重要です。特に改善すべきページやキーワードの特定、内部リンク設計の見直しなど、次のアクションにつなげる情報が得られます。
SEO施策の起点となるキーワード選定では、Googleキーワードプランナーやラッコキーワードといったツールが役立ちます。
Google広告の管理画面から使えるツールで、以下のような機能があります。
検索ニーズの定量的な把握に役立つ一方で、無料利用時は数値がざっくりとした幅(例:100〜1,000)で表示されるため、補助的な使い方が推奨されます。
特に、ユーザーがどのような疑問や課題を抱えているかを洗い出す際に重宝します。SEOコンテンツの構成案を練る際や、FAQ・記事タイトルの検討にも有効です。
自社の施策だけでなく、競合のSEO状況を分析することで、戦略に磨きをかけることが可能です。代表的なツールとしては、Ahrefs(エイチレフス)やSEMrush(セムラッシュ)があり、以下のような情報が得られます。
こうした情報をもとに、自社と競合のギャップを分析し、狙うべきキーワードやコンテンツの優先順位を決めることができます。特に、競合がカバーしていないニッチ領域の発見や、被リンク獲得のヒントを得るうえでも有用です。
SEO戦略の成果は、社内の体制とリソースの充実度に大きく左右されます。戦略が明確でも、実行部隊が確保できていなければ、成果につながる前に立ち消えてしまうことも少なくありません。
まず必要なのは、SEOの基本的な理解を持つ担当者の配置です。外部に依頼する場合でも、社内にSEOの判断軸を持つ人材がいなければ、戦略の整合性や投資対効果の検証が難しくなります。Web担当者や広報・マーケティング部門がこの役割を担うケースが多いですが、役割を明文化し、KPIの共有や定期的なレビュー体制を整備しておくことが重要です。
次に必要なのは、リソースの明確化です。コンテンツの制作体制(ライター、編集、デザイナー)、技術面の対応(エンジニア、CMSの保守)、分析ツールや外部サービスの導入に関する予算などを明確にし、継続的な運用が可能な体制を構築する必要があります。SEOは短期で成果が出るものではないため、継続的なPDCAサイクルを回すことが前提になります。
また、社内体制において「社内で完結させる部分」と「外部と連携する部分」を線引きしておくと、判断や行動のスピードが格段に向上します。
自社にSEOの専門人材がいない場合や、特定領域での強化を図りたい場合には、外部パートナーの活用が有効です。とはいえ、外部パートナーは数多く存在し、費用対効果や戦略性に大きな差があるため、選定には注意が必要です。
外部パートナーを導入すべきタイミングとしては、以下のようなケースが考えられます。
選び方のポイントは、単なる「順位上昇の実績」ではなく、「課題設定力」と「戦略設計力」です。ヒアリングを通じて業種理解の深さや、事業ゴールに基づく提案ができるかどうかを見極めましょう。
また、月額固定費型か、成果報酬型か、プロジェクト単位かなど、契約形態によって関与度も異なるため、自社の体制や目的に合った契約モデルを選ぶことも重要です。過剰な期待や丸投げではなく、あくまで「自社とともに戦略を磨く伴走者」として活用する視点が欠かせません。
近年のSEO環境は、AI技術の進展によって大きな転換期を迎えています。とりわけ、Googleが導入を進める「生成AIによる検索結果表示(SGE)」は、検索ユーザーの行動と検索結果の構造そのものを変えつつあります。
従来の「キーワード最適化」「コンテンツ量産」といったテクニック主導のSEOから、検索意図に対する最適解を提供するコンテンツへと重きが移っています。つまり、ユーザーの課題を本質的に理解し、専門性・信頼性・体験価値を提供することが、今後のSEOにおいて最も重要な価値基準になるのです。
加えて、AI生成コンテンツが急増する中で、Googleはオリジナリティや一次情報の価値をより厳しく評価しています。安易なAIコンテンツではなく、「体験に基づいた知見」や「独自の調査・分析」「具体的な事例紹介」といった差別化要素がますます重要になります。
また、構造化データやページエクスペリエンス(UX)、音声検索対応、動画SEOなどの要素も無視できません。AI時代のSEOでは「高度なコンテンツ企画力×技術対応×UI/UX最適化」の三位一体の戦略が求められます。
医療・金融・法律・健康・教育といったYMYL(Your Money or Your Life)領域では、他ジャンルよりもはるかに厳格な評価基準が設けられています。YMYLに該当するテーマでは、検索エンジンが「ユーザーの人生に悪影響を与えるリスク」を慎重に避けようとするため、信頼性・正確性・専門性の担保が絶対条件です。
そのためYMYL領域におけるSEO戦略は、単なるコンテンツ制作だけでは成立しません。以下のような複合的な対応が求められます。
さらに、Googleは医療・健康ジャンルを中心に、YMYL領域の検索結果に対して大幅なアップデートを繰り返しており、アルゴリズム変動の影響も大きくなっています。従って、リスクコントロールを含めたSEO設計と、Googleの評価指標の変化を常にウォッチしながら運用していく姿勢が不可欠です。
YMYL領域に参入する際は、戦略そのものが専門性に基づいて構築されている必要があり、SEO単体ではなく「コンテンツマーケティング全体」や「ブランディング施策」と連動させる視点が必要です。
医療・金融・法律など、人生やお金に大きく関わる「YMYL領域」は、SEOにおいて最も厳しい評価を受けるジャンルです。E-E-A-Tの重要性や対策の具体例を交えながら、YMYLにおける戦略設計のポイントをわかりやすく解説します。
AI時代におけるWeb制作の新常識「AIO(AI Optimization)」とは?従来のSEOとの違いや共存のポイント、AIを活用したコンテンツ設計の最適解を、実践視点で解説しています。
本記事では、SEO戦略の本質を「テクニックではなく設計図」と位置づけ、その立案から実行、改善までの全体像を解説してきました。
SEO戦略とは、検索順位の向上だけを目指すのではなく、「誰に・どんな情報を・どのように届けて、どんな成果を得たいのか」を明確に描くことから始まります。そのためには、ペルソナ設計、検索意図の深掘り、キーワードのグルーピング、競合分析、コンテンツマップの設計など、多角的な準備が欠かせません。
また、戦略の実行においては、ライティング・技術的SEO・UXの最適化といった実務を丁寧にこなし、Google Search ConsoleやGA4などを活用して、定量的に効果を測定・改善する姿勢が求められます。中でも、検索意図への対応力と、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の担保が、成果を左右する重要な要素です。
さらに、AIの普及やYMYL領域の厳格化など、SEOを取り巻く環境は常に変化しています。こうした中で成果を上げ続けるには、戦略を「一度作って終わり」にせず、社内外の体制を整備し、PDCAを継続して回し続ける体制を持つことが成功の鍵となります。
SEOは、単なる集客手段ではなく、顧客との信頼を育む「資産構築型マーケティング」です。だからこそ、焦らず、妥協せず、戦略的に取り組むことが、未来のビジネス成果を築く第一歩となるのです。
「コンテンツを増やしているのに成果が出ない」「どのキーワードを狙えばいいか分からない」そんな迷いを感じたら、SEOの戦略設計が必要なサインかもしれません。
ARDEMでは、貴社の事業モデルや競合環境を踏まえたSEO戦略を立案し、設計から運用まで伴走支援いたします。まずは、お悩みや目標をお聞かせください。
▶ お問い合わせはこちら
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。