Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
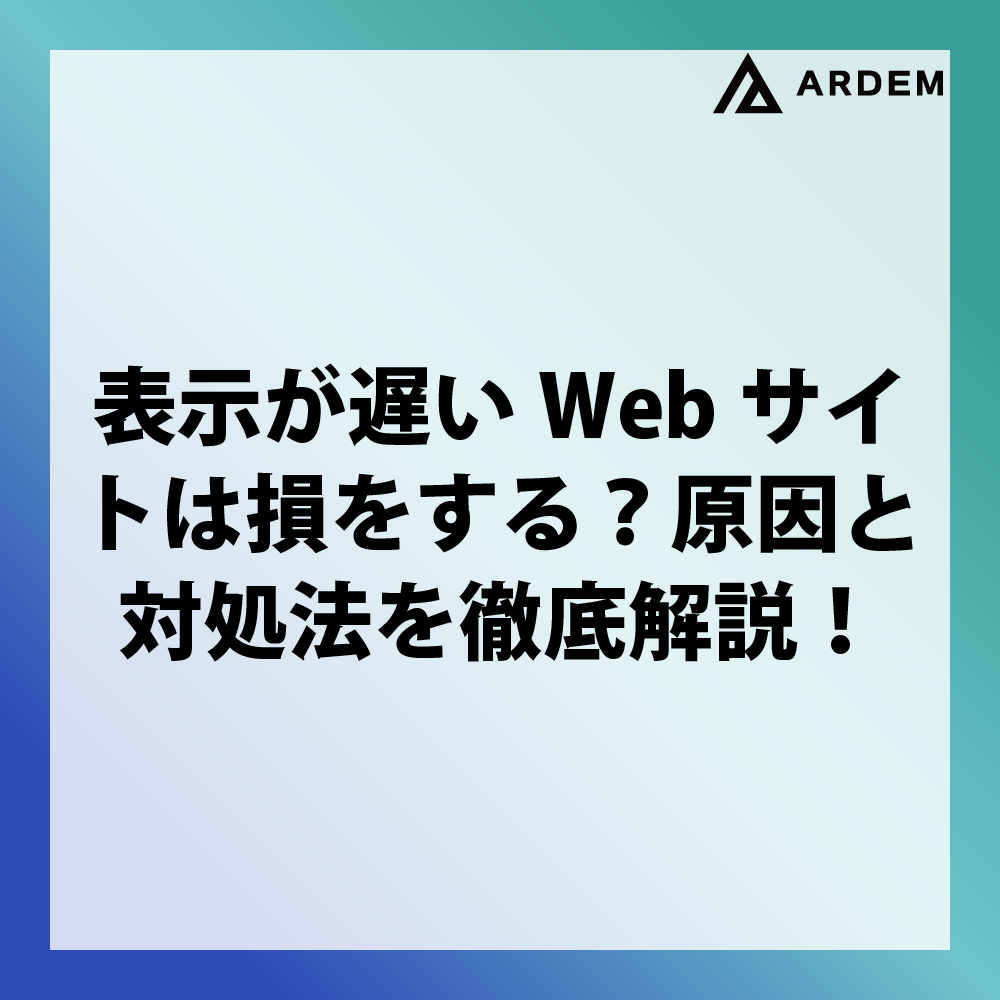
目次
「自社のホームページ、なんだか表示が遅い気がする…」
そんな違和感を覚えたことはありませんか?
Webサイトの表示速度は、ユーザーの離脱や検索順位に大きく関わる重要な要素です。読み込みに3秒以上かかると、訪問者の約半数が離脱するといわれており、放置すれば集客や成果に直結するリスクもあります。
本記事では、Webサイトが重くなる原因とその見極め方、今日から取り組める改善方法までをわかりやすく解説します。企業の担当者やWeb担当者の方は、ぜひ一度チェックしてみてください。
サイトの表示速度、今すぐ見直しませんか?
離脱率や検索順位に影響する「サイトの重さ」。気になった今が改善のチャンスです。無料相談も受け付けています。
▶ お問い合わせ
Webサイトの表示速度が遅くなる要因は複数あり、原因を正確に把握しなければ的確な対策はできません。ここでは特に影響の大きい代表的な原因を5つ紹介します。
画像はWebサイトにおいてもっとも容量を圧迫する要素のひとつです。高解像度の画像や未圧縮の写真をそのまま使用すると、読み込みに時間がかかり、ページ全体の表示速度が低下します。特にスマートフォンなどモバイル環境では、通信速度やデータ量の制限が影響しやすく、ユーザー体験に大きな悪影響を与える原因となります。
機能追加やアニメーションの演出に使われるJavaScript、デザインを整えるためのCSSも、量が多くなると読み込みが重くなります。また、複数のファイルがバラバラに読み込まれている場合や、使用していないコードが残ったままになっている場合も、処理負荷を増やす要因となります。
SNSのタイムライン表示、YouTube動画の埋め込み、Googleマップなど、外部サービスを多用していると、それぞれのサーバーからデータを取得する時間がかかり、ページ全体の表示速度が遅くなります。外部サービス側の応答状況にも左右されるため、自社ではコントロールしづらい点にも注意が必要です。
サーバーの性能や設置環境も、Webサイトの表示速度に大きく関係します。アクセス数が増えると処理能力を超えてしまい、応答が遅くなることもあります。また、安価な共有サーバーでは他サイトの影響を受けることもあり、自社サイトの表示速度が不安定になる原因になります。
WordPressなどのCMS(コンテンツ管理システム)を利用している場合、便利だからといって多数のプラグインを導入すると、それぞれが処理を行い、結果的にサイト全体の動作が重くなります。また、デザイン性に優れたテーマでも、裏側で多くのスクリプトが動作していれば読み込みに影響します。必要最小限に抑える見直しが重要です。
Webサイトの表示速度が遅いことは、単なる「使い勝手の悪さ」にとどまらず、ビジネスに直結するさまざまな損失を招きます。ここでは、代表的な3つのデメリットを見ていきましょう。
ページがなかなか開かないと、ユーザーはすぐに他のサイトへ移動してしまいます。特にスマートフォンユーザーは表示の遅延に敏感で、3秒以上かかると半数以上が離脱するといわれています。これはせっかく広告や検索から流入したユーザーを逃すことになり、大きな機会損失につながります。
Googleは、ページの表示速度を検索ランキングの要素のひとつに取り入れています。表示速度が遅いページは、ユーザー体験が悪いと判断され、順位が下がる可能性があります。特にモバイル検索においては、速度が重視されやすく、改善を怠ると検索結果の上位表示が難しくなります。
商品購入やお問い合わせといった成果(コンバージョン)に至る前に、サイトの重さが原因で離脱されてしまえば、本来得られるはずだった成果が失われます。また、ページにアクセスしてもすぐに戻ってしまう「直帰率」も高まり、マーケティング施策の効果が発揮できなくなります。スピードは、信頼や安心感にも直結する要素です。
Webサイトの表示が遅いと感じたとき、「何から手をつければよいのか分からない」と悩む方も多いのではないでしょうか。ここでは、専門的な知識がなくても始めやすい実践的な改善策を5つに分けて解説します。スピード改善は、ユーザー体験の向上だけでなく、SEOやコンバージョンにも大きく寄与します。できるところから、ひとつずつ取り組んでみましょう。
画像は、Webサイトの読み込みに最も影響を与える要素のひとつです。特に高解像度の写真や未圧縮のPNGファイルなどを多用していると、ページ全体の表示が遅くなってしまいます。
まずは、画像のファイルサイズを圧縮することが基本です。無料のオンラインツール(TinyPNGやSquooshなど)を使えば、画質をほとんど落とさずに軽量化することが可能です。
加えて、WebPという次世代フォーマットへの対応も重要です。WebPはJPEGやPNGと比べてファイルサイズを大幅に削減できるため、ページ全体の表示速度が大きく改善されます。WordPressの場合、プラグインやテーマがWebPをサポートしていることもあるため、対応状況を確認しておくとよいでしょう。
サイトの機能やデザインを実現するために不可欠なJavaScriptやCSSも、最適化がされていないと読み込みの遅延を引き起こす要因になります。たとえば、複数のスクリプトファイルを個別に読み込んでいたり、不要なコードが残っていたりすると、それだけでブラウザの処理が重くなります。
改善策としては、まず「縮小化(minify)」を行うことが有効です。これは、コードの空白や改行、コメントなどを削除し、ファイルサイズを軽くする方法です。WordPressであれば「Autoptimize」や「LiteSpeed Cache」などのプラグインを使って簡単に実施できます。
また、使用していないCSSやJavaScriptの読み込みを停止する「遅延読み込み(後述)」や「非同期読み込み(async・defer)」の設定も、読み込みのスピードアップに効果的です。
キャッシュとは、一度アクセスしたWebサイトのデータをユーザーのブラウザやサーバーに一時的に保存しておく仕組みのことです。次回以降のアクセス時に再読み込みをせずに表示できるため、表示速度が大幅に向上します。
WordPressでは「W3 Total Cache」や「WP Super Cache」といったキャッシュ系プラグインを活用することで、ブラウザキャッシュやページキャッシュ、オブジェクトキャッシュなどを簡単に導入できます。
また、「遅延読み込み(Lazy Load)」の設定を行えば、ユーザーがスクロールしたタイミングで画像や動画が表示されるようになり、最初の読み込み時間を短縮できます。特に画像が多いサイトでは、大きな効果が期待できます。
改善策をいくつか試しても表示速度が上がらない場合は、使用しているサーバーそのものに原因があるかもしれません。格安の共用サーバーでは、他のサイトの影響を受けやすく、処理速度や安定性が劣ることもあります。
中規模以上のトラフィックがある場合や、ECサイトのように処理が重いコンテンツを多く扱う場合は、VPSやクラウド型サーバー、あるいは高速表示に特化したマネージドサーバーへの移行も検討すべきです。
また、サーバー側のPHPのバージョンが古いと、処理能力が落ちることがあります。最新バージョンへの更新や、GZIP圧縮・HTTP/2対応の有無も確認しておきましょう。
WordPressなどのCMSを使っている場合、プラグインの数が増えるほど、サイトの動作は重くなりがちです。特に、ページごとに不要なスクリプトやCSSを読み込んでいる場合、表示速度に直接影響を及ぼします。
まずは現在使用しているプラグインの一覧を見直し、本当に必要なものだけに厳選することが大切です。また、1つのプラグインで複数の機能をカバーできる場合は、統合してしまうのも有効な手段です。
同様に、使用しているテーマも軽量なものに変更するだけで速度が改善するケースがあります。デザイン性と機能性を両立しつつ、表示が軽いテーマを選ぶことで、ユーザー体験を損なうことなくパフォーマンスを維持できます。
表示速度の改善には、まず現状を正しく把握することが欠かせません。直感的に「遅い」と感じても、その原因が画像にあるのか、サーバーにあるのか、スクリプトなのかは判断しづらいものです。そこで役立つのが、ページの表示速度を測定・分析できる無料ツールの活用です。
以下では、特に信頼性が高く、プロの現場でもよく使われている「PageSpeed Insights」「GTmetrix」「WebPageTest」の3つのツールについてご紹介します。どれも無料で利用でき、複数を併用することで、より正確な分析と改善方針の判断が可能になります。
Googleが提供する「PageSpeed Insights(ページスピードインサイト)」は、最もよく使われている速度分析ツールのひとつです。URLを入力するだけで、モバイルとパソコン両方の表示速度を測定し、100点満点でスコア表示してくれます。
このツールの優れている点は、単なるスコアだけでなく「何がボトルネックになっているか」を具体的に示してくれることです。たとえば、「使用していないCSSの削除」「画像の次世代フォーマット化」「サーバー応答時間の短縮」など、改善すべき項目がリストアップされ、どの程度の時間短縮効果があるかも数値で把握できます。
注目すべき指標としては以下の4つがあります。
とくにLCP(メインコンテンツの読み込み完了時間)は、ユーザーが「表示された」と感じる速度を左右する重要な指標です。LCPが2.5秒以内に収まっていれば、概ね「速いサイト」といえます。
また、PageSpeed Insightsは「実際のユーザーのデータ(フィールドデータ)」と、「シミュレーションによるデータ(ラボデータ)」を両方見られるのも特徴です。アクセス数が多いサイトでは、実ユーザーの体感速度に基づく分析が特に有効です。
PageSpeed Insightsだけではカバーしきれない部分を補完してくれるのが、「GTmetrix」と「WebPageTest」です。これらを組み合わせて使うことで、より多角的にサイトのパフォーマンスを分析できます。
GTmetrixは、カナダの企業が提供している表示速度分析ツールで、LighthouseやWeb Vitalsに基づく詳細なレポートを表示してくれます。URLを入力すると、読み込みの各フェーズ(DNS、接続、初回バイト、DOM読み込みなど)にかかる時間や、読み込んだファイルのサイズと数などがグラフ化され、非常に視覚的にわかりやすいのが特徴です。
また、「Waterfallチャート」を見ることで、どのリソースの読み込みに時間がかかっているかをピンポイントで特定することが可能です。画像、CSS、JavaScriptなど、どのファイルがボトルネックになっているのかが一目で分かるため、技術的な改善作業を進めやすくなります。
無料アカウントを作成すれば、テスト地域やブラウザ(Chrome/Firefoxなど)を選ぶこともでき、実際のユーザー環境に近い形で検証できます。
WebPageTestは、より詳細かつ専門的な視点で表示速度を分析したい場合におすすめのツールです。特に「Time to First Byte(TTFB)」や「Start Render」など、ページがどのタイミングで“視覚的に”読み込みを始めるのかに注目した指標が充実しています。
このツールの特徴は、読み込みの各段階における「時間経過のスクリーンショット」をタイムライン形式で確認できる点です。ユーザーの視点から見て、どのようにページが描画されているかを「見た目ベース」で確認できます。
また、接続する場所(日本/アメリカ/ヨーロッパなど)を指定できるため、海外向けのサイトや多言語サイトを運営している場合にも有効です。
表示速度の改善に向けてツールでの計測や簡易的な対処を行っても、根本的な原因を解決できていない場合、またすぐに速度が低下することもあります。とくに事業用のWebサイトやWordPressなどのCMSを利用している場合は、構造そのものや運用のあり方を見直すことが、持続的な高速化には不可欠です。
ここでは、効果的な改善を進めるために押さえておくべき3つのポイントを紹介します。
サイトの速度改善といっても、すべてを一度に対処するのは現実的ではありません。とくに企業サイトや更新頻度の高いメディアでは、リソースも限られており、どこから手をつけるべきかを明確にすることが重要です。
優先順位を決めるうえで意識したいのは以下の3つの観点です。
例:トップページのファーストビュー、CTAが配置されたページ、フォームページなど
例:巨大な画像ファイル、非同期化できていないJavaScript、遅い外部リソースの読み込みなど
小さな改善でも体感速度が上がれば、離脱率の低下などすぐに効果が現れることがあります。
また、Google PageSpeed InsightsやGTmetrixのスコアを鵜呑みにせず、「どの項目がサイトのKPIに最も影響するか」という観点から判断すると、優先度の高い施策が明確になります。
現在、Webサイトの多くがWordPressで構築されていますが、WordPressは便利な反面、プラグインの増加やテーマの構成次第で簡単に重くなってしまうという弱点があります。WordPressサイトを最適化するためには、以下のようなアプローチが効果的です。
プラグインの見直しと整理
画像とメディアの軽量化
キャッシュとCDNの導入
テーマや構造の見直し
とくにテンプレートに含まれるjQueryや外部スクリプトの読み込みが遅延を引き起こしているケースも多く見られます。開発会社や制作会社と連携して、サイト構造の最適化も視野に入れましょう。
自社内で改善作業を進めていても、「何をしてもスコアが上がらない」「触ると壊れそうで怖い」といった場面に直面することは少なくありません。そのようなときは、無理をせず、Web制作会社やサーバーの専門業者への相談を検討しましょう。
外注を検討する基準として、次のような状況が挙げられます。
また、速度改善を外注する際は、「一時的にスコアを上げる」だけではなく、「将来の更新や拡張を見据えた継続的改善」ができる体制を整えることが大切です。
とくにWordPressに詳しい制作会社や、PageSpeed Insights・Lighthouseの対策経験が豊富な業者を選ぶと、スムーズに改善が進みやすくなります。費用対効果を見極めつつ、技術的なサポートを受けながら取り組むのが理想です。
SEO対策は難しい?そんな方のために、最新情報を交えて分かりやすく解説。検索上位を目指すための基礎から実践までをカバーした保存版です。
せっかく作ったホームページが検索結果に表示されない…そんな悩みを抱えていませんか?SEO対策の基本とともに、よくある原因とその解決策を解説します。
Webサイトの表示速度は、単なる利便性の問題ではなく、ユーザーの行動や売上、企業の信頼性にも深く関わっています。「なんとなく表示が遅い」と感じる段階でも、すでにユーザーの離脱や機会損失が起きている可能性があります。
本記事では、サイトが重くなる原因の具体例や、今すぐ実践できる改善策、根本的な見直しの考え方までを解説しました。まずは「どこが重いのか」を正しく把握し、ユーザー目線と事業目線の両方から優先順位を決めて取り組むことが重要です。
特に、WordPressなどCMSを利用している企業サイトでは、定期的なメンテナンスと専門家との連携が、快適な表示速度の維持につながります。キャッシュ設定や画像圧縮だけでなく、サーバー選びやテーマ構成、プラグインの精査まで踏み込んで対策を進めましょう。
表示速度の改善は、ユーザー満足度を高め、SEO対策にもなり、最終的に「成果が出るサイト」へと近づくための大きな一歩です。アクセス解析の数値だけでなく、体感的な軽さ・快適さを意識しながら、継続的な改善に取り組んでいくことが、これからのWeb運用には欠かせません。
その遅さ、機会損失かもしれません。
表示速度の改善は売上や成果に直結します。まずは現状分析から始めてみませんか?ARDEMが丁寧にサポートします。
▶ お問い合わせ
関連記事

ARDEM広報担当
Harada Asuka
Author Profile
「誰かの『伝えたい』を、ちゃんと届く形にしたい」そんな思いから、2024年に中途入社。
これまで複数のブランディング案件に従事し、サービス認知度の向上や採用応募数の倍増など、成果に結びつくコミュニケーション設計を実践。
UX・SEO・CV導線を意識したコンテンツ制作を得意とし、見た人に伝わるだけでなく、行動につながる設計を重視。
情報の届け方ひとつでビジネスが大きく変わる面白さに惹かれ、現在は自社サービス運用・サービスブランディング・採用ブランディングを担当している。

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。