Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
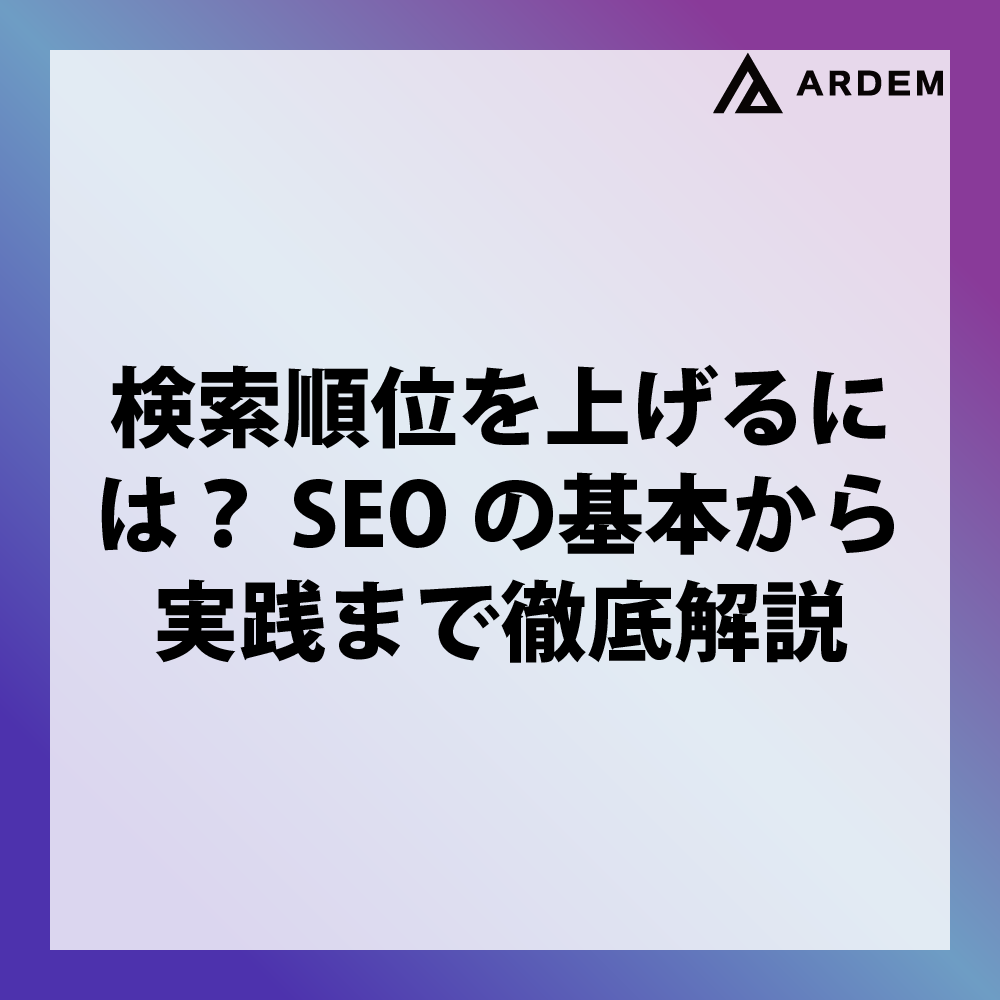
目次
インターネット上に無数の情報があふれる現代、ホームページをただ作るだけでは集客や成果にはつながりません。
多くの人に見てもらい、成果につなげるには「検索結果で上位に表示されること」が重要です。
しかし、「なかなか順位が上がらない」「何をすればいいのか分からない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、検索順位を上げるために必要なSEO(検索エンジン最適化)の基本から、具体的な内部対策・外部対策、コンテンツ改善、そして順位の継続的な改善方法までを、体系的かつ実践的に解説します。
「ホームページを成果につなげたい」「正しいSEOの知識を身につけたい」とお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。
検索順位を上げたいなら、まずは「サイトの現状分析」から。
\無料相談はこちら/
▶ お問い合わせ
検索順位とは、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードを入力した際に、自社のWebページが検索結果の何番目に表示されるかを指します。この順位は、検索エンジンが膨大な情報の中から「どのページが最もユーザーにとって価値があるか」を判断し、表示順を決定しているのです。
検索エンジンの動作は主に次の3段階に分かれます。
GooglebotなどのロボットがWeb上のページを巡回し、新しいページや更新されたページを発見します。
発見されたページの内容がGoogleのデータベースに登録され、検索に対応できる状態になります。
検索キーワードに対して最適なページを判断し、検索結果として順位付けされて表示されます。
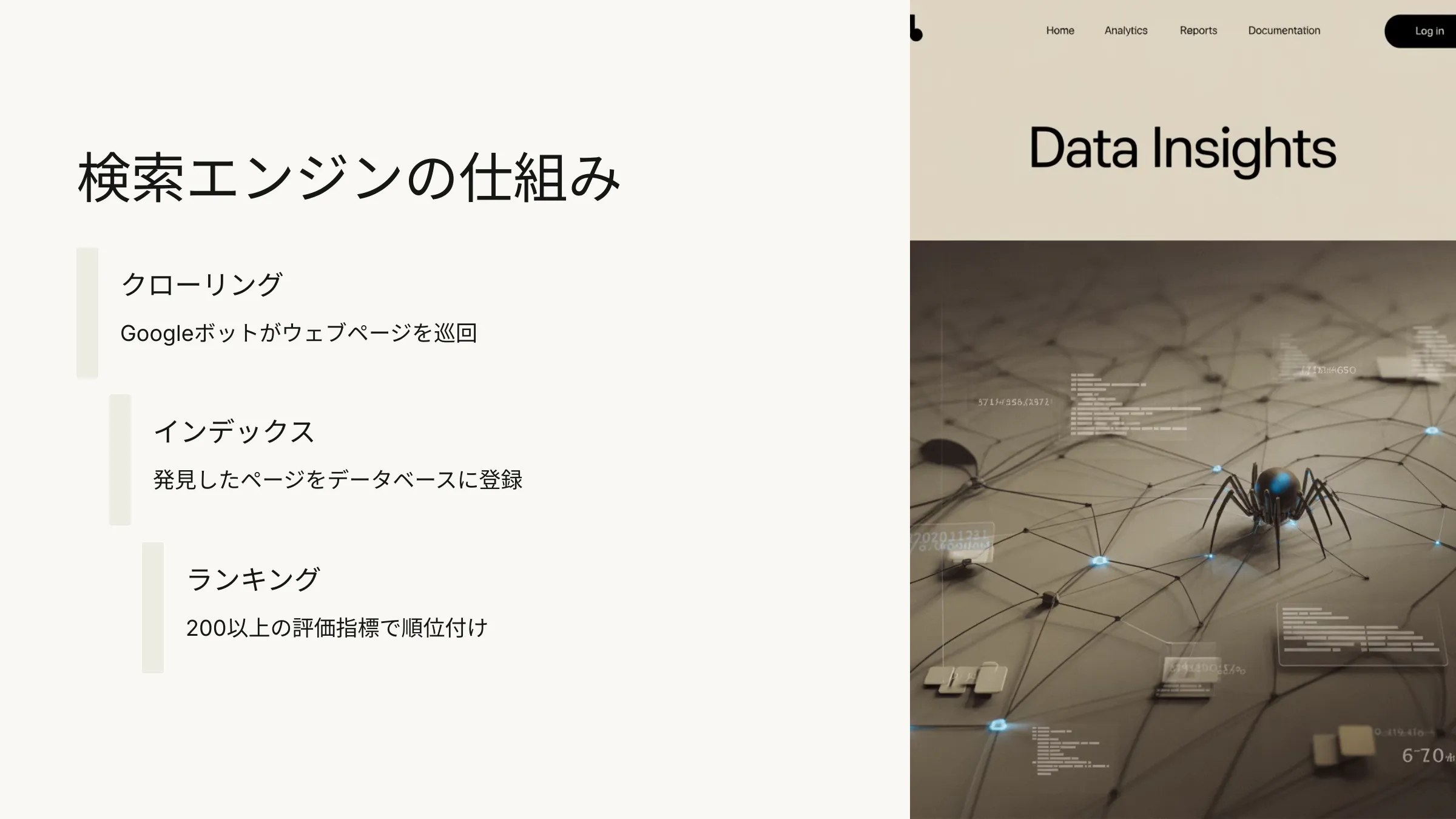
この際、Googleは200以上とも言われる評価指標を元に、各ページをランキングしており、コンテンツの質や被リンク、ユーザーの行動などが主な評価要素とされています。
つまり、検索順位を上げるには、この仕組みを正しく理解し、検索エンジンに「有益で信頼性のあるページ」として認識されるよう最適化する必要があります。
順位がビジネスに与える影響とは?
検索順位は、Webサイトの集客力に直結します。特に、検索結果の1ページ目(1〜10位)に表示されるか否かで、アクセス数は大きく変わります。さらに、1位と2位でもクリック率には顕著な差があり、一般的に以下のような傾向が見られます。
つまり、検索順位1位のページは他の順位と比べて数倍のアクセスを集める可能性があるということです。
検索順位の上昇は単なるアクセス増に留まらず、問い合わせ数や売上の増加、ブランド認知の向上にも直結します。
また、検索経由の訪問者は「自分で課題を持ち、能動的に情報を探している層」であるため、購買意欲や成約率が高いことも特徴です。これらの点からも、検索順位はオンラインマーケティングにおいて非常に重要な指標といえるでしょう。
検索順位は、単に「内容がある記事を書けば上がる」ものではありません。Googleが採用する複数の評価基準に則って、総合的にページの価値が判断され、順位が決定されます。この章では、その主要な要因を3つの視点から整理して解説します。
Googleは検索順位を決定する際、200以上のシグナル(評価項目)を用いています。以下はその中でも特に重要とされる代表的な要素です。
ユーザーの疑問に的確に答え、有益で独自性がある内容が評価されます。文字数や装飾より「中身の深さ」が重要です。
他サイトから自然に貼られたリンクは、信頼性・権威性の指標になります。量より質が問われます。
自サイト内でのリンクの張り方が整理されているか。クローラーの巡回しやすさに直結し、SEOにも影響します。
スマホで快適に閲覧できるかどうか。現在はモバイル表示を基準に評価されるため、必須の要素です。
サイトの読み込み速度が遅いと離脱率が上がり、ユーザー体験が損なわれるため、検索順位に影響します。
SSL化(https://)されているかどうか。安全性が低いサイトは評価が下がる傾向にあります。
これらは単体で評価されるのではなく、ユーザーの検索意図との整合性や総合的なUX(ユーザー体験)として判断されます。
Googleの検索品質評価ガイドラインでは、特に重要視される2つの概念があります。それが E-E-A-T と YMYL です。
E-E-A-T は以下の4つの頭文字から構成されます。
E-E-A-Tは特に医療・法律・金融などの重要分野において重視されますが、他の業種でも基本的に押さえるべき指針です。
YMYLとは「Your Money or Your Life」の略で、「人の生活や人生に大きな影響を与える内容」を指します。
たとえば以下のようなジャンルが該当します。
これらの分野で低品質なコンテンツが上位表示されると、ユーザーに誤った判断をさせてしまう危険があるため、GoogleはE-E-A-Tとの掛け合わせで、特に厳しく評価を行っています。
Googleは年に数回、検索アルゴリズムの大規模な変更(コアアップデート)を行っています。これにより、検索順位が大きく変動することがあります。
コアアップデートの詳細なロジックは非公開ですが、下記のような姿勢が求められます。
順位変動に一喜一憂するのではなく、継続的な改善と読者目線の最適化を積み重ねることが最も重要です。
検索順位を上げるためには、質の高いコンテンツの提供が欠かせません。Googleは「ユーザーにとって有益かどうか」を最も重視しており、検索意図に沿った内容であること、わかりやすい構成であること、信頼性のある情報であることなどが求められます。
このセクションでは、検索上位を目指すための具体的なコンテンツ対策について、基本から実践ポイントまでをわかりやすく解説します。コンテンツを“作る”だけでなく“最適化する”視点が重要です。
検索エンジンは「検索キーワードの背景にある意図(インテント)」を重視して順位を決めています。ユーザーが何を知りたいのか、どんな問題を解決したいのかを深く理解することが、SEOでは非常に重要です。
検索意図は大きく分けて以下の3つがあります。
「〇〇とは」「△△の方法」など
「おすすめ〇〇」「〇〇比較」など
「〇〇 通販」「〇〇 予約」など
これらを意識してコンテンツを作ると、Googleの評価基準にマッチしやすくなり、上位表示につながります。
キーワード選定とその使い方
効果的なキーワード選定は、検索順位を大きく左右します。月間検索数、競合性、ユーザーの意図などを分析し、狙うべきキーワードを明確にしましょう。
また、選定したキーワードは次のような箇所に自然に含めるのが効果的です。
ただし、無理に詰め込むと「キーワードスタッフィング」と判断される可能性があるため、自然な文脈で使うことが前提です。
見出し構成と情報設計の最適化
Googleはページ内の構造も重視して評価します。特に見出し(hタグ)は、コンテンツの意味構造を伝える大切な手段です。
効果的な見出し構成のポイント
また、情報設計の面でも、結論から書く「逆三角形型」や、1見出し1テーマで書く「単位分割構成」が読者にとって親切です。
重複・薄いコンテンツの見直し
検索順位が伸び悩む原因の1つが、サイト内に重複したり内容が薄いページが存在することです。これらはGoogleから「価値のないページ」と判断され、全体の評価を下げるリスクがあります。
対応策としては、
といったことがあります。
コンテンツの質を全体的に底上げすることが、ドメイン全体の評価向上につながります。
検索順位を向上させるためには、外部からの評価だけでなく、サイト内部の構造や設定にも目を向ける必要があります。内部対策とは、検索エンジンがWebページを正しく理解・評価しやすいように、サイト内部を整える施策のことです。
以下では、特に効果の高い4つの内部施策について詳しく解説します。
タイトルタグ(title)とメタディスクリプション(meta description)は、検索結果でユーザーに最初に表示される重要な情報です。Googleもこれらの情報をコンテンツの要約として評価対象としています。
・主キーワードを文頭付近に入れる
・30〜35文字以内に収め、簡潔かつ魅力的に表現する
・競合と差別化できるオリジナル性のある内容にする
・ユーザーの悩みに共感し、解決の糸口を示す
・80〜120文字程度を目安に、自然な文章で
・クリックしたくなるような訴求(例:数字・具体性・緊急性)を含める
メタディスクリプションは直接的な順位要因にはなりませんが、CTR(クリック率)を向上させることで間接的に評価を高めます。
内部リンクとは、自サイト内のページ同士をリンクでつなぐ施策です。Googleはリンクをたどってコンテンツの関係性を理解するため、適切な内部リンク構造はSEOにおいて不可欠です。
・関連性の高いページ同士を自然にリンクさせる
・パンくずリストを活用し、階層構造を明確に
・ナビゲーションやサイドバーに重要ページへの導線を設ける
・アンカーテキストには文脈に応じたキーワードを使用
また、内部リンクはユーザーの回遊性向上にもつながり、直帰率の低下や滞在時間の増加といったユーザビリティの向上にも貢献します。
モバイルファーストインデックスが採用されて以来、スマホでの表示最適化はSEOの基本条件となりました。PCで最適化されたページでも、モバイル対応が不十分であれば順位が落ちる可能性があります。
・レスポンシブデザインを採用し、画面サイズに応じてレイアウトが変化するようにする
・ボタンやリンクのサイズは指で押しやすい大きさに
・フォントは視認性の高いサイズを設定し、行間や余白にも配慮
・モバイルでも読み込みが速くなるよう、画像やスクリプトの最適化を行う
モバイル環境での使いやすさは、ユーザー満足度の向上にも直結します。
Googleはページの表示速度や操作性を重視しており、Core Web Vitals(コアウェブバイタル)は検索順位に影響を与える明確な評価基準となっています。
・LCP(Largest Contentful Paint):ページの主要コンテンツが表示されるまでの時間
・FID(First Input Delay):ユーザーが最初に操作を行った際の応答速度
・CLS(Cumulative Layout Shift):ページ表示中のレイアウトのズレの量
・画像や動画は圧縮し、WebP形式を利用する
・不要なJavaScriptやCSSの削除・遅延読み込み(Lazy Load)を導入
・サーバーの高速化やCDN(コンテンツ配信ネットワーク)の利用
・外部スクリプトの見直し(例:SNSボタンやフォントの遅延読み込み)
ページ速度の改善は、離脱率の低下・コンバージョン率の向上にもつながるため、SEO施策としても非常に重要です。
外部対策は、サイト外からの評価を高めるための施策です。Googleのアルゴリズムは、他サイトからどれだけ信頼されているかをランキング要因のひとつとして重視しています。その中でも中心となるのが「被リンク(バックリンク)」ですが、無理なリンク獲得はかえって逆効果となるケースもあります。ここでは、正しく効果を出すための外部対策の基本と注意点を整理して解説します。
検索順位を上げるためには、高品質な被リンクを自然に獲得することが理想です。Googleは人為的にリンクを集める行為をスパムと見なすため、「自然さ」が極めて重要となります。
他サイトから紹介されやすい情報、専門性のある解説、独自性の高い事例記事などを公開することで、自然なリンクを得られる土台ができます。
関連業界のWebメディアやブログとの協力関係を築き、紹介記事やインタビュー企画などに掲載されることで、信頼性のある被リンクを獲得できます。
新サービスや実績発表をプレスリリースとして発信し、ニュースサイトや業界紙に取り上げられることで、権威あるサイトからのリンクが得られる可能性があります。
パートナー企業や業界団体の紹介ページにリンクを設置してもらうことで、ナチュラルリンクの一種として評価されやすくなります。
被リンクは「量より質」が重要です。信頼性が高く、関連性のあるサイトからのリンク獲得を目指しましょう。
被リンクに加えて、サイテーション(引用)やSNSでのシェア・言及も外部評価に関係するとされています。
リンクが貼られていなくても、企業名やサービス名、住所などが第三者のサイトや記事に記載されることで、間接的に信頼性が高まるとされる指標です。特にMEO(地図検索最適化)においては、Googleビジネスプロフィールとの情報の一致が重視されます。
X(旧Twitter)やInstagram、Facebookなどで記事が拡散されることで、被リンク獲得のきっかけになったり、検索エンジンが注目するトレンドワードとして認識されることがあります。
SNS戦略のポイント
・タイトルやアイキャッチで興味を引く
・ハッシュタグで話題性を広げる
・投稿頻度を保ち、継続的に流入を狙う
SNSの反応は直接的なSEO効果は限定的とされる一方、間接的に話題性・権威性を生むきっかけとなるため、コンテンツとの連動が大切です。
検索順位を短期間で上げたいという焦りから、ブラックハットSEO(検索エンジンのルールを逸脱する不正手法)に手を出してしまうケースもあります。しかしこれらの手法は、Googleからのペナルティ対象となり、最悪の場合は検索結果から除外されるリスクがあります。
・大量の低品質サイトからの不自然な被リンク購入
・リンクファームの利用
・自作自演のリンクネットワーク構築
・有料リンクの隠蔽的な売買
なぜ避けるべきか?
Googleは過去のアルゴリズムアップデート(パンダ・ペンギンなど)により、こうした不正リンクの効果を無効化またはマイナス評価するようになりました。
外部対策において最も重要なのは「信頼性のあるサイトからの自然な評価を得ること」です。検索順位を安定して上げたいのであれば、地道で健全な取り組みが最も効果的であることを忘れてはいけません。
検索順位を上げるためには、「今どのキーワードで何位に表示されているのか」を把握し、そのデータをもとに改善を繰り返す必要があります。感覚や推測だけで対策をしても、的外れになってしまうことが多いため、客観的な数値と実行力が成功のカギとなります。
ここでは、検索順位を継続的に改善するための手法とツール活用について解説します。
検索順位の推移を正確に把握するには、専用の「順位チェックツール」の活用が効果的です。これらのツールを使うことで、日々の変動を可視化し、SEO施策の効果を数値で検証することができます。
国内で非常に高いシェアを持つツール。キーワードとURLを登録するだけで、毎日の順位を自動で取得可能。
海外製でありながら多機能。競合比較やSERP履歴の記録など分析機能も豊富。
順位計測と被リンク分析、競合調査まで対応した総合SEOツール。高機能で月額費用も高め。
順位計測はSEOの「現状分析」に不可欠な工程です。数値の変化を的確に捉え、戦略に活かしましょう。
Googleサーチコンソール(GSC)は、Googleが無料で提供しているサイト運営者向けの分析ツールで、検索パフォーマンスの把握やエラー検出に役立ちます。
1.検索キーワードごとの表示回数・クリック数・平均順位の確認
2.ページごとの掲載順位とクリック率の測定
3.インデックス状況やクロールエラーの把握
4.サイトマップの送信やモバイルフレンドリーのチェック
1.サイトをGSCに登録(Googleアカウントとドメインの認証が必要)
2.「検索パフォーマンス」画面で重要キーワードの掲載順位をチェック
3.低クリック率のキーワードや順位が停滞しているページを特定
4.タイトル・ディスクリプションの改善や内部リンクの追加などの対策を実行
GSCは順位変動の原因分析にも使えるため、順位チェックツールと併用することで、より深いインサイトが得られます。
検索順位の向上は、一度の対策で完結するものではありません。重要なのは、継続的に改善を繰り返すサイクル=PDCA(Plan-Do-Check-Act)を回すことです。
Plan(計画)
Do(実行)
Check(評価)
Act(改善)
このPDCAを一定の周期で繰り返すことで、検索順位は徐々に安定し、上位表示も狙いやすくなります。順位変動に一喜一憂せず、長期的な視点で改善に取り組む姿勢が大切です。

検索順位を上げるには、コンテンツの充実や内部対策に加えて、ホームページ自体の設計や運用体制にも工夫が必要です。検索エンジンに評価されやすい構造や、更新しやすい仕組みを整えることで、長期的なSEO効果を実現できます。
ここでは、SEOに強いホームページを作るためのCMS選定、構築方法、そして外注のポイントまでを解説します。
ホームページの制作においては、CMS(コンテンツ管理システム)の選定が非常に重要です。中でもWordPressは、SEOに強いCMSとして世界中で支持されています。
WordPressがSEOに有利な理由
また、自社でブログや実績紹介、ニュース更新を行うことが簡単にできるため、継続的な情報発信によるSEO強化にもつながります。SEOに強いホームページを目指すなら、WordPressの導入は非常に有力な選択肢です。
どれだけ高機能なCMSを選んでも、SEOに強い構築・運用体制が整っていなければ効果は発揮できません。
構築時に押さえるポイント
運用体制で重要な点
構築だけで終わらず、運用こそがSEOの成果を左右します。そのためにも、制作会社と運用担当者が協力して、PDCAを回しやすい体制を築くことが鍵になります。
自社で構築や運用が難しい場合は、制作会社への外注も有力な選択肢です。ただし、どの会社でもSEOに強いサイトが作れるわけではありません。業者選定では、SEO実績と運用サポート体制の有無が大きな判断基準となります。
SEOに強い業者を選ぶポイント
外注時のコツ
SEO対策に取り組む中で、多くの企業や担当者が共通して抱える疑問があります。このセクションでは、よくある質問とその正しい理解を紹介し、SEOに対する誤解を解きながら、現実的な対策のヒントを提供します。
「対策をしているのに、なぜ順位が上がらないのか」という声は非常に多く聞かれます。検索順位が改善しない主な原因には、以下のようなものがあります。
検索ボリュームが少ない、あるいは競合が強すぎるキーワードを選んでいないか再確認が必要です。
ユーザーが求める情報に十分に答えていない場合、Googleから評価されにくくなります。
モバイル対応、ページ表示速度、内部リンクなどの基本が整っていないケースも多く見られます。
既存の情報をなぞっただけのコンテンツは、上位表示が難しいのが現実です。
順位が上がらないときは「全体設計・コンテンツ・技術面」の3つの視点で総点検することが大切です。
SEOは短期間で結果が出る施策ではありません。一般的に効果が現れるまでには3〜6ヶ月程度かかるといわれています。これはGoogleのインデックスと評価プロセスに時間がかかるためです。
ただし、下記のような要因により、タイミングは前後します。
新規ドメインは評価に時間がかかる傾向があります。
競合が多いジャンルでは、上位表示に時間を要します。
高頻度・高品質なコンテンツ追加は、早期の成果につながる可能性があります。
SEOは「育てていくもの」と捉え、短期的な成果に一喜一憂せず、中長期的な視点で継続することが成功の鍵です。
「SEOとリスティング広告(Google広告など)は何が違うのか?」という質問はよくあります。両者は集客手段として併用されることも多いですが、費用、効果の出方、信頼性、継続性などの観点で異なる特徴があります。
このように、SEOと広告はそれぞれに長所と短所があります。短期的な集客は広告、長期的な集客はSEOというように、目的に応じて使い分ける、あるいは両方を戦略的に活用することが理想的です。
「検索結果に表示されない…」その原因は1つではありません。インデックス未登録やコンテンツの質など、よくある問題とその解決法を基礎から解説します。
一時的に順位を上げる“裏技”にはリスクが伴います。ペナルティの対象となるブラックハットSEOの手法と、安全なSEO戦略との違いを押さえておきましょう。
ユーザーの「知りたい」に応えるコンテンツを作れていますか?検索意図の読み解き方と、それを踏まえたSEO対策のポイントを解説します。
検索順位を上げるためには、「これだけやればOK」といった万能の手段は存在しません。検索エンジンは日々進化しており、ユーザーにとって有益なコンテンツを提供しているか、技術的な最適化がなされているかを厳しくチェックしています。
そのため、順位向上には以下のような複合的なアプローチと継続的な改善が不可欠です。
SEOは「一度やって終わり」ではなく、「継続的に育てていくもの」です。地道な努力を積み重ねることこそが、検索上位の安定した成果につながります。
もし、自社での対応に限界を感じている場合は、SEOに強いホームページ制作業者や専門のパートナーと組むことで、より確実な成果が期待できます。適切な戦略と実行力をもって、持続的な検索順位の向上を目指しましょう。
SEOに強いホームページをご提案します。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。
▶ お問い合わせ
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。