Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
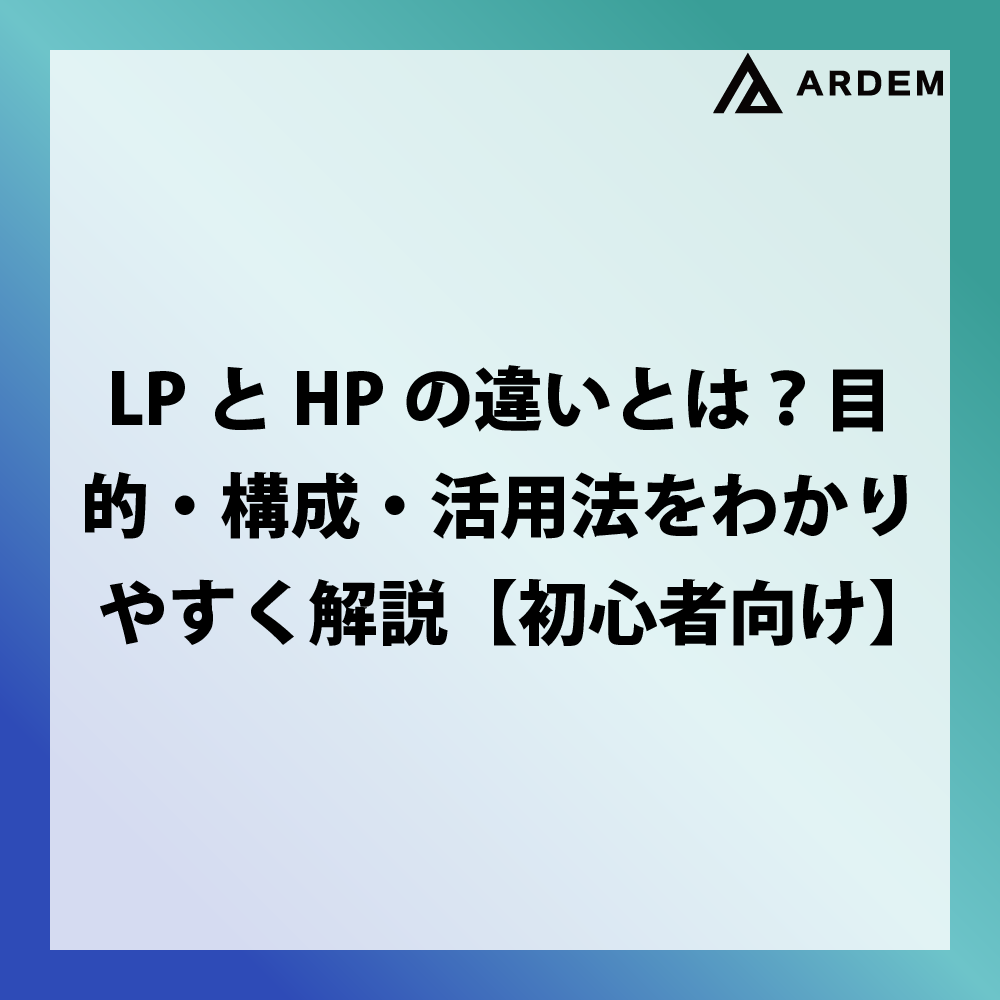
目次
Web集客やブランディングの相談を受ける中で、よくある質問のひとつが「LPとHPの違いって何ですか?」というものです。
どちらもインターネット上に公開される「Webサイト」ではありますが、その目的や構成、活用シーンはまったく異なります。闇雲にページを作るのではなく、役割を正しく理解して使い分けることで、Webの効果は何倍にもなります。
この記事では、LPとHPそれぞれの特性や違い、使い分け方についてわかりやすく解説します。これからWeb施策を始める方や、既存サイトの改善を考えている方はぜひ参考にしてください。
目的に合ったWeb戦略をご提案します
LPとHP、どちらを選ぶべきかお悩みの方へ。ARDEMでは目的に合わせたWeb制作・集客戦略のご提案が可能です。まずはお気軽にご相談ください。
▶ 無料相談はこちらから
LP(ランディングページ)とは、ユーザーが広告や検索結果などから最初にアクセスする「着地ページ」のことを指します。広い意味では、訪問者が最初にたどり着くすべてのWebページが該当しますが、一般的にマーケティングの文脈で「LP」と言う場合は、「商品・サービスの申し込みや資料請求など、1つの明確なアクションへと導くこと」を目的としたページを指します。
たとえば、化粧品の無料サンプル申し込み、オンライン講座の受講登録、保険相談の予約など、明確なコンバージョン(CV)をゴールとするページが該当します。訪問者の離脱を防ぎながら、効果的にアクションへと導く構成が求められます。
ランディングページは、その目的に合わせて非常にシンプルかつ直感的に作られています。一般的な特徴としては、以下のような構成が挙げられます。
ナビゲーションメニューが少なく、スクロールだけで情報が完結する構成が多く採用されます。これはユーザーの離脱を防ぎ、最後まで訴求を届けるためです。
キャッチコピー→共感を呼ぶ課題提起→解決策の提示→商品・サービス紹介→口コミや事例→アクション(CTA)という流れが一般的です。
資料請求・申込み・お問い合わせなどのボタンをページ内に何度も設置し、どこからでもコンバージョンできる設計にします。
スマホ閲覧を前提に、表示速度や視認性の高いデザインが必須です。ファーストビューでの印象づくりも極めて重要です。
このように、LPは情報を厳選し、ユーザーに迷わせない導線を設計することが最大のポイントです。

「LP=リスティング広告やSNS広告のリンク先」というイメージを持たれている方も多いかもしれません。たしかにLPは広告とセットで活用されるケースが非常に多いですが、LP自体は広告専用ページではありません。
実際には、自然検索からの流入や、既存のHPの一部として使われるLPも多く存在します。たとえば、特定のイベントキャンペーンページや、新サービス紹介専用ページなども「LPの構造」を取り入れて設計されることがあります。
また、LPの中には継続的に運用する「常設型LP」も存在します。一度作って終わりではなく、A/Bテストを繰り返しながら成果を改善していく手法が一般化しており、「LP=短期施策」と決めつけるのは正確ではありません。
つまり、LPは「広告用ページ」ではなく、「成果に特化した構造のページ」と理解するのが正確です。目的が明確で、訪問者に対するゴールが1つに絞られている点が、通常のWebページと大きく異なるポイントです。
「ホームページ(HP)」は、企業や団体がWeb上に設ける情報発信の拠点です。会社の顔としての役割を持ち、事業内容や理念、商品・サービス、採用情報など、幅広い情報を包括的に掲載することで、訪問者に総合的な理解を促す場となります。
広告からの流入だけでなく、名刺やチラシ、検索エンジンからの自然流入、SNSなど、あらゆる導線の受け皿となるのがHPです。また、会社の信頼性やブランドイメージを伝える重要な役割を担っており、企業にとってはオンライン上の「本社ビル」のような存在とも言えます。
特にBtoB領域では、問い合わせや商談前に必ずHPがチェックされることが多く、信頼感や企業姿勢を的確に伝えられるかどうかが、その後の商機に大きく影響します。
一般的な企業のホームページは、以下のような複数のページで構成されます。
第一印象を決めるページ。企業の特徴や最新情報をダイジェストで紹介。
企業理念、沿革、所在地、代表者などを掲載し、信頼性と透明性を示すセクション。
自社の提供する商品・サービス、技術、強みなどを詳しく紹介。SEO対策の観点からも重要なパートです。
クライアントとの関係性や成果を見せることで、信頼を補強する役割を果たします。
求人情報や社風、社員の声などを掲載し、採用活動の強化につなげます。
見込み顧客からのアクションを促す窓口。コンバージョン導線として重要です。
このように、ホームページは多面的な情報を整理して伝える「総合的な情報集約サイト」であることが特徴です。
ホームページの第一の目的は、企業の「信頼づくり」と「ブランド形成」です。創業理念や代表のメッセージ、事業領域、過去の実績などを体系的に伝えることで、「この会社はどんな会社か?」を正しく理解してもらう役割を果たします。
また、企業としての一貫したメッセージを発信できる場でもあり、名刺や会社案内パンフレットと同様に、企業活動を支える基盤となります。
さらに、情報の整理・更新がしやすく、ニュースやブログ、プレスリリースを通じてタイムリーな情報発信も可能です。紙の資料では難しい「最新の情報を常に届ける」体制を整える意味でも、ホームページは現代のビジネスには欠かせないツールと言えるでしょう。
LP(ランディングページ)とHP(ホームページ)の最も大きな違いは、「目的」です。LPは、広告やSNSなどからのアクセスを受けて、特定のアクション(資料請求・購入・問い合わせ・予約など)を促すために設計されています。いわば「一点集中型」で、訪問者の行動を最適化することが最大の目的です。
一方、HPは企業全体の情報を広く伝えることが目的です。信頼性の構築や会社案内、採用情報、事業内容の周知など、幅広い役割を持ちます。すべてのユーザーに対して網羅的な情報を提供するための「企業の公式な顔」として機能します。
つまり、LPは「集客や売上を最大化するための攻めのツール」、HPは「信頼とブランドを築くための守りの拠点」と言い換えることができます。
LPは、基本的に1ページで完結する縦長の構成が主流です。ファーストビューで関心を引き、サービスの特徴やメリット、料金、導入事例、FAQ、CTA(行動喚起)へと、ユーザーの心理に沿ったストーリーで構成されます。必要最低限の情報に絞り、離脱を防ぎながらコンバージョンにつなげる設計が特徴です。
対してHPは、トップページから会社概要、サービス紹介、採用情報、ニュース、ブログなど、複数ページにわたる「多層構造」で成り立っています。各ページごとに目的があり、必要に応じて深く情報を掘り下げられる構成になっています。
そのため、ユーザーが自ら情報を探索しやすく、理解を深めるのに適していますが、目的に応じた明確な導線設計がなければ、離脱や迷子の原因にもなりえます。
LPは「初見のユーザーをいかに逃さずアクションさせるか」がすべてです。1ページ内でストーリーが完結し、スクロールすることで自然に説得力が高まっていくよう設計されています。あえて外部リンクやメニューを設けないことも多く、集中と直感的な導線が重視されます。
一方、HPはユーザーごとにニーズが異なるため、複数の導線を持たせる必要があります。たとえば、見込み顧客、採用希望者、取引先など、ターゲットが多様であるため、それぞれが求める情報にたどり着きやすい構造やメニュー設計が求められます。
その結果、HPは「情報の交通整理」が重要なポイントとなり、直帰率や回遊性などを意識したUX設計が欠かせません。

「LP(ランディングページ)」と「HP(ホームページ)」のどちらを使うべきかは、達成したい目的によって大きく異なります。たとえば、明確な商品やサービスを紹介し、購入や問い合わせ、資料請求といった行動へと誘導したい場合は、LPが有効です。LPは訪問者に対して伝える情報を絞り込み、1ページ内で完結する構成になっているため、関心を持った人に対して強く訴求しやすいという特徴があります。
たとえば、「今すぐ申し込んでほしい」キャンペーンや、「期間限定」の商品・サービスを紹介する場面では、HPよりもLPのほうが反応率(CVR)を高めやすくなります。特に広告運用と組み合わせることで、大きな効果を生むことが期待できます。
一方で、企業全体の信頼感を高めたり、継続的な情報発信をしたり、採用活動など幅広い目的を持つ場合は、HPが必要です。会社概要、沿革、スタッフ紹介、事業紹介、ブログやお知らせなど、多くの情報を整理して掲載することで、企業としての姿勢や実績、ビジョンを伝えることができます。
たとえば採用活動では、「働く環境」「理念」「スタッフの声」など、応募者が安心できる情報を複数ページに分けて提供することが求められます。こうした構成はHPならではの強みです。

LPとHPは、目的に応じて「どちらかを選ぶ」というより、「両方を使い分ける」ことで大きな効果を発揮します。
たとえば、新しいサービスを告知する際に、広告の遷移先としてはLPを使ってダイレクトに申し込みを促しつつ、「この会社は信頼できるのか?」と気になったユーザーが、リンクからHPにアクセスできる導線を用意しておく。逆にHP内にバナーを配置して、特定の商品LPに誘導する流れをつくる。こうした相互リンクによる補完関係は、集客と信頼構築を両立させる上で非常に有効です。
また、広告運用を行っていない企業でも、LPのような構成を特設ページとしてHP内に設置するケースもあります。これにより、SEOの効果を得ながら、特定テーマでのコンバージョン獲得にも対応できます。
つまり、LPは「今すぐ成果を出す」ための直線的なツール、HPは「長く信頼を築く」ための基盤として、それぞれの役割を明確にしながら連携させることが、Webマーケティングにおける最適な選択肢となります。
LP(ランディングページ)でもHP(ホームページ)でも、成果を生むためには「何を、誰に、どう伝えるか」が非常に重要です。その中でも特に影響が大きいのが「コピー(文章)」と「CTA(行動喚起)」の設計です。
LPの場合、限られたスペースでターゲットの心を動かす必要があるため、「ベネフィット中心の見出し」「信頼性を高める実績紹介」「共感を誘う課題提起」「行動を促すCTAボタン」が必須です。読み手が疑問や不安を抱いた瞬間にその答えを提示できる構成が理想で、ファーストビューからスクロールごとの訴求まで一貫性を持たせることで、離脱を防ぎながらコンバージョンへ導きます。
一方、HPは幅広い訪問者を想定するため、「初めて訪れる人に会社の全体像をどう伝えるか」「どのページにいても次の行動が明確になるか」といった導線設計が重要になります。CTAも「お問い合わせ」だけでなく、「資料請求」「セミナー参加」「LINE登録」など、ターゲット層やフェーズに応じた選択肢を提示すると効果的です。
HPは検索エンジン経由での流入を見込むため、SEO(検索エンジン最適化)対策が欠かせません。コンテンツの質や内部リンク構造、キーワードの適切な配置、スマホ対応など、継続的な施策が必要です。特に「会社名+サービス名」など指名検索に対応するコンテンツ設計は信頼獲得にもつながります。
一方、LPは広告運用と組み合わせて初めて効果を発揮するケースが多く、Google広告やSNS広告などからの「誘導→即コンバージョン」を狙う設計が求められます。広告にマッチしたコピーやデザイン、広告で与えた期待を裏切らない内容、スクロールせずに目的を達成できる簡潔な構成がカギとなります。
つまり、HPは中長期でじっくり集客し、LPは短期で反応を得るという性格を持つため、それぞれに適した集客戦略を設計することが重要です。
近年では、「LPだけでは信頼が足りない」「HPだけでは行動喚起が弱い」という課題を補完するために、LPとHPを連携させるケースが増えています。
たとえばLPでサービスを知ってもらい、「この会社ってどんなところ?」と興味を持ったユーザーを、HPの「会社情報」や「代表メッセージ」へと誘導する。このとき、自然なリンク導線を設けておくことで、ユーザーに安心感を与え、結果的にCVRの底上げにつながります。
逆に、HP内でサービス紹介ページやブログ記事を閲覧しているユーザーに対して、「詳しくはこちら」とLPへ誘導する動線を作ることで、ニーズが高まったタイミングを逃さず成果につなげられます。
このように、LPとHPを単体で考えるのではなく、役割分担を意識しながら設計・運用することで、Web全体の成果を最大化する戦略が実現できます。
自社サイトを持つべきか迷っている方におすすめの記事です。企業ホームページが果たす役割や得られる効果、持たないことによるリスクをわかりやすく解説しています。Web施策の第一歩として、ぜひご覧ください。
検索エンジンでの上位表示を目指すなら必読の一記事。最新のSEO対策の基本から実践方法まで、初心者でも理解しやすい構成で解説されています。LPやHPの効果を最大化するための知識としても役立ちます。
https://ardem.co.jp/archives/blog/%e3%80%902025%e5%b9%b4%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%89%88%e3%80%91seo%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ae%e3%82%84%e3%82%8a%e6%96%b9%e5%ae%8c%e5%85%a8%e7%89%88%ef%bc%81%e5%88%9d%e5%bf%83%e8%80%85%e5%90%91%e3%81%91
LP(ランディングページ)とHP(ホームページ)は、目的・構成・活用方法のすべてにおいて役割が異なります。LPは「一点集中」で成果を出すことに長け、HPは「会社全体の信頼構築や情報発信」を担います。
大切なのはどちらを選ぶかではなく、目的に応じて適切に使い分けること。そして、両者を連携させることで、相乗効果による成果向上も狙えます。Web戦略における「入口」と「全体像」を明確にするためにも、自社の課題に合った設計を進めましょう。
成果につながるWeb制作を一緒に考えませんか?
「問い合わせが増えない」「サイトから成果が出ない」そんなお悩みをお持ちなら、まずはARDEMにご相談を。課題整理から設計・運用まで、伴走型でサポートいたします。
▶ Webサイト制作のご相談はこちら
SEOは「一度やって終わり」ではなく、「継続的に育てていくもの」です。地道な努力を積み重ねることこそが、検索上位の安定した成果につながります。
もし、自社での対応に限界を感じている場合は、SEOに強いホームページ制作業者や専門のパートナーと組むことで、より確実な成果が期待できます。適切な戦略と実行力をもって、持続的な検索順位の向上を目指しましょう。
SEOに強いホームページをご提案します。
お問い合わせはお気軽にどうぞ。
▶ お問い合わせ
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。