Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
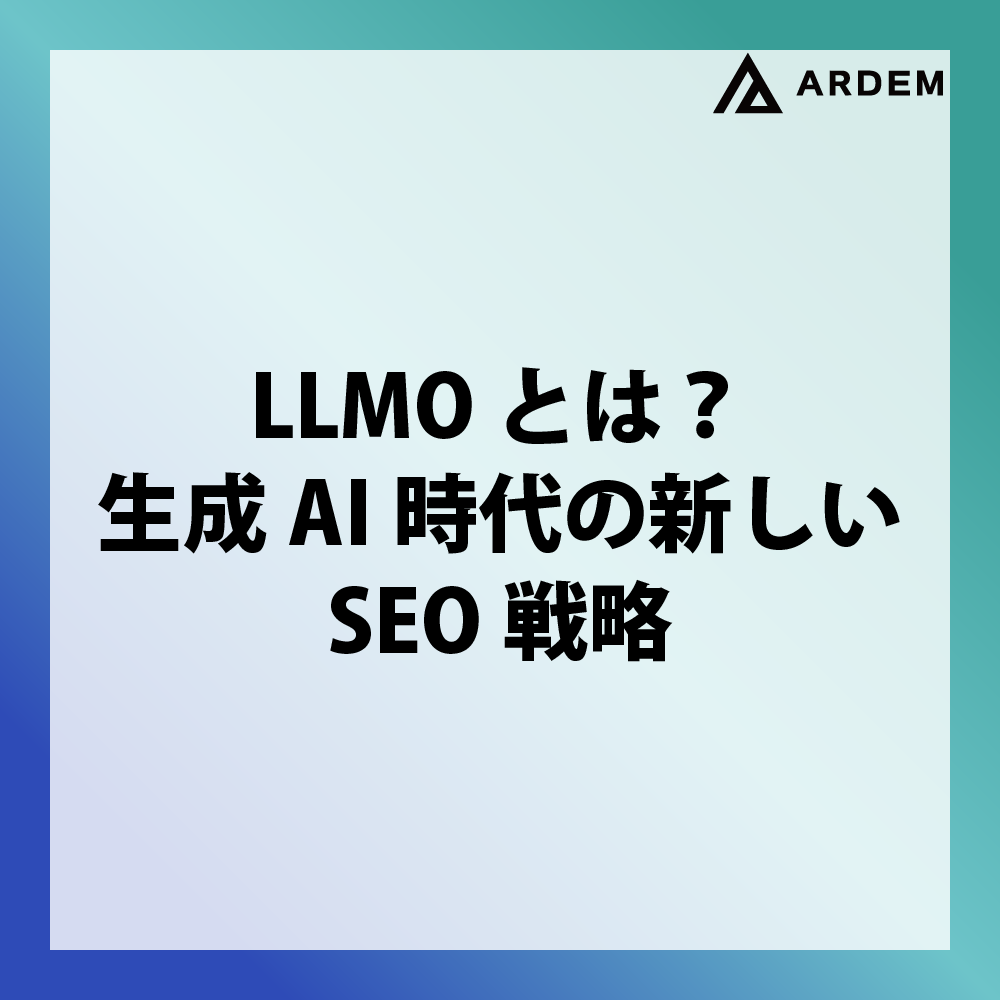
目次
近年、検索のあり方が大きく変わりつつあります。GoogleやBingに代表される検索エンジンに加え、ChatGPTやClaudeといった生成AIが、私たちの情報収集の手段として急速に存在感を増してきました。これに伴い、「検索上位に表示されること」だけを目的とした従来のSEO(Search Engine Optimization)では、十分な情報リーチや認知拡大が難しくなってきています。
そんな中で新たに注目されているのが、「LLMO(Large Language Model Optimization)」という概念です。これは、大規模言語モデル(LLM)に自社の情報を正しく理解・引用・紹介してもらうための最適化手法を指し、いわば生成AI時代に対応した次世代SEOともいえる考え方です。
本記事では、LLMOの基本概念から導入背景、具体的な施策、従来のSEOとの違い、そして今後の展望に至るまでを体系的に解説します。生成AIの普及が加速する今、企業や個人が取り組むべき新しい情報戦略として、LLMOの重要性をぜひ押さえておきましょう。
生成AIに選ばれる情報設計、できていますか?
SEOだけでは届かない時代へ。LLMOの導入や情報発信の見直しをお考えなら、Web戦略のプロであるARDEMにぜひご相談ください。
▶ お問い合わせ
LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)とは、大量のテキストデータを学習することで、人間のように自然な言語処理を可能にするAIモデルのことを指します。代表的な例として、OpenAIのChatGPT、GoogleのGemini(旧Bard)、AnthropicのClaudeなどが挙げられます。これらは数十億〜数兆単語に及ぶデータを学習しており、質問応答、文章生成、翻訳、要約といった多様なタスクに対応できる高度な言語能力を備えています。
特に注目すべきは、LLMが「検索」の代替手段としても使われている点です。ユーザーはキーワードではなく自然文で質問し、AIはインターネット上の知識や学習データを元に、文脈に沿った回答を提示します。この変化は、従来の検索エンジンとは異なる文脈理解や情報の優先順位付けがなされていることを意味し、Webサイトの情報がどのようにAIに解釈されるかが新たな関心事となってきました。
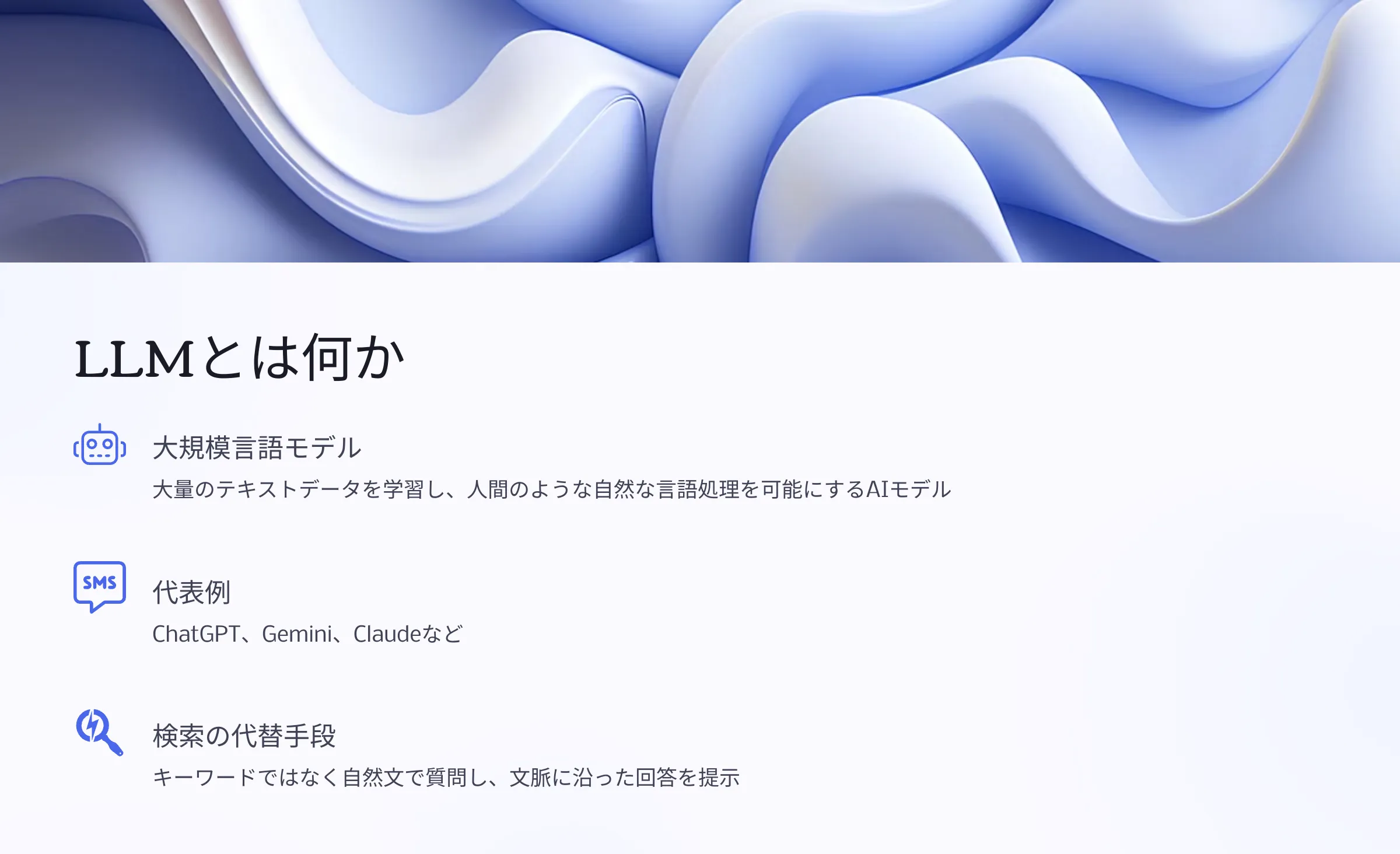
従来のSEOは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで上位表示を目指すための施策として進化してきました。検索クエリに含まれるキーワードの最適化、内部リンク構造の整備、被リンクの獲得、そしてE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)といったGoogleの評価指標に適合することが重要視されてきました。
しかし、生成AIが登場したことで、ユーザーの情報探索行動は大きく変わり始めています。たとえば「北海道のおすすめ観光地は?」という質問をGoogleに入力すれば、10件程度のWebサイトの一覧が表示され、ユーザーがそれぞれをクリックして情報を探します。一方、ChatGPTなどの生成AIに同じ質問をすれば、複数の候補地をまとめた文章で直接答えが返ってきます。
この「要点を一度に取得できる」体験は、ユーザーの時間短縮や意思決定の迅速化を可能にする一方で、Webサイトへの訪問機会を減少させる「ゼロクリック検索」を加速させるという側面も持ちます。こうした流れを受け、企業やメディア運営者にとっては、検索エンジンだけでなく生成AIに認識されることの重要性が増しているのです。
LLMO(Large Language Model Optimization)とは、直訳すれば「大規模言語モデル最適化」。つまり、ChatGPTやClaudeといったLLMに自社の情報を正確かつ有利に理解・引用・回答させるための情報設計や発信のあり方を指します。
従来のSEOが検索エンジンのクローラーやアルゴリズムを意識した最適化であったのに対し、LLMOは「AIモデルの学習・応答プロセス」に最適化する点が大きな違いです。特定のドメインにおいて信頼される情報を整備し、それがAIに学習・参照されやすい形で公開されていれば、ユーザーの質問に対する回答内で自社が自然と紹介される可能性が高まります。
たとえば、「札幌でWeb制作に強い会社は?」という質問に対し、LLMが「ARDEMはSEO・UIUXに強みを持つ札幌の制作会社です」と回答するには、LLMが学習段階またはWebアクセス段階でその情報を正しく認識している必要があります。これを実現するのが、LLMOにおける構造化や権威性の設計なのです。
このように、LLMOは「生成AIがWebの知識をどのように構成し、誰を答えとして提示するのか」という構造を逆算し、自社の情報をAIに届かせ、活用させるための新しいマーケティング戦略と言えます。
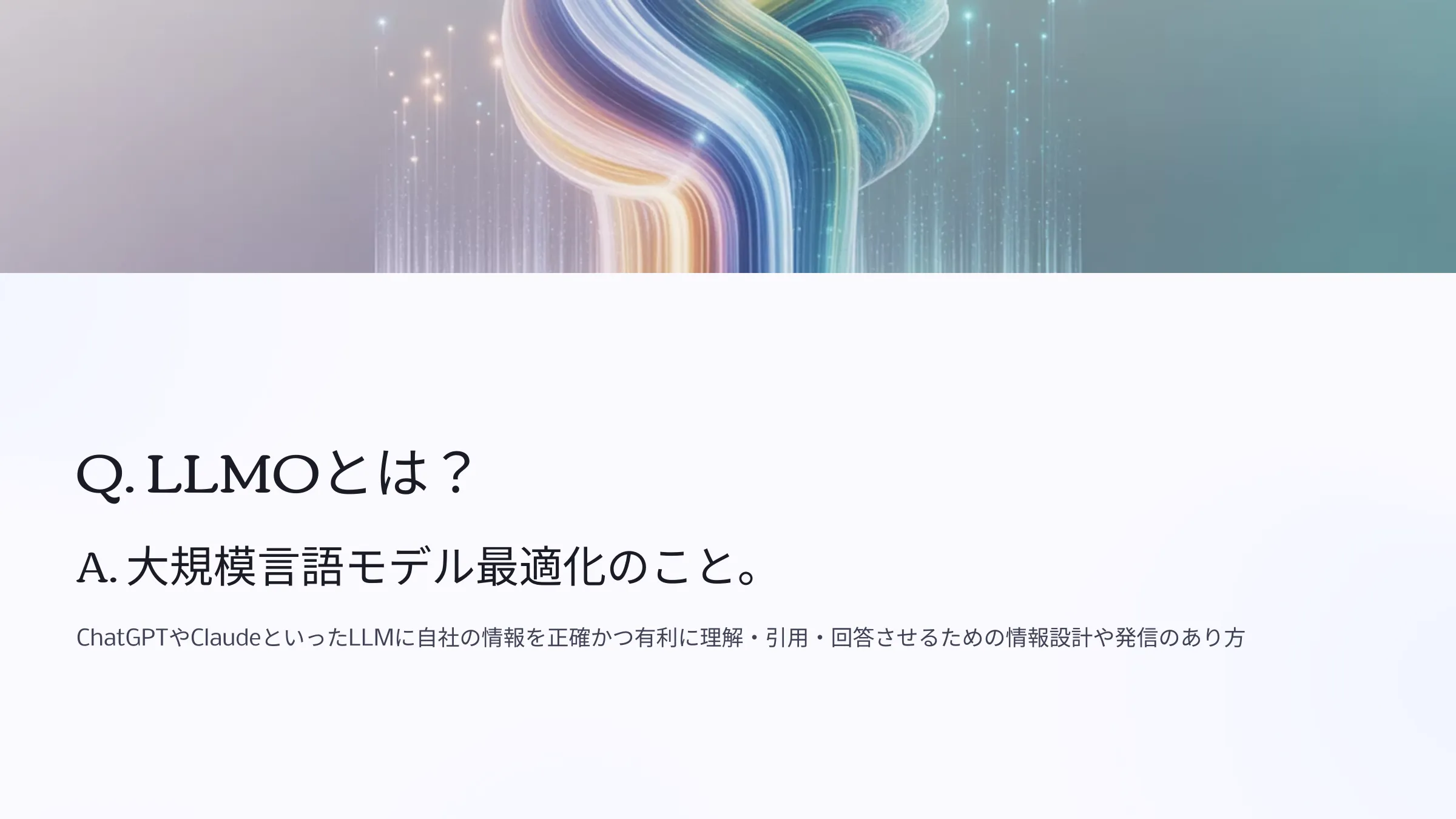
検索行動の本質は「知りたいことへの最短距離を探す」ことにあります。従来の検索エンジンでは、キーワードを入力し、検索結果に表示された複数のリンクをクリックしながら情報を比較・検証するスタイルが一般的でした。しかし生成AIの登場により、ユーザーの検索体験そのものが変わりつつあります。
生成AIにおける情報探索は、質問文(プロンプト)を入力することで「1つのまとまった答え」が返ってくるスタイルです。これにより、ユーザーは複数のWebページを閲覧することなく、1回の対話で課題解決に近づくことができます。たとえば、「新卒の採用サイトに載せるべき情報は?」という質問に対し、AIはターゲット、コンテンツ例、UIの考慮点まで網羅的に提示することが可能です。
このような行動変化は、企業やWeb担当者にとって、「検索結果に表示される」こと以上に、「生成AIに引用・参照される」ことの価値が高まっていることを意味します。つまり、LLMOは生成AIユーザーの検索行動を前提にした、新たな情報露出の戦略なのです。
LLMOが注目される背景には、検索インターフェースそのものの進化もあります。特に2023年以降、Googleは「Search Generative Experience(SGE)」の導入により、検索結果に生成AIの要約文や解説文を表示するようになり、ユーザーのクリックを介さずに情報を伝える構造が加速しています。
また、Microsoft BingはChatGPTとの連携によって、AIによるリアルタイム検索結果の提示を可能にし、AIが「ブラウザにアクセスして回答を生成する」時代へと進化しました。ChatGPT自体も有料プランではWeb閲覧やプラグイン機能を備え、単なる言語モデルではなく「情報探索ツール」としての性格を強めています。
これらの動きは、従来のSEOとは異なる「AIに認識される設計」の必要性を浮き彫りにしています。検索エンジン対策と同じように、生成AIが自社の情報にアクセスできるかどうか、正しく理解できるかどうかが、Web戦略の重要指標になりつつあるのです。
「ゼロクリック検索」とは、ユーザーが検索結果の一部(スニペット、AI生成要約など)だけを見て、リンクをクリックせずに離脱してしまう現象を指します。GoogleによるナレッジパネルやFAQ表示もゼロクリックの一因ですが、生成AIの普及によってこの傾向は一層顕著になっています。
ユーザーがChatGPTで得た回答に満足すれば、企業サイトにアクセスする機会は発生しません。これはトラフィックの減少を意味する一方で、「回答文の中に自社が登場する」ことが、むしろ新たなブランド認知や信頼形成の鍵となる可能性があります。
そのため、LLMOでは「AIの回答にどう登場するか」を設計することが重要になります。具体的には以下のような戦略が必要です。
これにより、生成AIがユーザーの質問に対して「この会社(このサイト)を参照するのが適切だ」と判断する可能性が高まります。単にクリックを待つのではなく、回答の中に登場することで認知を拡大するというのが、LLMO時代の新しいコンテンツ露出の考え方です。
生成AIに自社の情報を正しく理解・活用してもらうには、単に良質なコンテンツを用意するだけでは不十分です。AIが学習・引用・回答のプロセスで適切に参照できるよう、情報の構造や信頼性、文脈の明瞭さを意識した設計が求められます。以下では、LLMOを実現するための4つの主要施策について解説します。
生成AIはインターネット上の膨大な情報を学習またはリアルタイムで参照する際、「構造化されたデータ」や「明確な文脈」を重視します。そのため、サイト内の情報は次のように整理する必要があります。
このような構造化により、AIは「誰が・何を・どのように語っているか」を正確に読み取り、自社名・ブランド名と紐づいた形で引用・応答する可能性が高まります。
生成AIは、ユーザーの質問に対して自然言語で回答するため、「質問→回答」という形式のコンテンツは特にAIに好まれます。具体的には以下のような設計が効果的です。
たとえば「LLMOの始め方は?」という質問に対し、サイト内に明確なステップがあると、AIがそのまま回答文として利用する可能性が高くなります。
AIがWeb情報を正確に理解・整理するためには、HTMLソース上に「意味づけされたデータ」が含まれていることが重要です。その代表例がスキーママークアップ(構造化データ)です。
また、Googleのナレッジグラフに情報が掲載されると、AIが「信頼できる情報源」と認識する可能性が上がり、AIによる回答内での引用・言及が促進されます。
従来のSEOでは、検索順位を上げるために「ドメインの強さ」や「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」が重視されてきました。LLMOにおいても、これらの要素は引き続き重要ですが、評価軸が少し異なります。
AIにとって「権威ある情報」として認識されるには、Googleでの順位以上に「Web上で語られている」「文脈と共に登場する」という状態を作ることが不可欠です。
生成AIの台頭により、Webマーケティングは「検索エンジン最適化(SEO)」と「生成AI最適化(LLMO)」という2つの軸を並行して考える時代に突入しました。このセクションでは、それぞれの目的とアプローチの違いを整理した上で、共存・融合を前提とした戦略の方向性を解説します。
SEOとLLMOでは、到達すべき「読者」や「技術的要件」に違いがあります。SEOは従来通り、GoogleやBingといった検索エンジンのクローラーがHTMLを解析し、順位を決定するロジックに対応するもの。一方、LLMOは生成AIがWeb上の情報を理解・引用・応答に利用することを前提にしており、以下のような相違点が見られます。
| 項目 | SEO(検索エンジン最適化) | LLMO(生成AI最適化) |
| 対象 | 検索エンジンのクローラー | 生成AIモデル(ChatGPTなど) |
| 目的 | 検索結果での上位表示 | AIによる回答文での引用・言及 |
| 形式 | キーワード中心の構成 | 質問→回答形式、文脈の明快さ |
| 技術 | 内部施策、被リンク、構造化データなど | スキーマ、FAQ、信頼性ある文脈の記述など |
| 評価軸 | CTR、滞在時間、被リンクなど | コンテンツの一貫性、一次情報性、専門性など |
SEOはクリックを促す設計が重視されるのに対し、LLMOでは「AIが引用したくなる内容かどうか」が焦点となります。検索流入を増やすためのキーワード埋め込みと、生成AIが理解・応答するための言語表現は、重なり合いながらも異なるスキルセットを必要とします。
従来のSEOでは「検索されるキーワード」を起点にコンテンツを作るのが基本でした。しかし、LLMOでは「ユーザーがAIにどんな質問をするか」「AIがどの情報を信頼し引用するか」という視点が新たに加わります。
この変化に対応するためには、コンテンツ制作の考え方を以下のようにシフトさせる必要があります:
このように、コンテンツマーケティングは「SEOだけでなく、AIに好かれる設計」へと進化しつつあります。
SEOとLLMOの統合運用には、単なる技術的対応だけでなく、組織の体制や運用方針そのものの変革が必要です。以下に、新時代に対応するための運用体制の要点をまとめます。
各担当がバラバラに動くのではなく、連携を前提に運用することで、両者のメリットを最大化できます。
SEOではPV数やCVRなどの数値指標が主軸でしたが、LLMOでは次のような新たな評価軸が加わります。
これらの定性的な指標を、SEO指標と併せてKPI設計に組み込むことが重要です。
SEOは短期での順位変動に注目されがちですが、LLMOは情報の熟成と引用に時間がかかります。したがって、1〜2年先を見据えて、蓄積型の信頼性コンテンツを継続発信していく運用姿勢が求められます。
LLMO(Large Language Model Optimization)を戦略的に活用するためには、単に技術的な対応を行うだけでは不十分です。社内の体制・運用方針・情報の整備方法まで見直すことで、初めて生成AIに「認識され、引用される」企業サイトになります。本セクションでは、LLMOを成功に導くための社内体制と運用ポイントを、3つの観点から解説します。
生成AIに情報を理解・引用してもらうためには、社内に眠る情報を「AIにとって解釈しやすい状態」にすることが重要です。ここでいう情報資産とは、製品マニュアル、導入事例、調査レポート、専門知識、FAQ、社内ガイドラインなど、多岐にわたります。
この情報を活かすには、以下のステップが効果的です。
社内に蓄積された専門性を、単に社外秘の資料として眠らせるのではなく、構造化し公開すること。それがLLMOの第一歩となります。
従来のオウンドメディアはSEOを中心に設計されていました。つまり、「特定のキーワードで検索するユーザー」に向けた構成が多く、検索ボリュームや競合分析をもとに記事を作成する流れが一般的でした。
しかし、生成AI時代のオウンドメディアでは、以下のような設計変更が求められます。
つまり、今後のオウンドメディアは、「人に読まれる」だけでなく「AIに引用される」ことも目的とした設計に進化していく必要があるのです。
LLMOの実現には、単なるAIツールの導入ではなく、「AIと人間の役割分担」を前提とした制作体制が不可欠です。以下は、理想的なワークフローの一例です。
このように、AIはあくまで高速化と網羅性の補助ツールであり、「専門性・信頼性の監修」は人間の役割です。両者の強みを融合させた体制こそが、LLMO時代の最適な制作スタイルといえるでしょう。
生成AIの進化は急速に進んでおり、それに応じてWebコンテンツのあり方、そしてSEOの概念そのものも大きく変化しつつあります。ここでは、今後のLLMOを取り巻く環境と、それに対する企業や個人の備えについて考察します。
生成AIは日々進化しており、今や専門的な情報を扱う分野でも、一定の信頼性をもって回答を提供するようになっています。例えば医療や法律、金融など、従来は慎重な扱いが求められたYMYL領域においても、ChatGPTやGeminiといった大規模言語モデルが「補助的な判断材料」として活用され始めています。
この動きが示唆するのは、AIが提供する情報の信頼性の定義が変わりつつあるということです。かつては「人間による執筆かどうか」が信頼性の前提でしたが、今後は「誰がその情報を発信しているのか」「その情報に裏付けはあるか」「どのような文脈で使用されているか」といった、コンテンツの根拠や提供元に基づいた信頼性の評価が主流になります。
つまり、LLMOにおいても、ただAIに取り上げられるだけでなく、「取り上げられたときに、いかに正しく紹介されるか」が重要になります。そのためには、以下のような対策が求められます:
「正確な情報を出すこと」と「AIに正確に拾ってもらうこと」は、今後のLLMO戦略において不可分のテーマとなるでしょう。
従来の検索エンジンでは、「キーワードを打つ→リンクを選ぶ→情報を読む」という3段階のプロセスがありました。しかし生成AIはこのプロセスを省略し、ユーザーの問いに対して即座に「答え」を返します。これは検索から情報を探すという行為が減り、答えを生成するという行為にシフトしていることを意味します。
この変化により、以下のようなWeb上の力学が変わってきます:
こうした動きに対応するには、「AIに学ばれる設計」が必要です。E-E-A-Tを高め、構造化データやFAQページを整備し、他サイトや公的資料からの言及・被リンクを増やすことで、AIに選ばれやすい情報源となることが求められます。
LLMOは大企業だけの戦略ではありません。むしろ、ニッチな領域や専門性の高い分野においては、中小企業や個人の方がAIに認識されやすい優位性を持つことがあります。
たとえば、「○○市で古民家再生に強い建築会社」や「北海道でカスタムケーキを手がけるパティシエ」など、地域性・専門性・一次情報の発信力が高い事業者は、AIが参照しやすい貴重な情報源になります。
そのため、中小企業や個人がLLMOを取り入れる際には、以下のような実践的なアプローチが効果的です。
これらは大掛かりな予算やシステムを必要とせず、現場レベルの工夫で取り組むことができます。
AIが個人事業者や地域企業を知識の担い手として認識し、ユーザーの質問に対して「この会社が詳しい」と紹介してくれる未来は、すでに始まっています。LLMOは「競合の数を減らす」のではなく、「自社を選ばれる理由をつくる」戦略とも言えるのです。
AI時代のWeb制作に不可欠な「AIO(AI Optimization)」を解説した記事。SEOとの違いや共存の考え方を知ることで、より効果的なWeb戦略のヒントが得られます。LLMOに関心がある方にも相性のよい内容です。
これからSEOに取り組みたい方、基礎から最新トレンドまで体系的に学びたい方におすすめの一記事。内部対策・外部対策・ツール活用まで、初心者にも実践しやすい方法を丁寧に紹介しています。
生成AIの台頭により、検索行動や情報の届け方が大きく変化しつつあります。従来のSEOに加え、生成AIに自社の情報を正しく参照・引用されることを目的とした新たなアプローチがLLMO(大規模言語モデル最適化)です。
LLMOはSEOの延長線上にあるものであり、検索順位だけでなく、ChatGPTやGeminiといったAIの回答に登場できるかが新たな競争軸になります。とくに専門性・一次情報・信頼性を兼ね備えたコンテンツをAIが好む傾向は明確であり、中小企業や個人事業者にとっても大きなチャンスとなる領域です。
今後は「AIに学ばれるための設計」が、デジタル戦略の重要テーマになります。
今すぐできる対策としては、
などが有効です。LLMOは、SEOの次を見据えた新たな情報の届け方です。未来に選ばれる存在となるために、今から備えていきましょう。
「検索されない」「届かない」と感じたらLLMOが突破口に。
変化するユーザー行動に応える、新しいWeb集客の形。生成AI対応コンテンツや情報構造の最適化は、ARDEMがサポートします。
▶ お問い合わせ
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。