Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
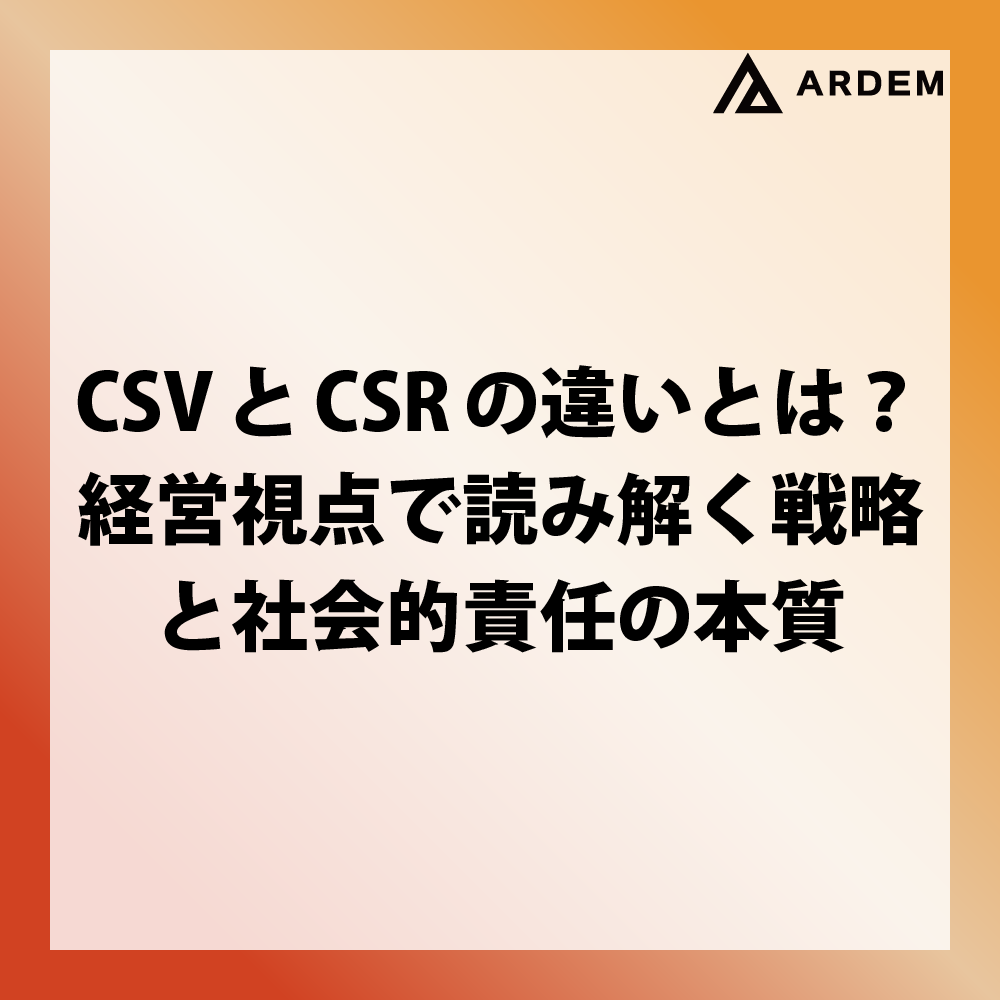
目次
企業経営において「CSR(企業の社会的責任)」という言葉はすでに広く知られていますが、近年では「CSV(共有価値の創造)」という新たな概念も注目されています。どちらも企業が社会とどう関わるかを示すキーワードですが、その目的やアプローチは大きく異なります。
CSRは「責任」としての社会貢献、CSVは「戦略」としての社会価値創造という違いがあり、それぞれが企業活動に与える影響も変わってきます。この記事では、CSRとCSVの定義や考え方の違いをわかりやすく整理しながら、これからの時代にふさわしい企業の在り方を探ります。
自社の理念や価値を可視化しませんか?
ARDEMでは、CSVやCSRを意識したコーポレートサイトの制作やブランド戦略設計を支援しています。
▶ [企業ブランディングのご相談はこちら]
CSVとは、「共通価値の創造(Creating Shared Value)」の略で、経営学者マイケル・ポーターとマーク・クラマーによって提唱された概念です。企業が経済的価値(利益)を生み出す過程で、同時に社会的価値(地域社会や環境への貢献)を創出することを目的としています。単なる社会貢献ではなく、本業と社会課題の解決を一体化させるのがCSVの大きな特徴です。
たとえば、健康食品を提供する企業が、健康寿命の延伸という社会課題に取り組むことは、顧客の満足度向上と企業収益の両立につながります。このように、CSVは事業活動の中に社会的価値を埋め込み、持続的な成長を実現しようとする経営戦略です。
一方、CSRは「企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility)」を指し、企業が社会の一員として果たすべき義務や役割を明確にした考え方です。法令遵守(コンプライアンス)、環境保護、地域貢献、労働環境の整備など、本業とは直接関係がない活動も含まれる点が特徴です。
CSRの原点には、「企業は利益だけを追求してよいのか?」という社会からの問いかけがあります。とくに大企業を中心に、企業イメージの向上や社会からの信頼構築のためにCSR活動が行われてきました。寄付活動やボランティア支援、環境保護プロジェクトなどが代表的です。
CSVとCSRは、いずれも企業と社会の関わり方を考えるうえで重要な概念ですが、根本的なアプローチが異なります。
CSRはコストとして捉えられることが多いのに対し、CSVは投資と見なされることが多く、事業戦略に組み込まれやすいという違いもあります。この違いを理解しておくことで、自社にとって最適な社会的取り組みの形を見極める手助けになります。
CSR(企業の社会的責任)では、企業が利益を追求する一方で、倫理的・社会的な責任を果たすことが求められます。このアプローチでは、社会貢献活動は本業とは切り離され、時には企業収益を圧迫する「コスト」として扱われることもあります。例えば、環境保護のための寄付や従業員のボランティア活動の推進などが該当します。
一方、CSV(共通価値の創造)は、社会課題の解決そのものをビジネス機会と捉え、経済的利益と社会的貢献を同時に実現するという発想です。たとえば、発展途上国の農家に技術支援を行いながら原料を安定的に仕入れることで、現地の生活水準を向上させつつ自社の供給網も強化するというような取り組みが代表例です。
このように、CSRは「責任感」から発想されるのに対し、CSVは「競争戦略」として設計されるという点に大きな違いがあります。

CSR活動は、短期的な企業価値の向上には直接つながらないケースが多いものの、中長期的には企業イメージやブランド力の向上に貢献します。また、ステークホルダーとの関係強化や、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点からの評価にもつながるため、企業の持続的成長を支える基盤づくりとして重要です。
一方、CSVは企業の競争力や収益性を直接的に押し上げることが期待されます。社会課題に対して本業のリソースや強みを活かすことで、これまでにない市場や顧客ニーズを開拓し、成長の新たなエンジンとして機能するのがCSVの魅力です。たとえば、エネルギー効率の高い製品を開発することで、環境問題への貢献と新たな収益源の獲得を両立できます。
このように、CSRは「信頼の蓄積」、CSVは「成長の戦略」という役割で企業価値に貢献します。
実務レベルでも、CSRとCSVはその取り組み方に違いが見られます。CSRでは、社外広報・総務・人事などが中心となって、社会貢献イベントや地域活動を計画・実行することが多く、社内で独立した活動として運営される傾向があります。
対してCSVは、経営戦略や事業開発に深く組み込まれ、マーケティング部門やプロダクト開発チームが主導するケースが多いのが特徴です。社会課題に向き合うこと自体が商品開発や新規事業につながるため、各部門の横断的な連携も求められます。
そのため、CSRは「組織の一部による社会的責任」、CSVは「全社的に取り組む社会価値創造」として位置づけられることが多いのです。
CSVの代表例としてよく挙げられるのが、ネスレの「ネスプレッソ」プロジェクトです。ネスレは、エチオピアやコロンビアなどの発展途上国で高品質なコーヒー豆を安定的に調達するため、生産者に対して農業技術や品質管理の教育を実施しています。この取り組みにより、現地農家の生産性と収入を向上させるとともに、ネスレ自身もプレミアムなコーヒー商品を安定供給できるようになりました。社会課題(貧困や農業技術の未発達)を解決しながら、自社の競争力を高めている好例です。
また、ユニリーバは「サステナブル・リビング・プラン」と題して、環境負荷を軽減しながら事業を成長させるというCSV戦略を掲げています。たとえば、同社の洗剤製品では水の使用量を減らせる処方を開発し、節水を促進すると同時に消費者の利便性を高めました。このように、ユニリーバは持続可能性を起点にした商品開発を通じて、環境問題の解決と売上拡大の両立を目指しています。
CSVは単なる社会貢献ではなく、「社会の課題を解決することが、企業のビジネスチャンスになる」という観点から実行されるのが特徴です。ネスレやユニリーバのように、経営戦略と一体化された形で取り組まれている点に注目すべきでしょう。
一方、CSRの代表的な取り組みとしては、日本企業による災害支援や環境保護活動が多く見られます。たとえばトヨタ自動車は、東日本大震災の際にいち早く義援金を提供し、被災地での移動支援や物資提供を行いました。これらは直接的な収益にはつながらないものの、企業としての社会的責任を果たす姿勢が広く評価され、ブランドの信頼性向上にも寄与しました。
また、花王株式会社は長年にわたり「環境への配慮」をCSRの柱として掲げており、省エネ活動や再生可能資源の使用、環境教育プログラムなどを積極的に展開しています。これらは短期的な収益貢献よりも、企業としての持続可能性や社会的評価を高めることに重点を置いた取り組みといえます。
CSRはあくまで「社会的責任」に基づいた活動であり、収益と連動しないケースが多く見られます。ただし、こうした活動が結果的に企業の評判を高め、優秀な人材の獲得やESG投資家からの評価につながるという側面も無視できません。
このように、CSVはビジネス成長と課題解決の同時実現、CSRは信頼性や社会的信用の蓄積という方向性で、それぞれ企業活動に大きな意味を持っています。
現代の企業経営において、単に短期的な利益を追求するだけでは持続的な成長は望めません。そこで注目されているのが、CSV(共通価値の創造)やCSR(企業の社会的責任)といった取り組みを、経営戦略に統合するという考え方です。
たとえばCSVのように、社会課題の解決と収益を同時に生み出すビジネスモデルは、持続可能な競争優位を築くうえで有効です。これは、企業が社会とともに成長する構造をつくることを意味しており、市場や事業の拡張性にも直結します。
一方でCSRは、法令順守や倫理的行動といった土台を企業に根づかせる役割を担います。社会的信頼の蓄積が企業ブランドを強化し、ステークホルダーとの関係を安定化させることに貢献します。つまり、CSVが「攻め」の施策とすれば、CSRは「守り」の戦略として重要なのです。
CSVやCSRの活動は、外部へのアピールだけでなく、社内外のステークホルダーとの信頼関係構築にもつながります。
たとえば、従業員は企業が社会課題に真剣に取り組む姿勢に共感しやすく、モチベーションの向上や離職率の低下といった効果が期待できます。実際に、社会的使命を持った企業で働くことに誇りを感じる若年層は年々増加しています。
株主や投資家にとっても、持続可能なビジョンを掲げる企業はリスクが低く、安定的な成長が見込める投資対象と見なされる傾向にあります。CSR報告書の提出やESG開示などを通じて、透明性の高い経営を行うことが信頼につながるのです。
また地域社会との関係でも、CSR活動によって企業が地域に根ざした存在であることが伝われば、住民や行政との協力体制が築きやすくなります。結果として、災害対応や新規事業の立ち上げ時などにおける社会的支持が得られやすくなるのです。
近年は、SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)といった国際的な指標への対応も、企業にとって無視できない要素となっています。
CSVは「ビジネスで社会課題を解決する」という観点から、SDGsの達成と非常に親和性が高い戦略です。たとえば「すべての人に健康と福祉を(Goal 3)」や「働きがいも経済成長も(Goal 8)」といった目標を、製品やサービスを通じて実現することができます。
一方CSRは、ESG評価において「S(社会)」や「G(ガバナンス)」の領域での基盤づくりを担います。たとえば労働環境の整備やコンプライアンス体制の強化などは、CSRの範疇であり、企業の評価にも直接影響します。
CSVとCSRを適切にバランスよく取り入れることで、企業はSDGsとESGという二つの世界的潮流にも対応できるようになります。今後の企業評価において、こうした社会的価値の創出がますます重視される中、両者を経営戦略にどう組み込むかが、持続的な成長の鍵となるでしょう。
CSVやCSRというと、大企業だけの取り組みのように思われがちですが、実は中小企業にとっても十分に実践可能です。むしろ、地域や業界との結びつきが強い中小企業こそ、独自の視点で社会的価値を創出できる余地があります。
たとえば、地元の障がい者支援施設と提携して軽作業の一部を委託したり、余剰食材を地域の子ども食堂へ寄付するなど、規模は小さくても社会課題の解決につながる取り組みは多数あります。これらはコスト負担が比較的少なく、かつ地域との関係強化や企業イメージ向上にもつながります。
中小企業がCSVに取り組む際は、「自社の事業を通じて、どんな社会的価値を提供できるか」という問いを出発点とすることが重要です。事業活動そのものが社会課題の解決に貢献できていれば、それは立派なCSVの実践といえます。
CSRを中小企業が実践する場合、大企業のように大規模な社会貢献活動を行う必要はありません。むしろ、日々の業務とCSRを自然に結びつけることで、無理なく継続できる仕組みをつくることが大切です。
たとえば、社員の健康促進のために社内でウォーキングキャンペーンを実施したり、紙資源削減のためのペーパーレス化を進めたりといった取り組みも立派なCSRです。また、地域の清掃活動や、災害時の備蓄物資の提供体制を整備することなども、身近なCSR活動として実践可能です。
CSRは「企業として当然果たすべき責任」として外部から評価される要素でもありますが、社員が働きやすく、誇りを持てる職場づくりにも直結します。無理に立派なことをしようとするのではなく、自社の業務や風土に合ったかたちでの取り組みが長続きの鍵です。
中小企業のCSV・CSR活動を社外に伝える手段として、ホームページやSNSの活用は非常に有効です。活動内容を可視化することで、顧客や取引先、求職者に対して「この会社は社会的責任を果たしている」という安心感を提供できます。
特に中小企業は、規模やブランドの知名度で大手企業に劣ることが多いため、理念や姿勢を発信する場としてのWebサイトは強力なツールとなります。事例紹介、社員の声、地域とのつながりなどを写真やインタビュー形式で掲載することで、等身大の魅力が伝わりやすくなります。
また、SNSを通じたリアルタイムの情報発信は、企業の透明性や親しみやすさを高める効果があります。CSR活動の様子を投稿すれば、社内外からの反響や応援コメントを受け取ることができ、社員のモチベーション向上にもつながります。
重要なのは、単なる広報ではなく「なぜその取り組みを行っているのか」「どんな想いがあるのか」まで伝えることです。中小企業の取り組みであっても、真摯な発信はステークホルダーの信頼を確実に育てていきます。

CSV(Creating Shared Value)とCSR(Corporate Social Responsibility)は、どちらも企業が社会との関わりを持ち、責任ある存在として価値を生み出していく上で重要な考え方です。しかし、今後の企業活動においては、単なる責任の履行にとどまらず、「価値の共創」という視点を持つCSV的なアプローチが、より一層求められていく傾向にあります。
CSRが「守り」の姿勢、つまり既存の社会的責任への対応を重視するのに対し、CSVは「攻め」の姿勢で、事業と社会貢献を両立させながら成長戦略に組み込む発想です。例えば、環境負荷の低い製品開発や、途上国市場への事業展開によって雇用と生活水準の向上を生み出すような事例が挙げられます。
もちろん、CSRが不要になるわけではありません。労働環境や法令順守、倫理的行動など、企業としての土台を固める上でCSRの役割は引き続き重要です。両者は対立するものではなく、段階的・補完的に活用することが、これからの企業経営にとって現実的な選択といえるでしょう。
現代の消費者や求職者は、価格や知名度だけで企業を選ぶ時代ではなくなりました。企業がどんな価値観を持ち、どのような社会的スタンスを取っているかを重視する「共感型の選択」が浸透しつつあります。
その背景には、SDGsやESG投資の普及、情報透明性の高まり、SNSによる企業活動の可視化などが挙げられます。企業に対しても、単に利益を追求するのではなく、「何のために存在するのか」「誰の役に立つのか」といった存在意義(パーパス)への問いが強まっています。
このような時代には、CSRのような受動的な社会貢献だけでは期待に応えきれません。社会課題を自らのビジネスチャンスとしてとらえ、解決に取り組むCSV的発想こそが、企業の信頼と選ばれる理由につながっていくのです。
とはいえ、CSVやCSRの取り組みに正解はありません。大切なのは、「自社らしさ」を軸にした価値の創造です。業種や規模、地域、企業文化によって実現できる社会貢献の形は異なります。
たとえば、食品メーカーであれば地産地消の推進、小売業であれば障がい者雇用やエコパッケージの導入、建設業であれば災害復旧支援や職人の技術継承といった具合に、自社が本業で関われるテーマを見つけ出すことが鍵です。
そのためには、トップダウンで理念を明確にするとともに、現場の声を吸い上げて社員が主体的に関わる仕組みづくりが必要です。また、その価値を社外にも正しく伝えるためには、WebサイトやSNSといった情報発信の場を活用し、自社の取り組みや姿勢を発信し続ける努力も欠かせません。
最終的には、社会からの共感と信頼が積み重なり、企業のブランド力や人材確保、事業拡大といった具体的な成果に結びついていきます。時代の変化に応じて、CSRとCSVを賢く組み合わせ、自社ならではの「持続可能な価値」を築いていくことが、これからの企業に求められる選択なのです。
CSRやCSVといった企業活動の姿勢を伝えるためにも、ホームページは欠かせません。なぜ今、企業サイトが必要なのかをメリット・デメリットの両面から解説しています。
社会的価値を持つ活動も、正しく届けてこそ意味があります。集客・発信力を高めたい企業担当者向けに、実践的なWebマーケティングのポイントをまとめたマニュアルです。
CSV・CSRの活動はCI戦略の一部とも言えます。CIの基本からWebサイトでの見せ方までを詳しく解説した、企業ブランディングを強化したい方必見の内容です。
CSV(共有価値の創造)とCSR(企業の社会的責任)は、企業が社会との関わりを築くための2つの重要な視点です。CSRは企業の義務や信頼の土台として不可欠である一方、CSVは社会課題を起点に企業成長へとつなげる「攻め」の戦略として注目されています。
時代とともに、企業には単なる責任以上の「価値ある存在」であることが求められています。これからの経営では、CSRによる信頼構築に加えて、CSVを通じた本業との融合が企業価値を左右します。社会と企業、双方の利益を追求するバランス感覚こそが、持続可能な企業経営の鍵となるでしょう。
CSV・CSRの取り組みを効果的に伝えるホームページを
情報設計に基づいたWebサイトで、企業の姿勢や社会貢献活動をわかりやすく発信しませんか?
▶ [ホームページ制作のご相談はこちら]
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。