Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
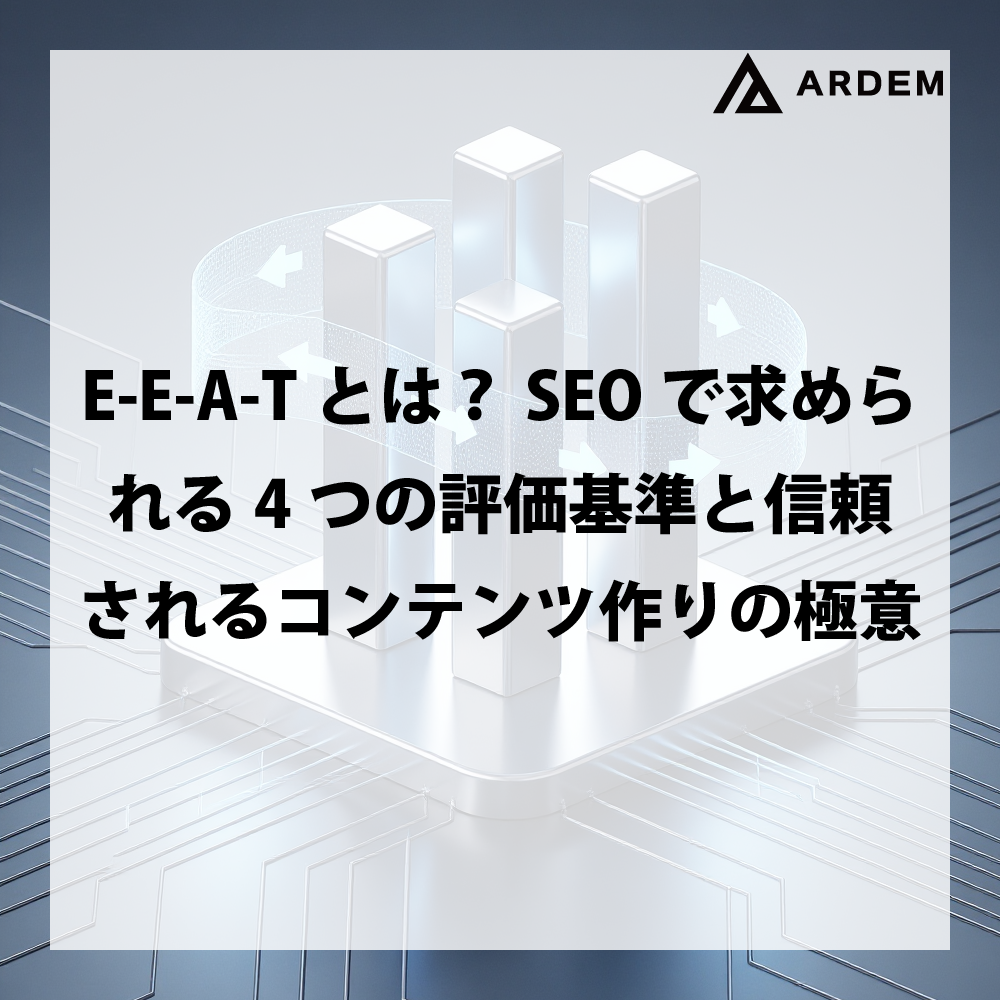
目次
「せっかく良いコンテンツを作ったのに、なかなか検索順位が上がらない…」
そんな悩みを抱えていませんか?
検索エンジン最適化(SEO)の世界では、コンテンツの品質がかつてないほど重要視されるようになっています。そのなかでも特に注目されているのが、Googleが定める評価基準「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」です。
この指標は、ユーザーにとって「本当に役立つ情報かどうか」を判断するうえでの大きな基準となっており、近年の検索アルゴリズムの中核に据えられています。
特に医療・金融・法律など、ユーザーの生活や人生に影響を及ぼす「YMYL(Your Money or Your Life)」領域では、E-E-A-Tの有無が検索順位に直結するケースも少なくありません。
「E-E-A-Tって具体的には何をすればいいの?」「どうやって評価されているの?」と感じた方のために、この記事ではE-E-A-Tの4要素それぞれの意味から、SEOへの影響、実践的な対策方法までをわかりやすく解説していきます。
E-E-A-Tを正しく理解し、自社のコンテンツ力を高めることで、長期的に安定した検索流入と信頼を獲得しましょう。
E-E-A-Tを意識したコンテンツ運用で、検索順位も信頼も上げたい方へ。
ARDEMでは、戦略設計からライティング支援、Web制作まで一貫して対応しています。
まずはお気軽に、無料相談をご利用ください。
▶ [無料相談フォームはこちら]

E-E-A-Tとは、Googleの検索品質評価ガイドラインにおいて重要な評価基準とされる「Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字を組み合わせた言葉です。これは、ウェブページやコンテンツ、さらにはその作成者が信頼できる情報源であるかどうかを評価する際に使われます。
単なるテクニックやキーワード詰め込みによるSEOが通用しにくくなった現在、Googleは「誰が」「どのような立場で」「どんな経験をもとに」情報を発信しているのかを重視するようになっています。つまり、検索上位に表示されるには、単に情報が正しいだけでなく、情報提供者自身の信頼性や体験にも注目されるということです。
では、なぜこのような評価基準が重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、ユーザーの安全と満足度を第一に考えるGoogleのポリシーがあります。
Googleは検索品質を向上させるため、全世界の評価者(人間の検索品質評価者)に向けて「検索品質評価ガイドライン(Search Quality Evaluator Guidelines)」という文書を公開しています。このガイドラインでは、E-E-A-Tが高いページを「高品質なコンテンツ」として評価することが明記されています。
この評価は、実際の検索ランキングを直接決めるものではありませんが、アルゴリズムを改善する際の参考データとして活用されています。そのため、Googleの方針を理解し、ガイドラインに沿ったコンテンツを制作することは、検索順位を高めるうえで非常に重要です。
とくにガイドラインの中では、次の3点が繰り返し強調されています。
これらの要素が満たされているほど、コンテンツのE-E-A-T評価は高まるとされています。

もともとGoogleは、2014年頃から「E-A-T(専門性・権威性・信頼性)」を重視していました。しかし、2022年12月に行われた品質評価ガイドラインの更新により、新たに「Experience(経験)」が追加され、「E-E-A-T」となりました。
この進化の背景には、ユーザーの検索意図が変化していることが挙げられます。情報があふれる現代において、ユーザーは単なる理論や知識だけでなく、実際にその情報を体験した人の声や経験談を求めるようになっています。たとえば、商品レビューや治療体験談、資格取得の勉強法など、「やってみた人の話」が求められる場面は非常に多いのです。
こうしたニーズに対応するため、Googleは「経験(Experience)」を明確に評価項目として組み入れました。つまり、コンテンツに一次情報やリアルな体験が含まれているかどうかが、今後ますます重要になるということです。
E-A-TからE-E-A-Tへと進化したことで、SEOにおけるコンテンツ制作のハードルは上がったともいえますが、逆に言えば「信頼される経験をもとに、誠実に発信すること」が正しく評価される時代になったということでもあります。
E-E-A-Tは、Googleがコンテンツの品質を判断する際に重視している4つの要素の頭文字です。それぞれの意味を理解し、実際のコンテンツ制作に活かすことが、検索上位を目指すための第一歩となります。ここでは、E-E-A-Tの各要素について詳しく解説します。
「Experience(経験)」とは、コンテンツ作成者が実際にそのトピックに関して体験したことがあるかどうかを指します。たとえば、商品レビューや医療体験談、旅行記など、実際に「自分でやってみた」「使ってみた」という一次情報には、ユーザーが信頼を置きやすいという特性があります。
Googleは、こうした一次体験に基づいたコンテンツを高く評価しています。なぜなら、それは単なる理論やデータでは得られないリアルな価値があるからです。
例:
ポイント:
「Expertise(専門性)」は、そのテーマについて深い知識やスキルを持っているかどうかという点に関係します。とくに医療、法律、金融、不動産などのYMYL(Your Money or Your Life)領域では、この専門性の有無が極めて重視されます。
たとえば医療情報を扱う場合、医師や看護師、薬剤師など医療に関する資格や実務経験がある人が書いた記事のほうが、専門性が高いと評価されます。
例:
ポイント:
「Authoritativeness(権威性)」は、その情報が外部からどれだけ評価・信頼されているかに関係します。専門家としての肩書きや、第三者からの評価、他サイトからの引用などが、Googleにとって権威の指標になります。
たとえば、同業界の有名サイトからリンクされていたり、テレビや書籍などのメディアで紹介されていたりすると、権威性が高いとみなされます。
例:
ポイント:
「Trust(信頼性)」は、E-E-A-Tの中でも最も重要とされる要素です。Googleも検索品質評価ガイドラインで「Trust is the most important member of the E-E-A-T family(信頼性は最も重要)」と述べています。
情報が正確であることはもちろん、誰が何の目的でコンテンツを作ったのかが明確であることが、信頼性の判断材料になります。虚偽や誇大な表現、出典不明の情報、不自然な誘導などは信頼性を損ね、順位低下につながる恐れがあります。
例:
ポイント:
「E-E-A-TはSEOに直結するのか?」
この問いに対する答えは、「直接的ではないが、極めて重要な間接要因である」というのがGoogle公式の立場です。Googleはランキング要因としてE-E-A-Tのスコアを明示的に数値化しているわけではありませんが、数多くのアルゴリズムや評価指標を通じてE-E-A-Tの高いページが上位表示されやすくなる構造を作り上げています。
このセクションでは、E-E-A-Tが検索順位にどのように影響しているのか、どのようなジャンルで特に重視されているのか、またその評価はどのように行われているのかを詳しく見ていきましょう。
E-E-A-T自体は数値的なランキングファクターではないものの、それを構成する要素はGoogleの検索アルゴリズムの随所に組み込まれています。たとえば以下のような点が間接的に順位へと影響を与えています。
Googleはこれら複数のシグナルを組み合わせることで、E-E-A-Tの高いコンテンツを上位に持ってこようとしています。
特に、ユーザーが満足しているか(UX)やサイト全体の信用性を加味しながら、E-E-A-Tが実質的なランキング評価に大きく寄与する仕組みとなっています。
E-E-A-Tが特に重視されるのが、YMYL(Your Money or Your Life)領域です。これは、ユーザーの健康・安全・金融・法律など、人生に重大な影響を与える可能性があるジャンルのことを指します。
具体的には以下のようなジャンルが該当します。
これらの領域では、誤った情報がユーザーに深刻な影響を与える可能性があるため、より厳格にE-E-A-Tが評価される傾向があります。
実際、GoogleのコアアップデートではYMYL領域のサイトが一斉に順位変動を受けることが多く、信頼性の乏しい情報は容赦なく圏外に落ちることも珍しくありません。
E-E-A-Tの評価方法には、大きく分けて以下の2つがあります。
Googleは、無数のランキングシグナル(被リンクの質、コンテンツの構造、著者情報の有無、ユーザー行動データなど)をもとに、E-E-A-Tを間接的に数値化して評価しています。
たとえば、
など、検索アルゴリズムの複数の層でE-E-A-Tを構成する要素が絡み合っています。
Googleは、実際の人間が「検索結果の品質を評価する」というプロセスを通じて、アルゴリズムの精度を改善するデータを収集しています。
この評価者たちは、Googleが公開している「検索品質評価ガイドライン」に基づき、ページのE-E-A-Tが高いかどうかを判断します。
ここで得られた評価結果は、直接検索順位に影響するわけではありませんが、今後のアルゴリズム改善の方向性に大きく影響します。つまり、「このような特徴のあるページが高評価されるべきだ」とGoogleが学習する材料になっているのです。
Googleは検索順位を決定する正確なアルゴリズムを公開していないものの、いくつかの公式ガイドラインやアップデート情報を通じて、コンテンツ評価の方針を明らかにしています。なかでも「検索品質評価ガイドライン」と「ヘルプフルコンテンツアップデート」において、E-E-A-Tの考え方が明確に示されています。
この章では、Googleが何をもって「信頼できるコンテンツ」と判断しているのか、その根拠となる公式文書をもとに解説します。
Googleが世界中の品質評価担当者(Search Quality Raters)に配布している「検索品質評価ガイドライン(Search Quality Evaluator Guidelines)」は、E-E-A-Tに関する最も公式かつ具体的な資料です。
このガイドラインでは、Webページを以下のような観点から評価するよう指示されています。
そして、特に強調されているのが「E-E-A-Tが高いほど、ページの評価は高くなる」という点です。
ガイドライン上では、YMYL領域の記事に対しては、**「高いE-E-A-Tが不可欠」**とも明記されています。
なお、最新のガイドラインでは、「Trust(信頼性)」が最も重要な要素であると位置づけられており、その他のExperience、Expertise、Authoritativenessは信頼性を担保するための要素とされています。
Googleは2022年から段階的に導入している「Helpful Content Update(ヘルプフルコンテンツアップデート)」においても、E-E-A-Tの考え方を強く反映させています。
このアップデートの目的は、以下のようなコンテンツを検索上位に表示させることです。
つまり、検索エンジンのために作られたコンテンツ(いわゆるSEOテクニックに偏った記事)ではなく、ユーザーのために作られた有益なコンテンツが評価される仕組みに変化しているのです。
Googleはこのアップデートに際し、開発者向け公式ページで「E-E-A-Tの考え方を持つことは、ヘルプフルコンテンツの品質向上に役立つ」と明言しています。
E-E-A-Tはあくまで直接的なランキングシグナルではないとGoogleは明言しています。
つまり、「E-E-A-Tスコア〇点だから順位〇位になる」といった単純な構造ではありません。
しかし、実際の検索結果を分析すると、E-E-A-Tの高いサイト・記事が上位にランクインしやすい傾向が顕著に見られます。これは、Googleの多層的なアルゴリズムがE-E-A-Tを複数の評価軸に反映していることを示しています。
具体的には以下のような要素がランキングに影響を与えると考えられます。
| 関連する要素 | 間接的にE-E-A-Tを評価する動き |
| 被リンクの質と量 | 権威性の指標として認識されやすい |
| 構造化データの有無 | 著者情報や企業情報の明示に有効 |
| 滞在時間・直帰率 | 経験や信頼性が高いコンテンツは離脱率が低い |
| ユーザー行動(クリック率等) | 有益な情報ほどCTRやシェア率が高くなりやすい |
| モバイル対応・UX設計 | ユーザー満足度がE-E-A-Tの信頼性に寄与 |
つまり、E-E-A-Tの実践とは、Googleが理想とする検索体験を提供することに他なりません。その結果として、自然と検索順位の上昇や安定化が見込めるのです。
検索上位を目指すうえで、E-E-A-Tの強化は欠かせない要素です。E-E-A-Tが高いコンテンツとは、ユーザーにとって「信頼できる・納得できる・役に立つ」情報が提供されている状態を指します。ここでは、実際にどのような工夫や運用を行えばE-E-A-Tを高められるのか、実践的な視点で4つの重要な対策を解説します。
E-E-A-Tの基盤としてまず重要なのが、「誰がその情報を発信しているか」を明確にすることです。コンテンツに信頼を持ってもらうためには、著者がどんな立場で、どんな経験・実績を持っているのかをユーザーに伝える必要があります。
具体的な取り組み例:
たとえば、「医療系の記事なら医師」「お金の話ならファイナンシャルプランナー」「育児の話なら実際の親」など、そのテーマにおいて語るに足る人物が書いているという印象があるだけで、信頼性は大きく変わります。
E-E-A-Tの中でも、特に新しく加わった「Experience(経験)」を高めるうえで効果的なのが、一次情報=自らの体験に基づいた内容の発信です。
Googleは、インターネット上に溢れる情報のなかで「自分で体験した人が語っているかどうか」を重要な判断材料としています。コピペやAIの再構成記事では得られないリアルな視点が、検索評価の差を生みます。
効果的な書き方:
ユーザーは、専門知識と同じくらい「自分ごと化できるリアルな声」を求めています。一歩踏み込んだ体験共有は、E-E-A-Tだけでなく、読者の共感と行動にもつながります。
E-E-A-Tの「Authoritativeness(権威性)」を高めるには、第三者からの評価や引用も不可欠です。特にSEOの観点からは、**信頼性のある他サイトからの被リンク(バックリンク)**が重要なシグナルとされます。
また、自ら他の信頼ある情報源へリンクを張ることも、「内容の裏付けがある」「調査・比較されている」という印象を強めます。
具体的な戦略:
Googleは「他人から評価されている情報=価値がある」と見なす傾向にあるため、**“リンクされるに値する良質な情報”**を蓄積することも戦略の一環です。
E-E-A-Tの「Trust(信頼性)」を強化するためには、記載している情報の裏付けや出典の明示が不可欠です。正確性の高い情報であることを示すことで、読者にとっての安心感が生まれ、Googleからの評価も高まりやすくなります。
実践のポイント:
また、信頼性を損なう行為(例:誇張した表現、明らかな誤記、不正確な引用など)は、SEOだけでなくユーザー離脱・ブランド毀損にもつながるため、公開前の事実確認や第三者によるレビューも推奨されます。

E-E-A-Tを高めるためには、コンテンツそのものの質を向上させるだけでなく、サイトの構造や外部との関係性、ブランドの信頼性構築も重要です。ここでは、実際の運用に活かせる具体的な取り組みを4つの観点から紹介します。
企業やオウンドメディアでE-E-A-Tを高めるには、情報の信頼性を可視化し、継続的にコンテンツを改善・管理する体制が求められます。
主な対策例:
信頼性の裏づけを「明示」することは、企業が行うSEOにおいてますます必須になっています。
YMYL(Your Money or Your Life)ジャンルにおいては、一般的なE-E-A-T対策に加えて、法的・倫理的な配慮と、情報の正確性と根拠の明示が非常に重要です。
注意すべきポイント:
この領域はGoogleからの評価が非常に厳しく、E-E-A-Tの欠如は即座に順位低下につながるため、細心の注意が必要です。
Googleは情報の信頼性を評価する際に、第三者が提供する公的情報や外部データベースとの整合性も参照しています。その代表例が「ナレッジパネル」と「ウィキペディア」です。
・OrganizationやPersonの構造化データをページに記述
・Wikidataに企業・著者情報を登録
・Googleビジネスプロフィールを充実させ、SNSやサイトと統一感を持たせる
ナレッジパネルやウィキペディアは、Googleのアルゴリズムが「権威」を推定する材料として利用するため、SEO上の間接的効果は非常に大きいといえます。
SNSは直接的なSEOシグナルにはなりにくいとされていますが、E-E-A-Tの「信頼性」や「ブランド認知」の強化には大いに寄与します。
活用ポイント:
さらに、SNSでエンゲージメントが高い投稿があると、検索結果のサイドリンクやトップニュース枠に表示されることもあり、間接的なSEO効果も期待できます。
SEO対策にはさまざまな手法がありますが、そのすべてがE-E-A-Tと同じ性質を持っているわけではありません。むしろ、E-E-A-Tは従来のSEO要因を補完し、全体の評価を底上げする“信頼の土台”として機能します。
ここでは、コンテンツSEO・内部対策・UX・ページスピードといった他の代表的な施策とE-E-A-Tとの違いや相互作用について整理します。
コンテンツSEOとは、検索意図に沿ったキーワード選定や、適切な構成・文量・見出し設計などを通じて、検索エンジンとユーザー双方に最適化されたコンテンツを提供する施策です。
一方、E-E-A-Tはそのコンテンツの“中身の信頼性”を高めるものであり、コンテンツSEOが「入り口」を整えるのに対して、E-E-A-Tは「本質的な価値」を保証する役割を担います。
| 項目 | 目的 | 代表的な施策 | 補完関係 |
| コンテンツSEO | 検索キーワードに沿った最適化 | タイトル設計、見出し構造、キーワード出現率 | E-E-A-Tによって情報の“深み”を補う |
| 内部対策(テクニカルSEO) | サイト構造やクローラビリティの最適化 | パンくずリスト、サイトマップ、内部リンク、canonical設定 | E-E-A-Tによってページ自体の“評価軸”を明示できる |
たとえば、どれだけキーワードが正しく設計されていても、中身が信頼できない情報であれば検索順位は伸びません。逆に、非常に信頼できる内容であっても、検索ニーズに答えていなければ露出されにくくなります。
つまり、E-E-A-TとコンテンツSEO・内部対策はそれぞれ独立ではなく、重なり合うことで最大の成果を発揮する関係にあるのです。
ユーザー体験(UX)やページ表示速度も、E-E-A-Tとは別軸のSEO評価要素として、Googleが強く重視しているポイントです。
UXの良さとは、ページの見やすさ、導線のわかりやすさ、目的到達のしやすさなど、ユーザーがストレスなく情報を得られる設計のことを指します。これに対してE-E-A-Tは、得られる情報そのものが信頼できるか、役に立つかという本質面を評価します。
| 指標 | 影響する主なSEO評価軸 | E-E-A-Tとの関係性 |
| ページスピード | Core Web Vitals(LCP・FID・CLSなど) | 読了率・離脱率の改善→結果的にE-E-A-Tの評価を後押し |
| モバイル対応・UI | ユーザビリティの高さ | 「読みやすい」「探しやすい」構成は専門性や信頼性の伝達を助ける |
| 構造化データの活用 | リッチリザルトの表示 | 著者やレビューの情報をGoogleに正確に伝え、E-E-A-Tを補完 |
UXやスピード改善は、直接的な「信頼性」の評価ではないものの、ユーザーの行動指標(滞在時間、直帰率、再訪率など)を通じて、E-E-A-Tに間接的な影響を及ぼします。
たとえば、同じ内容のページでも、表示が遅かったり読みにくかったりすれば、信頼できる印象は得られません。逆に、快適で洗練されたUI設計は、情報への信頼感を視覚的に強化する役割も果たします。
E-E-A-Tはコンテンツの評価基準として重要であると理解していても、具体的に「何をどうすればよいのか」が分かりづらいという声は少なくありません。ここでは、E-E-A-Tに関して寄せられる代表的な質問に対し、明確かつ実践的な回答を提示します。
いいえ、E-E-A-Tに関してGoogleがスコアを数値化して公開することはありません。GoogleはE-E-A-Tを「直接のランキング要因ではない」としつつも、アルゴリズム全体に浸透した重要な概念として扱っています。
ただし、間接的にE-E-A-Tが反映されていると思われる指標をチェックすることは可能です。たとえば以下のような方法で、信頼性や評価傾向の手がかりを探れます。
また、コンテンツが検索品質評価ガイドラインに照らして適切かどうかを、社内でセルフチェックリスト化するのも有効です。
はい、個人ブログであってもE-E-A-Tは適切に評価されます。企業サイトや大手メディアに比べて不利なのでは?と思われがちですが、実際には個人ならではの強みが活かされる場面も多くあります。
特に「Experience(経験)」の要素においては、実体験に基づいた一次情報を共有できる点が個人ブロガーの大きな武器となります。
たとえば、
などは、単なる情報サイトにはない臨場感や信頼性を提供できます。
もちろん、誤情報の発信や匿名での信頼性の低い投稿は逆効果になりますが、「顔が見える」「過去の投稿と整合性がある」「責任感を持った発信」が継続されていれば、個人でも十分に高いE-E-A-Tを築けます。
必ずしもマイナスではありませんが、AIが書いたという事実よりも「内容の品質」と「誰が責任を持って公開しているか」が重要です。
Googleは2023年以降、「AIによって生成されたコンテンツそのものを禁止することはない」と明言しており、人間の役に立つものであれば、生成方法を問わず評価する方針を示しています。
しかし注意すべきは以下の点です。
つまり、AIはあくまで「執筆補助ツール」として活用し、人間が編集・監修し、責任を持って発信する体制が整っていることが前提です。とくにYMYL分野では、AIだけで構成された記事が順位圏外になる事例もあるため注意が必要です。
サジェストを活用したSEO対策をさらに深めたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
まず、検索品質に大きな影響を与える「YMYL(Your Money or Your Life)」の概念とSEO対策について詳しく知りたい方には、こちらの記事がおすすめです。医療・金融・法律など、信頼性が特に重視されるジャンルでの施策のヒントが詰まっています。
また、SEO対策の全体像を体系的に学びたい方には、基礎から応用まで網羅したこちらの解説記事もご活用ください。初心者の方にも分かりやすく、すぐに実践できる内容が満載です。
どちらもサジェスト理解とSEO戦略を組み合わせる上で役立つ内容となっています。
E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、Googleが掲げる検索品質評価の核心であり、コンテンツSEOをはじめとする施策の“土台”ともいえる考え方です。一朝一夕で結果が出る施策ではありませんが、長期的な視点で取り組むことで、検索エンジンにもユーザーにも評価される資産へと育っていきます。
特にYMYLジャンルではE-E-A-Tの欠如が致命的になりうる一方で、一般ジャンルでもE-E-A-Tを意識した発信が、継続的なアクセスやブランドの信頼性向上につながります。
SEOはもはや「検索順位を上げるためのテクニック」ではなく、ユーザーにとって有益な情報を、誠実に届け続ける活動そのものです。E-E-A-Tを意識した運用とは、すなわちコンテンツに「責任」と「根拠」と「経験」を持たせることにほかなりません。
こうした点を明確にし、「信頼される発信者」としてコンテンツを積み重ねていくことが、SEOだけでなく事業全体の価値向上にも直結します。
小手先のテクニックに頼らず、本質的な信頼を築く姿勢こそが、これからのWebマーケティングにおける最大の競争力となるでしょう。
「どれだけ更新しても順位が上がらない…」そんなお悩み、私たちがサポートします。
ARDEMでは、E-E-A-Tを軸にしたWebサイト改善・コンテンツ戦略のご提案が可能です。
まずはお気軽に、無料相談で課題を一緒に整理してみませんか?
▶ [無料相談はこちらから]
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。