Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
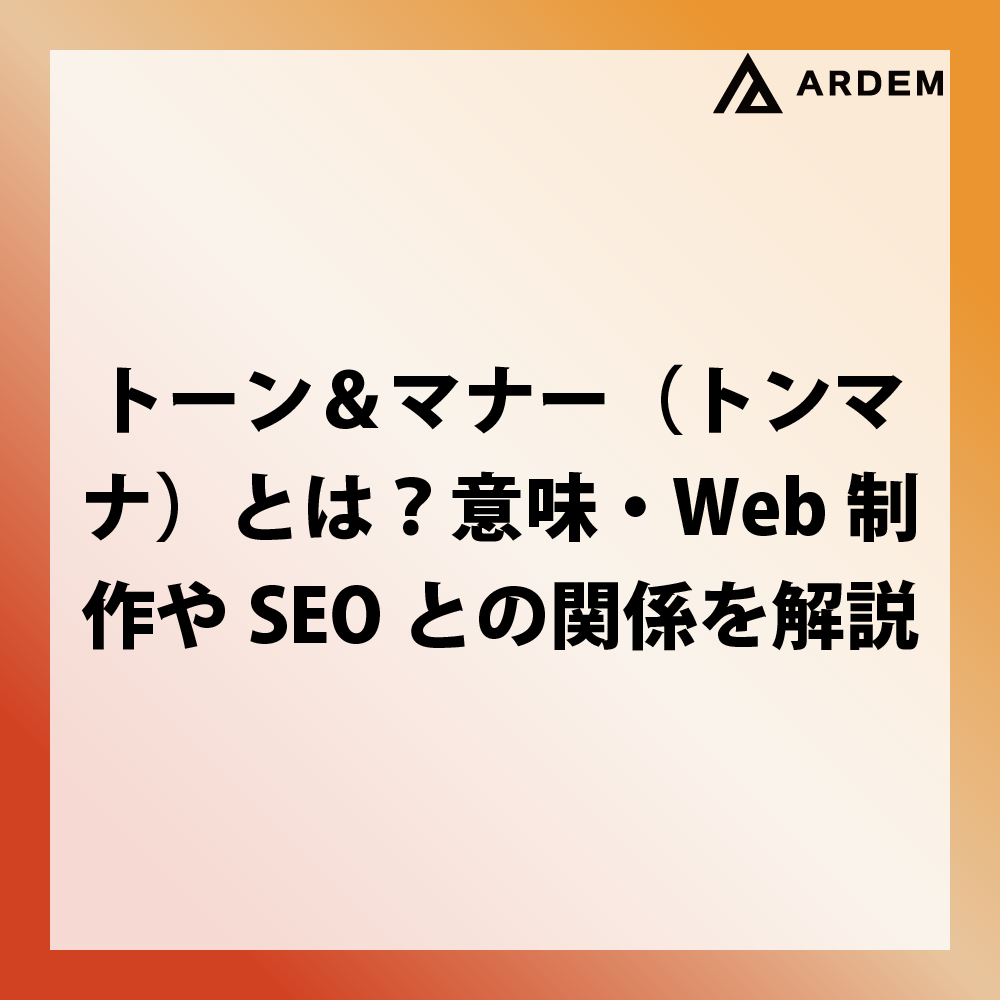
目次
企業やブランドが発信するあらゆる情報には、その印象を決定づける“雰囲気”や“語り口”があります。これは単なる言葉遣いやデザインの違いではなく、「トーン&マナー(トンマナ)」と呼ばれる重要なコミュニケーション要素によって形作られています。トンマナが整っているかどうかは、ユーザーとの信頼構築、ブランドイメージの確立、さらにはWebサイトの成果にも大きく影響します。
特に、Webコンテンツがあふれる現代においては、記事やホームページ、広告バナーなど、どの媒体においても一貫したトンマナが求められます。また、SEOとの関連も無視できず、Googleが推奨する「信頼性」や「専門性」といった評価指標にも関わってくるテーマです。
この記事では、「トーン&マナーとは何か?」という基本的な意味から、Web制作やSEOとの関係、実際の活用方法までをわかりやすく解説します。企業の情報発信力を高めたい方、サイト制作や運用を担う方にとって、必ず押さえておきたい内容です。
企業の魅力を正しく、わかりやすく伝えるには、トーン&マナーを軸にした一貫性ある情報発信が欠かせません。
ARDEMでは、貴社の言葉の設計からWebサイト制作まで、ブランドらしさを丁寧にカタチにします。
まずはお気軽にご相談ください。
▶ お問い合わせはこちら
「トーン&マナー(トンマナ)」とは、企業やブランドが発信する情報における“雰囲気”や“統一感”を保つための方針やルールを意味します。一般的には広告・広報・Web・パッケージ・紙媒体など、さまざまなクリエイティブ領域で用いられています。
まず「トーン(Tone)」とは、文章やビジュアル、声のトーンなどの“表現の雰囲気”を指します。たとえば、フレンドリー、フォーマル、親しみやすい、専門的といった印象の違いがそれにあたります。
一方で「マナー(Manner)」は、そのトーンをどのように使うか、どの範囲まで許容されるかといった“運用ルール”を意味します。言い換えれば、トーンが「方向性」なら、マナーは「ブレないためのガイドライン」といえるでしょう。
この2つが明確に定義・運用されていることで、複数の担当者がコンテンツを制作してもブランドとしての一貫性を保つことができ、受け手に安心感や信頼を与えられるのです。

企業にとって、トンマナを整えることは単なる「見た目の統一」にとどまりません。むしろ、ブランドとしての信頼性・一貫性を高める戦略的な取り組みといえます。
例えば、ある企業がWebサイトでは堅い文章を使っているのに、SNSでは砕けた若者言葉を多用していた場合、ユーザーはその企業の姿勢に一貫性を感じることができず、不信感を持つ可能性があります。逆に、どのチャネルでも一貫した雰囲気で情報発信されていれば、「この企業は誠実そうだ」「世界観がはっきりしていて好感が持てる」といったポジティブな印象が生まれます。
また、制作チームや委託先との連携においても、トンマナが明文化されていることで、誰がどのパートを担当してもズレのないコンテンツ作成が可能になります。特に複数人・複数拠点でWebサイトや広告を制作・運用するケースでは、ブランドイメージを守る上で不可欠な要素です。
このようにトンマナは、企業のブランド価値を正しく、そして効率的に伝えるために欠かせない指針なのです。
次章では、実際にトンマナがどのように活用されているのか、具体的な事例を交えながら解説していきます。

企業がブランドを構築していく上で、「トンマナ」は表現の土台となる極めて重要な要素です。どれほど良質な商品やサービスを提供していても、それを伝える手段に一貫性がなければ、ブランドとしての印象は曖昧になってしまいます。
たとえば、高級志向の化粧品ブランドがWebサイトではエレガントで上品な印象を与えているにもかかわらず、パンフレットではポップでカジュアルなトーンを使っていた場合、ユーザーの中に「このブランドは本当に高級なのか?」という疑念が生じます。このような印象のズレは、ブランドの信頼性や独自性を損なう原因になりかねません。
その点、トンマナが明確に設計され、全ての発信物において徹底されていれば、ユーザーはブランドに対して統一された印象を抱くようになります。「この会社らしい」「このブランドの世界観が好き」と感じてもらえることは、競合との差別化やファンの獲得につながり、ブランディングの成功に直結するのです。

人は情報の内容だけでなく、その「見せ方」や「言い回し」からも信頼性や真剣さを判断しています。たとえば、企業のWebサイトでページごとにデザインがバラバラだったり、文章のトーンが急にカジュアルになったりすると、「本当にこの会社に任せて大丈夫だろうか」と不安を感じるのが自然です。
逆に、配色、フォント、レイアウト、文章のトーンなどがすべて統一されていると、無意識のうちに「この企業は細部まで気を配っている」「丁寧な会社だ」という印象を受けるようになります。これは特に初めて訪れたユーザーにとって重要で、第一印象を大きく左右するポイントです。
また、トンマナの統一はユーザーにとって「安心感」や「使いやすさ」にも直結します。たとえば、あるECサイトが常に同じ構成・言い回しで商品を紹介している場合、ユーザーは商品選びのたびにストレスなく情報を読み取ることができます。これによりユーザー体験(UX)が向上し、再訪率や購買率の向上にもつながるのです。
つまり、統一されたトンマナは「企業の姿勢」と「ユーザー体験」の両面において、大きな信頼の土台となります。次章では、トンマナをSEOやWeb戦略の中でどう活用していけるか、その関係性に迫っていきます。
トンマナは、Webコンテンツの種類によって適切なバランスと設定が求められます。たとえば、企業のコーポレートサイトでは「誠実さ」「信頼感」「品位」などが重視されるため、落ち着いたトーンで明瞭かつ丁寧な言葉遣いが望まれます。デザイン面では、清潔感のある配色や整ったレイアウトがそれを補完します。
一方、LP(ランディングページ)は、より感情に訴え、コンバージョンにつなげる役割があるため、ややインパクトのある表現やコピーライティングを交えつつも、ブランドの世界観とズレないように配慮が必要です。トンマナを損なわない範囲で強調や装飾を行い、ユーザーの行動を促す設計が求められます。
ブログ記事では、情報提供や専門性が中心となるため、ターゲット層に合わせて親しみやすい口調か、専門的で信頼感のある文体を使い分けることが重要です。社内ノウハウや顧客の成功事例を紹介する記事であれば、ややカジュアル寄りのトーンでも問題ありませんが、「社としての立ち位置」がブレないよう一貫性を保つことが求められます。
このように、コンテンツごとに目的や読者の心理状態を想定し、適切なトンマナを設計・調整することが、ブランドの整合性とユーザー体験の両立につながります。
トンマナの一貫性を保つうえで、テキスト表現の細部まで意識することは非常に重要です。特に、以下の要素は注意深く設計・運用する必要があります。
「です・ます調」か「だ・である調」かによって、文章が与える印象は大きく異なります。前者はやわらかく親しみやすく、後者はやや堅めで信頼感や権威性を与える傾向があります。どちらかに統一することで、読み手の印象が安定します。
語尾が曖昧だったり、文末の表現が揺れていると、読み手に違和感を与えてしまいます。「〜と思います」「〜です」「〜しましょう」などを場面ごとに使い分けつつ、同一ページ内では一定のルールを設けて統一することが望まれます。
過剰な敬語表現や二重敬語は読みづらさや違和感を生みやすくなります。一方、カジュアルに寄せすぎると信頼性を損なう恐れもあるため、対象となる読者に応じて「フレンドリーさ」と「丁寧さ」のバランスを調整することが求められます。
若年層をターゲットとしたコンテンツであれば、ある程度くだけた表現や擬音語を使用することも効果的です。しかし、企業としての品位を損なわないように「使いすぎない・砕けすぎない」ことが基本です。
これらのポイントを丁寧に見直し、トンマナを守ることで、読者にとって読みやすく、企業の意図や価値観が伝わるコンテンツを作ることができます。次のセクションでは、トンマナとSEOとの関連性について掘り下げていきます。
Googleの検索評価において近年重視されているのが「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」という観点です。これは、検索ユーザーに対してどれだけ信頼できる情報を届けているかを評価するためのフレームワークであり、トンマナはこの評価軸に密接に関係しています。
たとえば、専門性を示すためには、信頼のおける文体・根拠ある表現・用語の正確な使い方が求められます。トンマナが曖昧だったり、コンテンツ全体で文体がぶれていたりすると、「このサイトは本当に専門的なのか?」という疑念をユーザーや検索エンジンに与えかねません。
また、「経験(Experience)」や「信頼性(Trust)」を担保するには、書き手が誰なのか、どのような立場で語っているのかが明確であることが重要です。たとえば医療・法律・金融などYMYL(Your Money or Your Life)領域では、丁寧な言葉遣いや一貫した敬体が信頼感を演出します。このとき、トンマナは単なる表現のトーンではなく、E-E-A-T全体を支える“体幹”とも言える存在です。
つまり、SEOにおけるE-E-A-T強化を目指すうえで、トンマナはコンテンツの信頼性と一貫性を演出するための重要な基盤なのです。
Googleは、過剰なSEOテクニックや不自然なキーワード詰め込みを見抜くアルゴリズムを進化させており、「ユーザーにとって自然な表現」で書かれているかを重視しています。ここでいう自然な表現とは、「読みやすく」「違和感がなく」「意図が明確である」文章であり、トンマナとの整合性が大きく関わります。
たとえば、キーワードを意識しすぎて「不自然な反復表現」が増えてしまうと、文章の流れが崩れ、ユーザーの離脱を招く恐れがあります。一方、トンマナに沿って丁寧に構成されたテキストは、キーワードの配置も自然で、読み手にストレスを与えません。結果として、ページの滞在時間が伸び、検索評価にポジティブな影響を与えることになります。
また、トンマナがサイト全体で一貫していれば、どのページを訪れても「この企業・ブランドらしさ」を感じられるため、リピーターやファン化にもつながります。Googleは“コンテンツの品質”を「単一ページ」ではなく「ドメイン全体の傾向」としても見ているため、ブランドの言語的統一性(=トンマナ)は、間接的にSEO順位の安定にも貢献します。
つまり、Googleにとってもユーザーにとっても、トンマナの整合性は“質の高いWebサイト”を判断するための重要な手がかりであり、SEOにおいても無視できないファクターなのです。
トンマナを統一するには、まず社内で言語に関するルールを明文化することが欠かせません。たとえば「語尾の統一(です・ます調/である調)」「敬語・カジュアル語の使い分け」「句読点の有無」「英数字・記号の表記ルール(全角/半角など)」といった基本方針を、ガイドラインとしてまとめておくことが重要です。
このガイドラインはWebコンテンツだけでなく、SNS投稿、メルマガ、営業資料などあらゆる情報発信に適用できる内容にしておくと効果的です。特に複数人でコンテンツを作成する体制の場合、ルールの有無がコンテンツの品質に大きな差を生みます。
また、定期的に内容を見直し、時代や媒体に合わせてアップデートしていく運用体制も整えておくと、トンマナの一貫性を継続的に維持できます。
トンマナは「誰に向けて発信するか」によって最適な表現が変わります。そこで欠かせないのが、ターゲットとなるペルソナの設定です。ペルソナとは、年齢、性別、職業、価値観、行動特性などを具体的に想定した“仮想のユーザー像”であり、これを明確にすることでトンマナの方向性が決まります。
たとえば、30代のキャリア女性に向けたブランドであれば、「共感を呼ぶ丁寧な言葉」「美意識に配慮した表現」「適度な感情のこもった語り口」が求められるでしょう。一方、10代の学生を対象とする場合は、ややくだけた言い回しやトレンドを意識した語彙が効果的です。
ターゲットに合ったトンマナでなければ、どれだけ情報が正しくても届きにくくなります。ペルソナとトンマナの整合性を意識することで、情報の受け手に刺さる言葉選びが可能になり、ひいてはエンゲージメントやCVRの向上にもつながります。
近年では、ChatGPTなどのAIライティングツールを活用してコンテンツ制作を行う企業が増えています。しかしAIが生成する文章は、一貫したトンマナの維持が難しい場合があるため、注意が必要です。
AIはあくまで「過去の膨大な文書データに基づいた平均的な言語スタイル」をもとにテキストを生成します。そのため、企業独自の言葉遣いやブランドトーンにフィットしていない場合があります。AIに任せきりにせず、トンマナガイドラインに沿って人間が監修・編集する工程を挟むことが、質の高いコンテンツを維持するためには不可欠です。
また、AIに対してプロンプト(指示文)を出す際にも、「誰に向けた文章か」「どんなトーンで書くべきか」など、トンマナに関する情報を具体的に与えることで、より意図に沿った出力が得られやすくなります。
AIツールを活用する場合は、“時短のための補助ツール”として使うのではなく、“トンマナを保ったまま効率的に伝えるための支援者”として位置づける意識が大切です。
トーン&マナー(トンマナ)は、企業やブランドが「何を」「どのように」伝えるかに関わる、情報発信の根幹です。単なる文体の統一にとどまらず、読み手との信頼関係を築き、ブランド価値を高めるための大切な要素といえます。
特にWebサイトやSNS、ブログといったデジタル上の発信では、トンマナの一貫性がユーザーの印象を左右します。SEOにおいても、離脱率の低下やサイトの評価向上に寄与することから、見過ごせないポイントです。
社内で言語ルールを策定し、ペルソナとの整合性を図りながら、AIツールの特性にも注意して運用することで、誰にでも伝わる「あなたらしい」言葉を生み出すことができます。
情報があふれる時代だからこそ、「何を言うか」だけでなく「どう言うか」に目を向けることが、選ばれるブランドへの第一歩となるでしょう。
「社内でトンマナのルールがバラバラ…」「文章のトーンがブランドと合っていない気がする」
そんなお悩みがある方は、ARDEMにご相談ください。
企業の価値を伝える言葉づくりと、伝わるWebサイト設計をサポートします。
▶ お問い合わせ
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。