Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
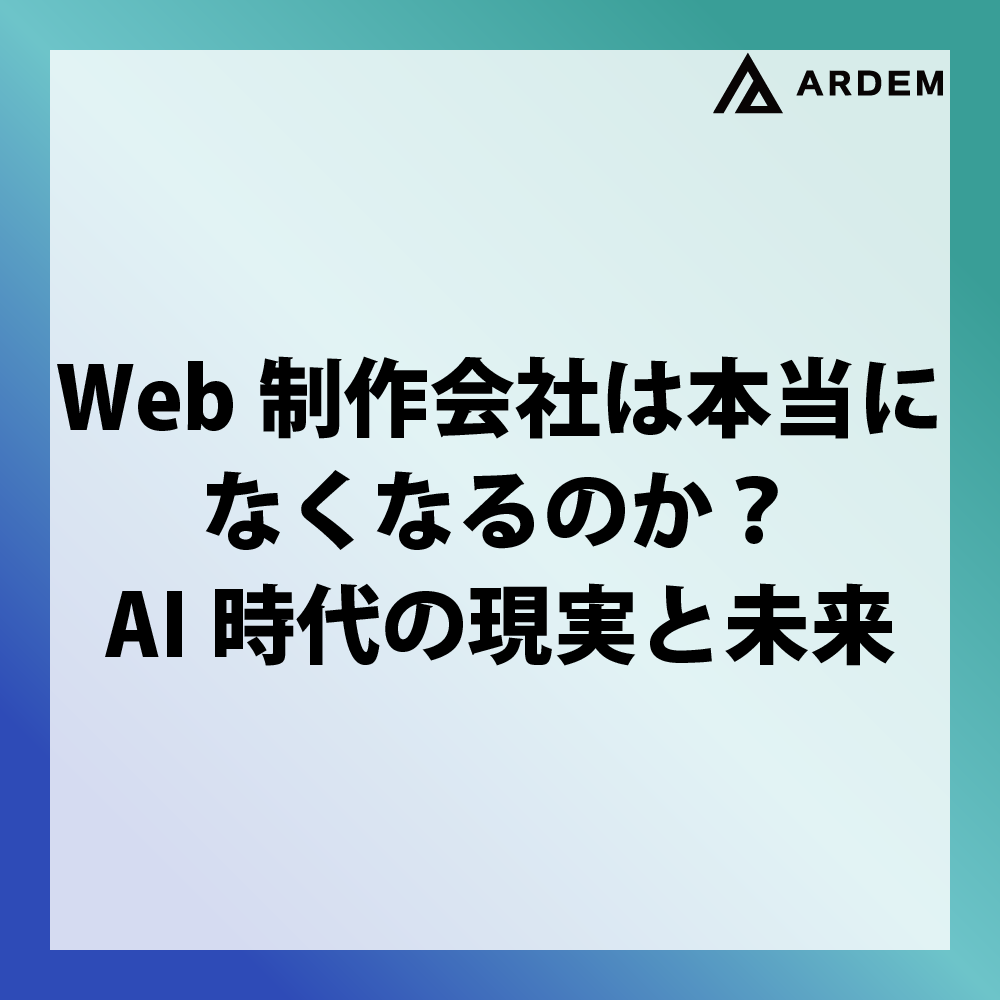
目次
Webサイト制作の現場に、かつてないほどの変化が押し寄せています。ノーコードツールやAIによる自動生成が進化し、「もう制作会社に頼まなくてもサイトは作れる」と考える企業も増えてきました。実際に「Web制作会社は将来的にいらなくなるのでは?」という声も少なくありません。
しかし、果たして本当にそうなのでしょうか。たしかにツールや技術の進歩によって、Webサイトを作る「手段」は多様化しましたが、「成果を出すサイト」を作るために必要なスキルやノウハウは、むしろ複雑化しています。
本記事では、Web制作会社がなくなると言われる背景を冷静に分析し、今後求められる制作会社の役割や進化の方向性について深掘りします。制作会社選びに悩む企業の方や、業界の将来を見据える制作者の方にとって、今後のヒントとなる内容です。
Web制作を「作って終わり」にしない。札幌・札幌周辺エリアで成果につながるパートナーをお探しなら、ARDEMへご相談ください。
サイトリニューアルや新規立ち上げを検討中の方は、課題整理からお手伝い可能です。お気軽にご相談ください。
▶ 無料相談はこちら
Web制作の現場では「制作会社不要論」が語られる機会が増えています。その背景には、技術や環境の変化だけでなく、企業の情報リテラシー向上や働き方の多様化など、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。
ここでは、特に影響が大きいと考えられる4つの要因を取り上げて解説します。
近年、プログラミング知識がなくてもWebサイトを構築できる「ノーコード」や「ローコード」ツールが急速に普及しています。たとえば、WixやSTUDIO、ペライチ、WordPressのブロックエディタなどは、ドラッグ&ドロップで直感的に操作でき、テンプレートも豊富に用意されています。
これらのツールの登場により、「Web制作=専門知識が必要」という常識が覆されつつあります。特に小規模な事業者や個人事業主にとっては、コストや時間の面で大きなメリットがあり、自力でサイトを立ち上げるケースも増えています。
さらに、近年注目されているのが、AIを活用したWeb制作の自動化です。たとえば、文章生成AI(ChatGPTなど)を使えば、コンテンツのライティングが瞬時に行えますし、画像生成AI(MidjourneyやDALL·Eなど)を使えば、オリジナルのビジュアル素材も自動生成できます。
さらに、AI搭載のWeb制作ツール(ZyroやBookmarkなど)は、ユーザーの目的や業種を入力するだけで、デザインや構成を提案してくれる機能を備えています。これらのツールを使えば、Web制作における「調査」「構成」「デザイン」「実装」といった工程を大幅に省略できるため、制作会社の存在意義に疑問を抱く声も出てきているのです。
副業解禁や働き方改革を背景に、Web制作を副業として行う人や、フリーランスとして独立する人が増えています。クラウドソーシングサービスの普及により、企業と個人制作者のマッチングも容易になりました。
企業側にとっては、制作会社に依頼するよりも低コストでスピーディに制作を進められるというメリットがあります。また、個人とのやり取りは柔軟で、細かいニュアンスにも対応してもらいやすいという点で、制作会社よりも好まれる場面もあります。
このように、「個人対企業」の関係が強まる中で、組織としての制作会社の立ち位置が相対的に揺らいでいるのです。
Webサイトに求められる役割が「情報掲載」から「集客・売上に貢献する仕組み」へと進化する中で、クライアントのニーズはより多様化・高度化しています。同時に、マーケティングやSNS運用、広告などを自社内で完結しようとする「内製化」の動きも広がっています。
たとえば、簡易的なLPやイベント用の特設ページなどは、自社マーケ担当者がノーコードツールで制作してしまうケースも少なくありません。こうした「軽量案件」の内製化が進むことで、従来制作会社が請け負っていた領域が徐々に狭まり、必要とされる場面が限定的になってきているのです。
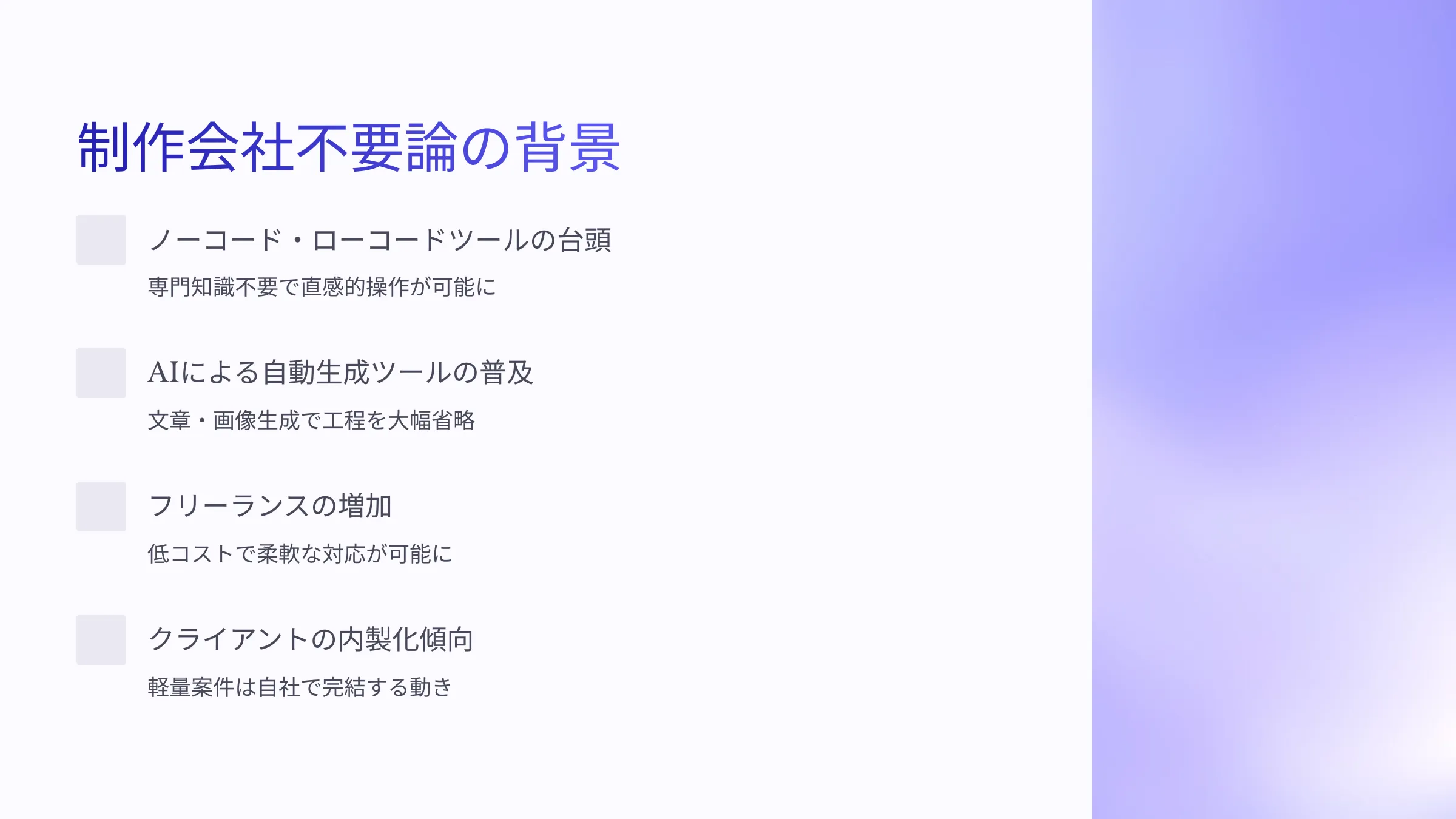
「ノーコードツールやAIの普及でWeb制作会社は不要になる」といった声がある一方で、実際にはいまだ多くの企業がWeb制作会社の力を必要としています。その理由は、Webサイトが単なる「見せる媒体」ではなく、「成果を生み出す戦略資産」へと進化しているからです。ここでは、Web制作会社ならではの4つの強みを紹介します。
Web制作は「サイトを作って終わり」ではありません。誰に何を伝え、どう行動させるか。そのためにどのような導線を設計し、どの媒体と連携するか——。このような全体戦略の立案と設計が成果に直結します。
Web制作会社には、多種多様な業種・業態のWeb戦略に携わってきた実績があり、クライアントの事業特性や課題に応じた最適解を導く力があります。また、ヒアリング力や課題抽出力にも長けており、「そもそもなぜWebサイトが必要なのか」から一緒に考え、成果につながる方針を共に描くことができます。
こうした“ビジネスパートナー”としての伴走力は、単なる制作スキルとは一線を画すプロフェッショナル性といえるでしょう。
ノーコードツールやテンプレートの限界の一つは、「誰にでも使える」ことによって、差別化されたデザインや使い勝手が犠牲になりやすい点です。Web制作会社は、ユーザー体験(UX)とユーザーインターフェース(UI)に配慮しながら、企業ごとのブランドイメージを損なわずに表現できる設計力を持っています。
たとえば、導線設計ひとつとっても、「訪問者がどのような心理でどの情報を求めているか」を想定し、迷わず目的地にたどり着けるように設計される必要があります。また、色使いや余白、写真のトーンなどのデザイン要素には、企業の信頼感や世界観を左右する力があります。
こうした「感じさせる設計」は、テンプレートでは実現しにくく、プロによる設計力が問われる領域です。
Webサイトが果たすべき役割は、単なる「会社案内」から「集客・売上を生む媒体」へと変化しています。特にSEO対策、SNSや広告との連携、CV設計(コンバージョン導線)などは、専門的な知見と継続的な運用が求められます。
Web制作会社の中には、制作だけでなくマーケティング支援にも強みを持つところが増えており、アクセス解析やA/Bテスト、広告運用の最適化などを通じて、継続的に成果を改善していく体制を構築できます。
単に「見栄えの良いサイトを作る」だけではなく、「ビジネス成果につながるWeb戦略を実現する」という視点で総合的に支援できる点も、大きな価値といえるでしょう。
Webサイトは公開して終わりではなく、セキュリティ対応・CMSアップデート・トラブル対応など、運用フェーズでのサポートも不可欠です。Web制作会社には法人向けの品質保証やSLA(サービスレベル合意)を整えているケースも多く、何かあった際の迅速な対応や、長期的な運用の安心感があります。
また、社内での稟議・決裁プロセスに対応した見積書や契約書のやり取り、プライバシーポリシーや法的表記に関する助言など、法人取引ならではの実務対応にも慣れているため、特に中堅〜大企業にとっては制作会社の存在が欠かせないものとなっています。

AIやノーコードツールの普及により、Web制作の“作業工程”そのものは誰でもある程度こなせる時代になりました。しかし、その一方で「作るだけの制作会社」は確実に淘汰されつつあります。これからの時代に生き残るWeb制作会社は、単なる制作代行から脱却し、より本質的な価値提供を行う方向へと進化が求められています。ここでは、制作会社がこれから担うべき4つの進化の方向性について紹介します。
かつてのWeb制作会社は、「依頼されたデザインを形にする」ことが主な業務でした。しかし今、求められているのは「事業課題を解決するためのWeb戦略を共に考えるパートナー」です。
例えば、「採用に苦戦している企業」であれば、単に採用ページを設置するのではなく、ターゲットに合わせた魅力の言語化、導線設計、エントリーフォームの最適化、indeedやGoogleしごと検索との連携などを含めた施策提案が必要になります。
つまり「ページを作る」から「成果を出す」へと軸足を移し、コンサルティング・ディレクション能力の強化が鍵となるのです。
制作業務の多くはフリーランスや外部パートナーでも賄える時代になっています。デザイン、コーディング、撮影、ライティングなど、それぞれの専門性を持つ人材を適切にアサインし、プロジェクトを円滑に進める“総合プロデューサー”としての役割が今後さらに重要になります。
制作会社が持つべきは、全体戦略と品質管理、納期管理、そして各種専門職をまとめる「ハブ」としての機能です。自社ですべてを抱え込むのではなく、最適な外部リソースと連携しながら、目的達成に向けてクライアントとチームを導いていく力が問われています。
中小企業やスタートアップの中には、「Webに詳しい担当者が社内にいない」「更新をすべて制作会社に依存している」といった課題を抱えているケースが多くあります。このような企業に対して、ホームページの運用方法やWebマーケティングの基礎を“教育”するという支援も、制作会社が果たせる重要な役割です。
たとえば、CMS(WordPressやSTUDIOなど)の更新方法を丁寧にレクチャーしたり、SEOの初歩的な考え方を共有したりすることで、クライアントが「自走できる状態」を目指す内製支援は、大きな信頼と差別化につながります。
「頼られる」だけでなく「育てる」という発想こそが、次世代の制作会社に求められる視点です。
サイトを公開して終わり、という時代はすでに過去のものです。現在では、「公開後にどのような成果を出せるか」「その成果をどう検証し、改善していくか」が問われています。
アクセス解析(GA4やSearch Console)、SEO対策、SNSや広告運用まで一貫してサポートできる体制を持つ制作会社は、クライアントにとって非常に心強い存在です。
特に中小企業の場合、マーケティング専任の人材を持たないケースが多いため、制作会社が戦略から実行、改善提案までを包括的に支援することで、持続的なWeb活用が実現します。
また、こうしたワンストップ支援体制は、LTV(顧客生涯価値)向上やリピート契約にもつながり、制作会社の安定経営にも寄与する大きな強みです。
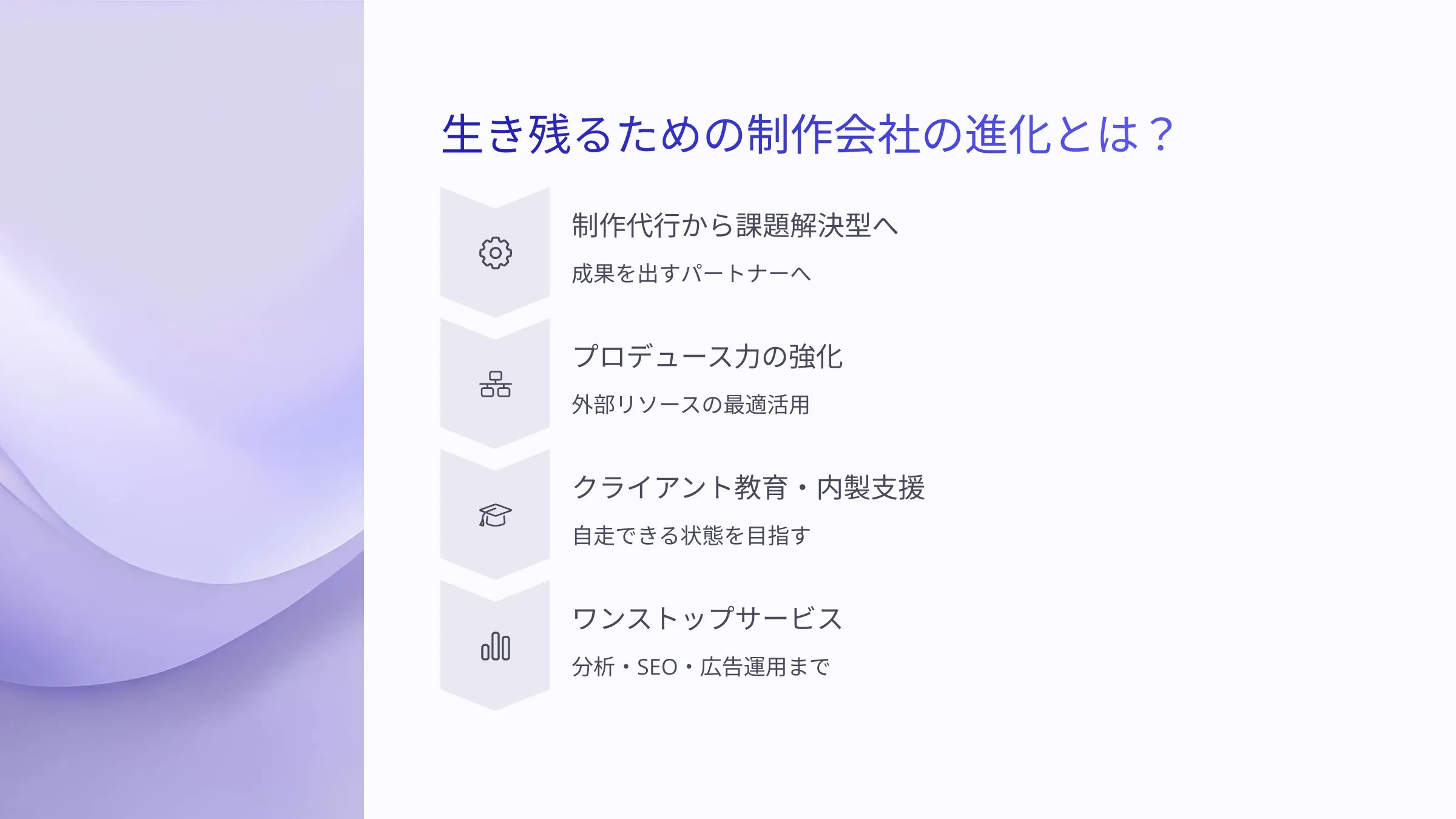
Webサイトの制作手段が多様化し、誰でも“それなり”のサイトを作れる時代になったからこそ、パートナーとなる制作会社をどう選ぶかがますます重要になっています。とくに、今後生き残る制作会社は「つくるだけ」ではなく、「成果を生み出す仕組みづくり」まで担う存在です。以下のポイントをもとに、信頼できる制作会社を見極める視点を紹介します。
デザインや構築といった表面的な“制作”が得意な会社は多く存在します。しかし、本当に成果につながるWebサイトを求めるのであれば、「なぜこの構成にしたのか」「なぜこのキーワードでコンテンツを展開するのか」といった戦略的思考を持っている会社を選ぶべきです。
具体的には、制作前にヒアリングや市場分析を丁寧に行い、競合やターゲットユーザーを踏まえたサイト構成を提案してくれる会社は、成果志向のパートナーといえるでしょう。単なるデザインの美しさや技術力だけでなく、ビジネスへの理解と成果への責任感があるかが判断基準になります。
多くの企業がWebサイトに求める目的は「集客したい」「採用を強化したい」「問い合わせを増やしたい」といったものですが、それらのニーズを表面的に受け取るだけでは、的確な施策は生まれません。
制作会社が真に価値ある提案を行うには、企業のビジョンや事業内容、競合状況、これまでの取り組みと課題まで深く理解する必要があります。初期の打ち合わせで「ヒアリングの深さ」や「質問の質」をチェックしてみましょう。クライアントを“下請け”としてではなく“パートナー”として捉えているかどうかが、対応の姿勢に表れます。
また、進行中にもしっかりとしたフィードバックや改善提案ができる体制(専任担当の有無、定期ミーティングの有無など)も重要な判断ポイントです。
制作会社を選ぶ際に、過去の制作実績を見るのは基本的なステップですが、それだけでは不十分です。重要なのは、「制作後にどのような成果が出たか」を明確に示せるかどうかです。
たとえば「リニューアル後に問い合わせ数が2倍になった」「採用エントリーが前年比150%に増えた」といった具体的な成果を数値で提示できる会社は、単なる制作ではなく、課題解決にコミットしてきた証拠といえます。
また、そうした成果を得たためにどのような施策を行ったのか(例:CTA設計、UI改善、SEO戦略の導入など)まで説明してもらうと、支援の質がより明確にわかります。
Web制作業界において、「Web制作会社は将来的にいらなくなるのでは?」という声が上がるのは、決して的外れな意見ではありません。しかし、それは“業界全体が消滅する”という意味ではなく、“淘汰が進む”という意味で捉えるべきです。つまり、生き残るのは「選ばれる理由がある会社」だけであり、それ以外は自然とフェードアウトしていく流れが加速しているのです。
かつては「格安でホームページを作成します」といった価格重視の制作会社が多く存在していました。しかし現在、テンプレート化された低価格サービスは、ノーコードツールやAIの台頭により、企業が自力で済ませる選択肢に置き換えられつつあります。
その結果、価格だけで選ばれる制作会社は、差別化が難しくなり、生き残ることが困難になります。今後求められるのは、単に安く早く“つくる”のではなく、顧客のビジネスにどんな付加価値を与えられるかという観点です。
たとえば、
こうした「戦略+制作」の視点を持つ会社は、価格以外の軸で顧客に選ばれる存在として残り続けることができます。
生成AIやノーコードツールが進化したことで、「人の手による制作=時代遅れ」と捉える風潮も出始めています。しかし、実際にはツールの活用次第で、制作会社の価値はむしろ高まる可能性があります。
ポイントは、「ツールを使いこなしてコスト削減すること」ではなく、「ツールによって生まれた余力を、戦略や提案に振り分けられるか」です。
たとえば、AIを使ってワイヤーフレームのたたき台を作り、その分クライアントのマーケティング課題に時間をかけて向き合う。CMSで更新の自動化を実現し、クライアントの社内運用の最適化までサポートする。そうした“課題解決力”こそが、今後の制作会社に求められる最大の武器です。
制作の一部が自動化されても、「誰のために、なぜこのサイトを作るのか」を見失わず、顧客と共に成長する意識を持てる会社こそが、これからも選ばれ続ける存在となるでしょう。

「Web制作会社は将来なくなるのか?」という問いに対して、答えは明確です。なくなるのではなく、選ばれない会社が消えていくのです。
AIやノーコードツールの進化により、従来型の「つくるだけ」の制作業務は確かに代替可能になりつつあります。しかし、その一方で「どんな目的で」「誰に向けて」「どのように成果を上げるか」という戦略性が、これまで以上に重要視される時代に突入しています。
“作って終わり”の制作会社は確かに淘汰されていくかもしれません。しかし、戦略と提案力を武器に「選ばれる理由」を持つ会社には、むしろこれからの時代にこそ活躍の余地が広がっています。
Web制作会社が生き残るために必要なのは「技術」ではなく「本質をつかむ力」。変化の時代を生き抜くために、今こそ制作の価値を再定義すべきタイミングです。
私たちARDEMは、「ただWebサイトを作るだけ」では終わらない、成果にこだわるWeb戦略パートナーです。札幌を拠点に、企業や店舗の本質的な課題を捉え、ブランディングから集客・運用支援までを一気通貫でご支援しています。
特に重視しているのは、クライアントごとの「目的」と「ゴール」に対する深い理解。テンプレート的な制作ではなく、ヒアリングや分析を通じて課題の本質にアプローチし、成果を生むための構成・導線設計・コンテンツ企画を行っています。
また、Webサイトは公開して終わりではありません。私たちは「運用して、成果につなげる」ことを前提に、SEO施策やUI/UXの改善提案、アクセス分析にも注力。中長期的な視点で、クライアントと伴走する体制を整えています。
「AIの時代に選ばれるWeb制作会社とは?」という問いに、ARDEMは「戦略と伴走力のある会社」と答えます。単なる制作の外注先ではなく、ビジネスの成長をともに描くパートナーとして、これからのWeb活用をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせ
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。