Blog


Get
Report!
Blog
BLOG
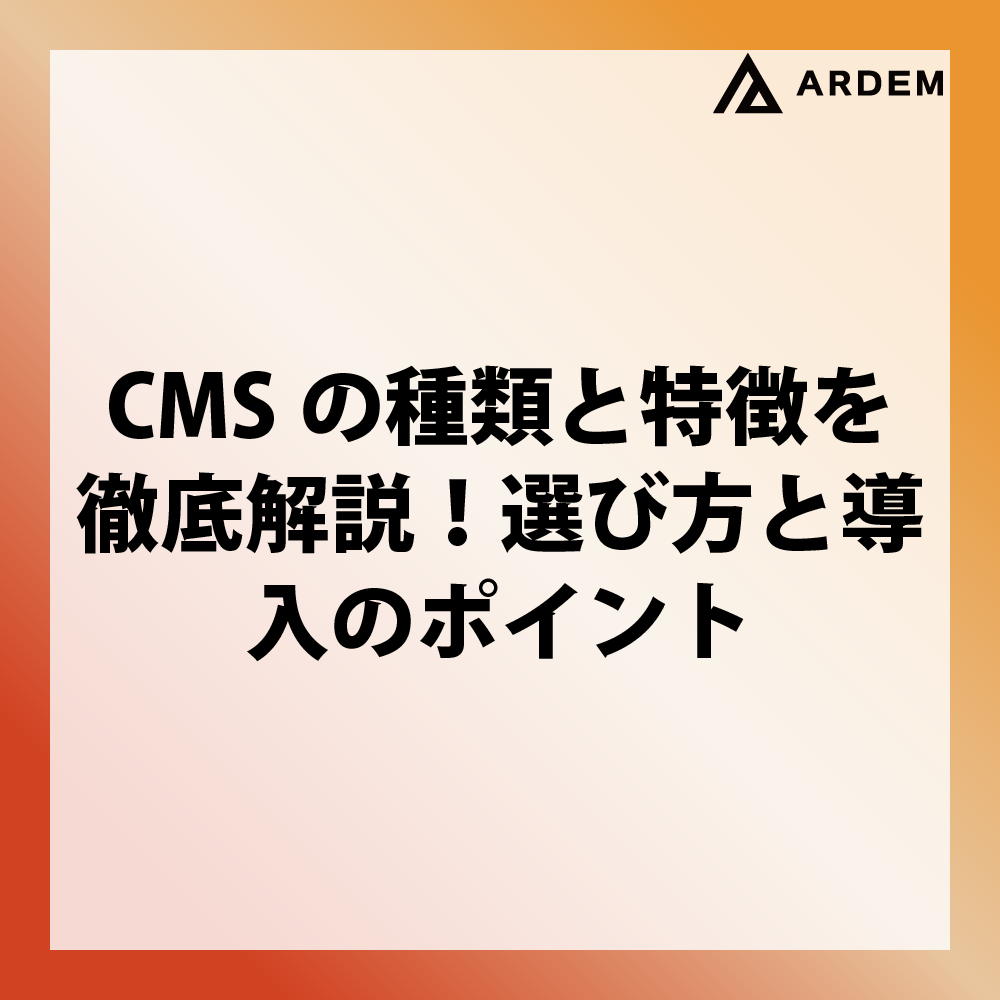
目次
Webサイトの運営において、今や欠かせない存在となったCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)。企業のコーポレートサイトからブログ、ECサイトまで、さまざまなWebサイトがCMSを活用して効率的に構築・管理されています。
しかし、CMSとひとくちに言っても、その種類や機能、選び方には大きな違いがあります。
本記事では、CMSの基本的な役割から、代表的なCMSの種類、それぞれのメリット・デメリット、そして導入時に押さえておくべきポイントまでをわかりやすく解説します。自社に最適なCMSを選ぶための判断材料として、ぜひ参考にしてください。
CMS導入に迷ったら、まずは無料相談から。
CMSの選定にお悩みの方、自社に最適な構成を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。中小企業から大規模サイトまで、豊富な導入実績をもとに最適なご提案をいたします。
▶ [CMS選定・導入無料相談はこちら]
近年、企業や個人がWebサイトを運営するうえで欠かせない存在となっているのが「CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)」です。これまでHTMLやCSSを手作業で記述していた時代とは異なり、専門的な知識がなくてもサイトを構築・更新できる仕組みとして、多くの企業が導入しています。
本章では、CMSの基本的な構造と機能、手動でのサイト更新との違い、そして企業がCMSを積極的に採用するようになった背景について解説します。

CMSは、Webサイトのコンテンツを「管理」するためのシステムです。構造としては大きく分けて「管理画面(バックエンド)」と「公開画面(フロントエンド)」の2つに分かれ、管理画面で入力・編集した内容が自動的に公開画面に反映される仕組みです。
CMSを導入することで、以下のようなことが可能になります。
従来のようにHTMLファイルを1ページずつ修正する必要がなく、Webサイト全体の更新や運用の効率が大きく向上します。
従来のWebサイト制作では、HTMLやCSSをエディターで手動入力し、サーバーにアップロードして反映させる作業が必要でした。これは自由度が高い反面、専門知識や時間が求められ、非エンジニアにとっては大きなハードルとなっていました。
一方、CMSはあらかじめ構築されたテンプレートやデータベースと連動し、直感的な操作でコンテンツを管理できます。たとえばWordPressでは、ブログ記事を入力フォームに打ち込むだけで、画像の挿入や見出しの設定も簡単に行えます。
HTML手打ちとの主な違いは以下の通りです。
手打ちHTML:
CMS:
このように、CMSはWebサイト運営をより「身近なもの」に変える存在となっています。
企業がCMSを採用するようになった背景には、Web運用の「スピード」と「継続性」が重視されるようになった社会的変化があります。情報更新の遅れは信頼性の低下につながるため、担当部署が自ら情報を発信・更新できるCMSの導入は必然でした。
また、スマートフォンやSNSの普及により、ユーザーとの接点が多様化。キャンペーンや新商品の告知など、リアルタイムな情報発信が求められる中、従来の開発フローでは対応が難しくなりました。CMSであれば、現場担当者がスピーディに更新でき、IT部門や制作会社に依存しない体制を整えることができます。
さらに、セキュリティ対策やSEO対応といった要素もCMSに標準搭載されていることが多く、コストパフォーマンスの面でも優れています。このように、CMSは「企業の情報資産を自らコントロールする」ための重要なツールとして定着してきたのです。
CMSにはさまざまな種類があり、目的や運用体制に応じて適切な選定が求められます。ここでは、主に4つの代表的なCMSの種類について、その特徴と代表的なサービス例を紹介します。
オープンソース型CMSは、ソースコードが公開されており、誰でも自由に利用・カスタマイズできるCMSです。世界中の開発者が改良や機能追加に貢献しており、拡張性・柔軟性に優れているのが特徴です。特に開発リソースが社内にある企業や、自由度の高い構築を求める中〜大規模サイトに向いています。
代表的なオープンソースCMS:
メリット
デメリット
クラウド型CMS(SaaS型CMS)は、ベンダーが提供するCMSサービスをインターネット経由で利用するタイプです。サーバーの準備やシステム保守が不要で、直感的な操作でWebサイトの構築・管理ができるため、Webに詳しくない担当者でも運用しやすいのが利点です。
代表的なクラウド型CMS:
メリット
デメリット
商用パッケージ型CMSは、ベンダーが開発・販売しているCMSソフトウェアをライセンス購入して利用する形態です。企業向けに設計されており、セキュリティ・サポート体制が整っているため、重要な情報を扱う企業サイトや公共機関、金融系サイトなどで広く採用されています。
代表的な商用パッケージCMS:
メリット
デメリット
自社開発型CMSは、企業が自らの要件に合わせて一からCMSを開発する方法です。既存のCMSでは実現できない機能やセキュリティ基準、ワークフローなどを完全に自社仕様に合わせられるのが最大のメリットです。
一方で、開発コストや保守・改修の負担が大きく、長期的な視点での運用体制が求められます。主に大企業や特殊な業務要件を持つ企業に向いている選択肢です。
メリット
デメリット

CMSを導入する際、選択肢としてよく挙がるのがWordPressやMovable Type、Wix、STUDIOといった有名プラットフォームです。さらに、MakeShopやBASEなどのEC特化型CMSも比較対象となります。
ここでは、それぞれのCMSの特徴や向いている用途を詳しく見ていきます。

WordPressは、世界中で圧倒的なシェアを誇るオープンソースCMSです。ブログから企業サイト、ECサイトまで、あらゆるジャンルに対応できる汎用性の高さが最大の魅力です。
メリット:
デメリット:
活用事例:
中小企業のコーポレートサイト、オウンドメディア、士業のブログ、医療機関の情報発信サイトなど。

Movable Type(MT)は、商用パッケージCMSとして高い信頼を得ている国産CMSです。WordPressと比べて堅牢性や静的出力に強みがあり、大手企業や自治体などに多数導入されています。
特徴・メリット:
デメリット:
導入に適した用途:


近年急速に利用者が増えているのが、ノーコードでWebサイトを構築できるCMSです。代表的なものには「Wix」や「STUDIO」があり、Web制作の専門知識がなくても直感的に操作できるのが大きな魅力です。
ノーコードCMSの魅力:
注意点:
向いているケース:
CMSのなかには、ECサイト(ネットショップ)の構築に特化したプラットフォームもあります。代表的なものが「MakeShop」や「BASE」で、ショッピングカート機能や在庫管理、決済システムなどが標準搭載されています。
EC向けCMSの特徴:
代表例の違い:
通常CMSとの違い:
CMSは非常に多くの種類が存在し、それぞれに異なる強みと弱点があります。自社の目的や運用体制に合ったものを選ばなければ、かえって管理負担やトラブルの原因になりかねません。ここでは、CMSを選定する際に特に重視すべき4つの観点を解説します。
CMS選定でまず最初に確認したいのが、社内でどこまで対応できるかという「運用スキル」との相性です。
たとえば、WordPressやMovable Typeのように自由度の高いCMSは、その分HTMLやCSS、プラグイン管理などの知識が求められます。社内にWeb担当者がいる企業であれば問題ありませんが、専門人材がいない場合は、トラブル対応やコンテンツ更新にストレスを感じる可能性があります。
一方、STUDIOやWixのようなノーコードCMSであれば、ドラッグ&ドロップで操作できるため、デザインやコーディングの知識がなくても扱えます。更新頻度が高く、スピーディに社内で情報発信を行いたい場合には、こうした操作性重視のCMSが適しています。
さらに、ECサイトであればMakeShopやBASEのように商品管理に特化したUIが備わっているCMSのほうが運用負荷を軽減できます。
社内で誰がどこまで関与するのか、外注する場合はどこを委託するのかを明確にしておくことが、後悔しないCMS選定の第一歩となります。
CMSを導入した直後は十分でも、事業の成長や業務プロセスの変化によって、「もっとこんな機能が欲しい」「外部システムと連携したい」といったニーズが生まれることがあります。
WordPressはプラグインが豊富で、問い合わせフォーム、予約システム、顧客管理、会員機能、SEO対策など、さまざまな追加機能に対応できます。さらに自社開発や外注を通じて、オリジナルのカスタマイズも可能です。柔軟性を重視するなら、拡張性に優れたCMSを選ぶべきです。
一方、ノーコードCMSや無料プランのEC特化型CMSでは、仕様が固定されており、独自の要件に対応できないこともあります。例えば、「外部の在庫管理システムとAPI連携したい」といった場合に制約がかかることがあります。
カスタマイズが必要な要件(会員機能、顧客別価格表示、多言語対応など)がある場合は、そのCMSで実現できるのか、どの程度の開発工数が必要かを事前に確認しておくと安心です。
CMSはWebサイトの根幹をなすシステムであるため、セキュリティ対策は必須です。特に個人情報を扱うサイト、ECサイト、医療・士業など機密性の高い業種では、セキュリティの甘さが致命的なリスクに直結します。
WordPressのようなオープンソースCMSは、脆弱性が公表されやすく、世界中の攻撃対象にもなりやすいという側面があります。その分、最新のセキュリティパッチが提供されており、正しく運用すれば高い安全性を保つことも可能です。
対して、Movable Typeのような商用CMSは、静的HTML出力による攻撃リスクの低減や、サポート付きライセンスによる定期的なメンテナンスが可能で、企業サイトや公共機関のように堅牢性を求める場面で信頼されています。
また、ノーコードCMSはセキュリティ対策がサービス提供者に一任されており、ユーザー側で個別設定できる範囲が限られていることもあります。簡単に使える反面、自由にセキュリティ強化できない点には注意が必要です。
サポート体制についても、無料のCMSでは自己解決が基本となりますが、有料のCMSや商用ライセンス付きCMSでは、トラブル時の問合せ先や技術サポートが用意されているケースが多く、社内に技術者がいない企業には大きな安心材料となります。
CMS選定において「結局いくらかかるのか」は非常に重要な判断材料です。ただし、単純な初期費用だけで比較すると、見落としてしまう点もあります。
WordPressの場合:
Movable Typeの場合:
ノーコードCMS(STUDIO、Wixなど)の場合:
EC向けCMS(MakeShop、BASEなど)の場合:
導入前には、「初期費用」「月額費用」「保守・更新コスト」「拡張時の追加費用」など、トータルでの運用コストを試算し、自社の予算に見合ったCMSを選定する必要があります。
CMSはただ選んで使い始めればよいというものではありません。導入には一定の準備と段階的な検討が必要で、特に初めてCMSを導入する企業にとっては、「何から始めればいいのか分からない」という声も少なくありません。ここでは、導入前に押さえておくべき要件や、社内と外部制作会社との連携ポイント、想定されるトラブルとその対策まで、導入を成功させるためのプロセスと注意点を解説します。
CMSの導入を検討する際、まず取り組むべきは「自社に必要な機能や目的」を明確にすることです。CMSの種類が多様化している現在、要件が曖昧なままでは、選定もスムーズに進みませんし、結果的に合わないツールを選んでしまうリスクもあります。
最低限、以下のような要件は導入前に整理しておきましょう。
また、将来的にサイト規模が大きくなる予定があるか、複数担当者で運用するのかといった運営体制の変化も見越した設計が求められます。要件を可視化することで、CMS選定や制作会社との打ち合わせが格段にスムーズになります。
CMSを導入する際、多くの企業ではサイト制作を外部の制作会社に委託するケースが一般的です。ただし、「すべてを任せれば安心」と考えて丸投げしてしまうと、公開後に「更新方法がわからない」「思っていた使い勝手と違う」といった問題に発展することがあります。そこで、事前に制作会社と自社の間で役割分担を明確にしておくことが、導入成功のカギとなります。
まず、CMSの選定や機能提案は、制作会社が主導して進めることが多くなります。ただし、その前提として、自社側は「何を実現したいか」「どんな情報を載せたいか」といった希望や要件を具体的に共有する必要があります。
サイト設計やUI設計も制作会社の担当範囲に含まれますが、自社がフィードバックを返しながら方向性をすり合わせていく姿勢が重要です。一方、サイトに掲載するコンテンツの原稿は、基本的には自社で準備します。制作会社が構成案や一部ライティングを支援することもありますが、企業の考えやサービス内容を正しく反映させるには、自社主導の情報提供が欠かせません。
また、写真やロゴなどの素材提供についても同様で、可能な限り自社で用意し、必要に応じて制作会社と撮影などを調整します。
操作マニュアルの作成は制作会社が対応することが多く、導入後はそれを基に社内で更新や管理を行います。公開後のサイト運用については、日々の更新業務は基本的に自社が行うべきですが、CMSの技術的な保守やセキュリティ対策は、保守契約を結ぶことで制作会社にサポートを依頼する体制も一般的です。
このように、CMS導入プロジェクトは「構築して終わり」ではなく、「運用する力を自社に根付かせる」ことが成功のポイントになります。そのためにも、導入初期の段階から担当者を決め、社内教育と並行して、制作会社との円滑な連携体制を構築しておくことが大切です。
CMSを導入してWebサイトを公開した後は、いかにスムーズに運用・管理していくかが重要です。構築時の利便性だけでなく、公開後の維持・改善を見据えた運用体制がなければ、せっかくのCMSのメリットを十分に活かすことができません。以下に、CMS運用時に特に意識すべき3つのポイントを解説します。
CMSはシステムである以上、脆弱性への対応が不可欠です。とくにWordPressなどのオープンソースCMSは、広く使われている分だけ攻撃対象にもなりやすく、放置しているとサイトの改ざんや情報漏洩などのリスクが高まります。
そのため、CMS本体・プラグイン・テーマのアップデートは定期的に行う必要があります。アップデート前にはバックアップを取得し、トラブル発生時にすぐに復元できる体制を整えておくことも大切です。
また、不正アクセス対策としてWAF(Web Application Firewall)の導入や、ログイン制限、二段階認証の設定も検討しましょう。保守管理は社内での対応が難しい場合、制作会社や専門業者と契約することでリスクを抑えることができます。
CMSは誰でも更新できる利便性が魅力ですが、その使いやすさを維持するためには、運用に関わる担当者の教育が欠かせません。特に複数人でコンテンツを更新する場合、誤操作によるレイアウト崩れや公開ミスなどが起こりやすくなります。
CMS導入時に制作会社から提供されるマニュアルを活用し、管理画面の基本操作や注意点、更新フローについて社内で共有しましょう。また、新しい担当者が入った際には、定期的な研修や引き継ぎの場を設けることが理想です。
さらに、CMSのバージョンアップに伴って操作画面が変わることもあるため、長期的には使い方を社内でキャッチアップし続ける体制が求められます。
CMSを効果的に運用するには、更新ルールやワークフローを明文化し、属人化を防ぐことが重要です。たとえば「誰が」「どの頻度で」「どのページを」「どういう手順で」更新するのかといった内容を社内マニュアルにまとめておくことで、業務の混乱を防ぎ、品質を一定に保つことができます。
また、更新内容のチェック体制(Wチェック・レビュー担当の設置)や、画像サイズ・掲載文言のトーン統一などもルール化しておくと、CMSを使った情報発信がより安定して継続できます。
こうしたルールは一度作れば終わりではなく、実際の運用状況に応じて随時見直すことが必要です。CMSの機能拡張や社内体制の変化にも柔軟に対応できるよう、継続的な改善を意識した運用が求められます。
WordPressの導入を検討している方におすすめの記事です。CMSの代表格ともいえるWordPressを使って、企業ホームページをどのように構築すればよいのかを、初心者にもわかりやすくステップごとに解説しています。自社サイト制作の第一歩として、ぜひ参考にしてください。
「費用をかけずにホームページを作りたい」「スマホだけで簡単に始めたい」という方にぴったりの一記事。無料で使えるスマホアプリを5つ紹介し、それぞれの特徴や使い方を丁寧にまとめています。CMSとあわせて、手軽な選択肢も視野に入れたい方におすすめです。
CMS(コンテンツマネジメントシステム)は、Webサイトの構築・運用を効率化するための強力なツールであり、その種類や特徴を正しく理解することで、自社に最適な選択が可能になります。
オープンソース型CMSはカスタマイズ性とコスト面で魅力があり、WordPressをはじめ多くの中小企業で採用されています。一方、クラウド型やSaaS型は保守の手間を減らし、スピーディなサイト立ち上げが可能で、更新頻度が高いプロジェクトに適しています。パッケージ型やフルスクラッチ型は、セキュリティや機能の独自性を重視する大規模サイトに向いています。
CMSを導入する際は、業種・規模・更新頻度・社内の運用体制などを総合的に考慮し、自社に合った種類を選ぶことが重要です。導入後も、セキュリティ対策や運用ルールの整備、管理者の教育を怠らず、継続的な改善と保守を行うことで、CMSの本来の価値を最大限に引き出せます。
自社にとってベストなCMSを選び、長期的な視点でWeb活用を成功に導いていきましょう。
「更新しやすいCMSにリプレイスしたい」「運用の手間を減らしたい」などの課題もお任せください。目的に応じたCMS導入からカスタマイズ、保守運用までサポートします。
▶ [CMS導入支援の詳細を見る]
関連記事

株式会社ARDEM
Company Profile
北海道札幌市を拠点に、全国の企業を対象としたホームページ制作・Web戦略支援を行う。
SEO対策やMEO施策、集客・採用強化、ブランディング、マーケティングなど、企業ごとの課題に応じた最適な提案と構築を強みとする。
「一緒に戦う理解者であれ」という想いから、表面的な制作にとどまらず、公開後のアクセス解析や運用支援まで一貫して対応。蓄積された実績と知見をもとに、成果に直結するWeb活用を支援している。